
一人暮らしの高齢者が、誰とも話さずに1日を終え、認知症が進行していくことに危機感を持つ人も多いのではないだろうか。2050年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になる(※)と言われる日本。認知症になってから対処するのではなく、認知症を予防するために今から実践できることとはあるのだろうか。
理化学研究所に所属し、ロボット工学博士であり認知症予防研究者である大武美保子さんは認知症予防のひとつに「会話」を挙げている。今回は大武さんに、認知症予防に大きな影響を与える「会話」について詳しく伺った。
※出典:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」

大武 美保子さん
理化学研究所ロボット工学博士・認知症予防研究者

堂上 研
株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長
1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。
https://ecotone.co.jp/
好奇心に溢れた幼少期を経て、発明家になるのが夢に

堂上:大武さんは会話支援ロボットの開発や、著書『脳が長持ちする会話』などで認知症予防を研究されています。大武さんは僕と同い年だと伺いました。認知症は、40~50代の我々にとって、親、そして自身の将来も含めて気になるトピックだと思います。今日はいろいろと教えてください。
大武:私は40~50代の同世代が75歳、80歳になった時に困らない状態にしたいという思いで『脳が長持ちする会話』を出版しました。女性で言えば、50代の10年間で骨量(骨密度)が減少しやすくなりますが、事前に骨が減りにくい運動をしたりカルシウムを摂っていたりすれば、70~80代になっても骨が折れにくくなります。
堂上:骨が折れて寝たきりになったり、それが原因で出かけなくなったりすると、認知症になりやすくなるのでしょうか。
大武:それは大きいですね。よく海老のように大きく背が曲がっている高齢の方がいらっしゃいますが、あれは実は骨折なんです。背骨と背骨の間の柔らかい骨がぐしゃっと潰れて、腰が曲がっている状態なんですね。
堂上:そうなんですか! 骨が折れているから起き上がれなくなっているんですね。大武さんは認知症予防について研究されているとのことですが、ロボット工学博士でもあります。ロボットと認知症はどのような関係があるのでしょうか。
大武:認知症予防が目的で、ロボットは手段です。ロボット工学を使って会話を支援したり場の雰囲気を作ったりするロボットを開発しています。
堂上:なるほど。後ほど詳しくお伺いできればと思いますが、そもそも、大武さんが認知症予防に取り組もうと思ったきっかけを教えていただけますか?
大武:東京大学で機械情報工学科に進んだ3年生の時に祖母が認知症になり、後に認知症予防について研究するきっかけとなりました。元々は文系も好きだったのですが、機械情報工学科は装置が必要な学科で独学をしにくいので、大学で学びたいと思いました。
堂上:もともとは文系がお好きだったとのことですが、幼少期は何をしているときが楽しかったですか?
大武:虫取りや木登りが好きでした! 東京生まれなのですが、駅からは遠く、竹藪や木登りできる木のある環境で育ったんです。学研の付録も大好きで、いろいろなものを混ぜると色が変わる実験キットや、カブトガニを育てるキットにワクワクしていました。
堂上:わかります! 学研の付録、懐かしいですね。僕もカマキリを捕まえたり、木登りしたりするのが好きでした。
大武:先日、自分の子どもにもカタツムリを見せてやりたいとマンションの管理人さんに話したら、管理人さんがカタツムリを千葉のご自宅付近で捕まえてきてくれて自宅で飼うことになりました。その後、繁殖して100匹くらいの卵がかえって大変なことになりました(笑)。
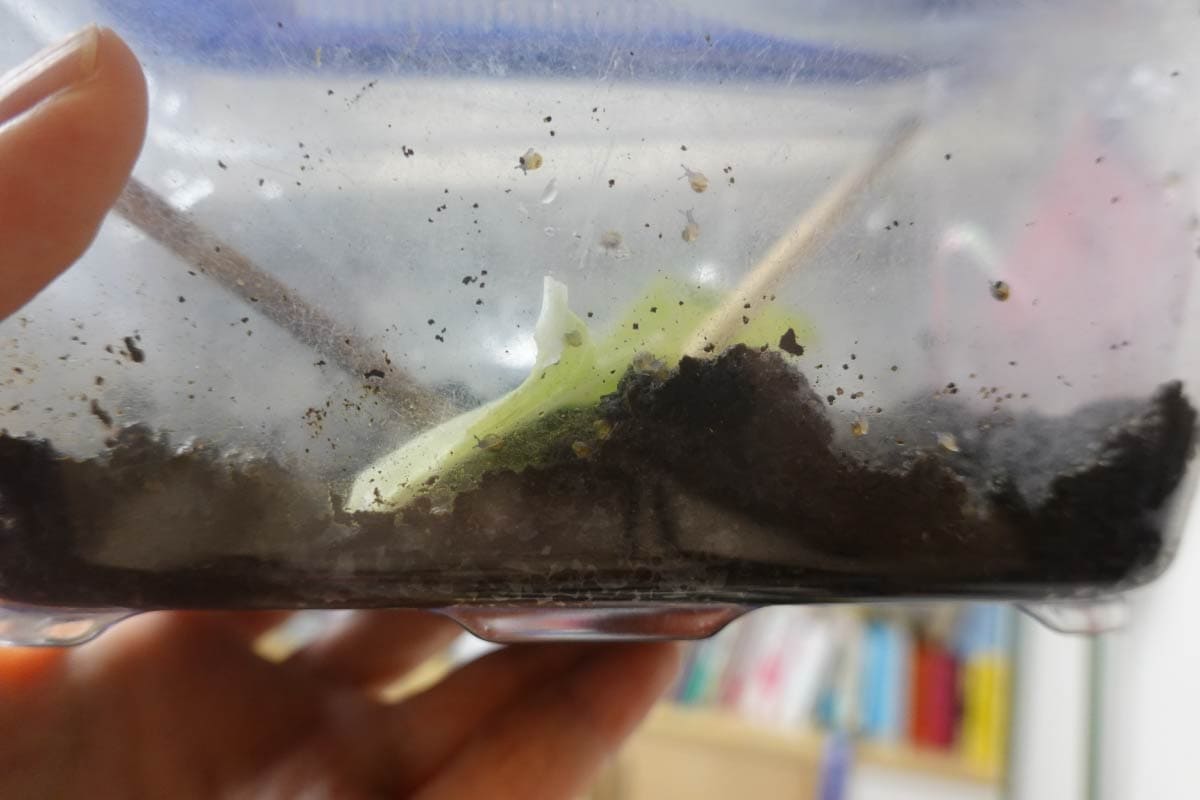
堂上:生態系が生まれていますね! 僕もカマキリの卵を自宅でかえしてワクワクしたのを思い出します。虫かごに入れずにペン立てに入れていたので母は大絶叫でしたけれど(笑)。好奇心旺盛なお子さんだったのですね。学校では部活をされていましたか?
大武:中学生の時は書道部でした。小学生の時に習っていた書道の先生が、昼間はスキーを滑って、夜は書道の先生をやられていて。その先生の生き方に憧れたんです。大学では「力を使わずに人を飛ばしてみたい」と思って合気道部に入りました。
堂上:新しいことにどんどん好奇心旺盛にチャレンジしていける人は、ウェルビーイング度が高いことが分かっています。大武さんはまさに、チャンスを逃さずに挑戦し続けているのが素敵です。ご両親の教育の影響もあったのでしょうか。
大武:好奇心を止めない育て方をしてくれたと思います。「女の子だからこっちのほうが良い」ということも言われませんでした。母は専業主婦なのですが、これからの時代は女性も働くようになるから、医者か弁護士、どちらかになれるように文系も理系も好きでいてくれると良いなと思っていたようです。結果的に工学部に進んだわけですが。
堂上:僕は「禁止を禁止する」という言葉が好きで、ウェルビーイングに欠かせないと思っており、ルールをなくした自由な環境ではイノベーションが起こりやすいと考えています。大武さんはそういった「禁止を禁止する」環境で育ったわけですね。とはいえ、僕は最近子どもにゲームのやりすぎを禁止してしまいました……。
大武:制約は創造の泉でもありますから、禁止ではなく制約と捉えたらどうでしょうか。
堂上:なるほど、制約の中でかいくぐろうとすることから創造性が生まれますね。大武さんが、医学部や生物学、物理学ではなく、工学に関心を持たれたのはなぜだったのでしょう。
大武:私はエジソンのような発明家に憧れがありました。「博士、何ができましたか?」と言われるような、発明をしてみたいと思っていたんです。
堂上:面白いですね。ウェルビーイングを探求する方々の中には、ロボット工学を学ばれている方も多いです。先日、Welluluに登場いただいた前野隆司先生も工学部機械工学科ご出身で、「人を幸せにするためのロボット、テクノロジーを作りたい」とお話されたのが印象的でした。大武さんも認知症予防のため、人がウェルビーイングな生活をするためのロボットを開発していらっしゃって、共通点を感じます。
大武:前野先生は大学院の時から研究を拝見していまして、学会の講演でもお会いすることがありますよ。
脳を活性化させるのは「武勇伝」ではなく「新しい話」

堂上:認知症予防についても伺っていきたいのですが、「会話」をすると認知症になりにくくなることは、研究結果で分かっているのでしょうか。
大武:はい。認知症予防のためには、その性質を持った会話が必要ですね。
堂上:会話には種類があるのですか?
大武:認知症予防に効果的なのは「頭を使う会話」です。例えば一方的に言いたいことを言って、相手の言葉を聞いていない場合は、脳が十分に働いていません。相手の言葉を受けて返す会話であることが重要です。
堂上:例えばテレビを見てテレビに向かって話しているだけ、とは違うということですね。
大武:何かを媒介して共通のことを考え、会話をするのがポイントです。私が会話訓練法として編み出した「共想法」では、好きな食べ物などの写真を持ってきてその写真の説明をし、他の人が質問するという形式をとっています。それぞれの視点をシェアし、人の数だけ多様な視点を持ち帰れるため、思考回路が回り出すんです。
堂上:僕は、これまでWelluluで約150人の方とお話させていただいて、その方の生き方や視点を吸収させてもらっている感覚があります。僕はもしかしたら、認知症になりにくいかもしれないですね。僕の父も、取材記事を読んで考えた感想を言ってくれるので、良い影響があるのかなと思いました。会話が重要なことは分かったのですが、高齢になると耳が遠くなり、聞こえにくくなると会話が億劫になることもありますよね。
大武:そうですね。だから恥ずかしがらずに補聴器をつけるということも大事です。どうしても会話が好きじゃなかったら、何かしらの情報の入力と出力をするということでも良いんですけれど、会話は聴覚も使うし筋肉も使うので、やはりおすすめしたいんです。
堂上:大武さんが開発されているロボットではどのように会話を促進されていますか。
大武:グループ会話の支援ロボット『ぼのちゃん』は場の雰囲気を作る役割を持っており、司会をすることで「共想法」を促します。また自主トレ用の小さいロボットも作っています。これはロボットに質問をすると答えてくれるので、会話の盛り上がる質問力を鍛えることができます。

堂上:認知症予防のために、家族ができることはあるでしょうか。
大武:意識的に会話をしたり、離れて暮らしているのであれば電話をかけたりすると良いと思います。本人にそこまでその気がなくても、周りが働きかけることで増やせるのが会話の良いところです。また、会話の中でも最近のことを話すのがお勧めです。本人から最近の話をしなくても、こちらが最近の話をするとか最近のことについて質問するなどして、ぜひ働きかけをしてみてください。
堂上:僕も親に電話して、話をよく聞いてあげないとダメですね。昔話ではなく、最近のことを話すのが良いのですか?
大武:昔の写真を見て記憶が呼び起こされ、新しい話が出てくるのは良い影響がありますよ。ただ毎回同じ話、いわゆる「武勇伝」ばかりする人は注意です。これは再生ボタンを押して話しているだけで、脳に負担がかかっていません。
堂上:新しい内容を導き出すのが重要だということですね。Wellulu編集部でも、週に1回、最近新しいと思ったこと・面白いと思ったことを発表してみると脳のトレーニングになるし、コミュニケーションにもなって良いかもしれないなぁ。
大武:良いと思いますよ。面白い話をしなければならないと思うと、身の回りに何か面白いことがないか注意を払い、面白いことをやってみたり面白い場所に行ってみたりしますよね。それも認知症予防に良いんです。注意を払う、体験する、記憶する、計画する。これらが大事です。
堂上:ウェルビーイングにも繋がるお話だなと思います。僕は子どもと夕食を食べている時に、「今日は何か楽しいことあった?」と聞くようにしているんです。最初、子どもたちは「普段と変わらない、何もなかった」と言っていたのですが、僕が毎回聞くので、段々と楽しいことを探し出したり、楽しいことを自分で作り出したりするようになりました。ウェルビーイングな生活を送るためには、まずウェルビーイングを意識することで、自分自身で楽しいことを作り出す能力が身につくんだと実感しています。
大武:ご家族と実践されていて素晴らしいですね。著書『脳が長持ちする会話』に対して、前野先生が「科学的研究に裏付けられた、幸せになれる会話の本」と推薦の言葉を寄せてくださいました。会話は脳を長持ちさせ、認知症を予防するだけでなく、ウェルビーイングにも繋がるのだと思います。
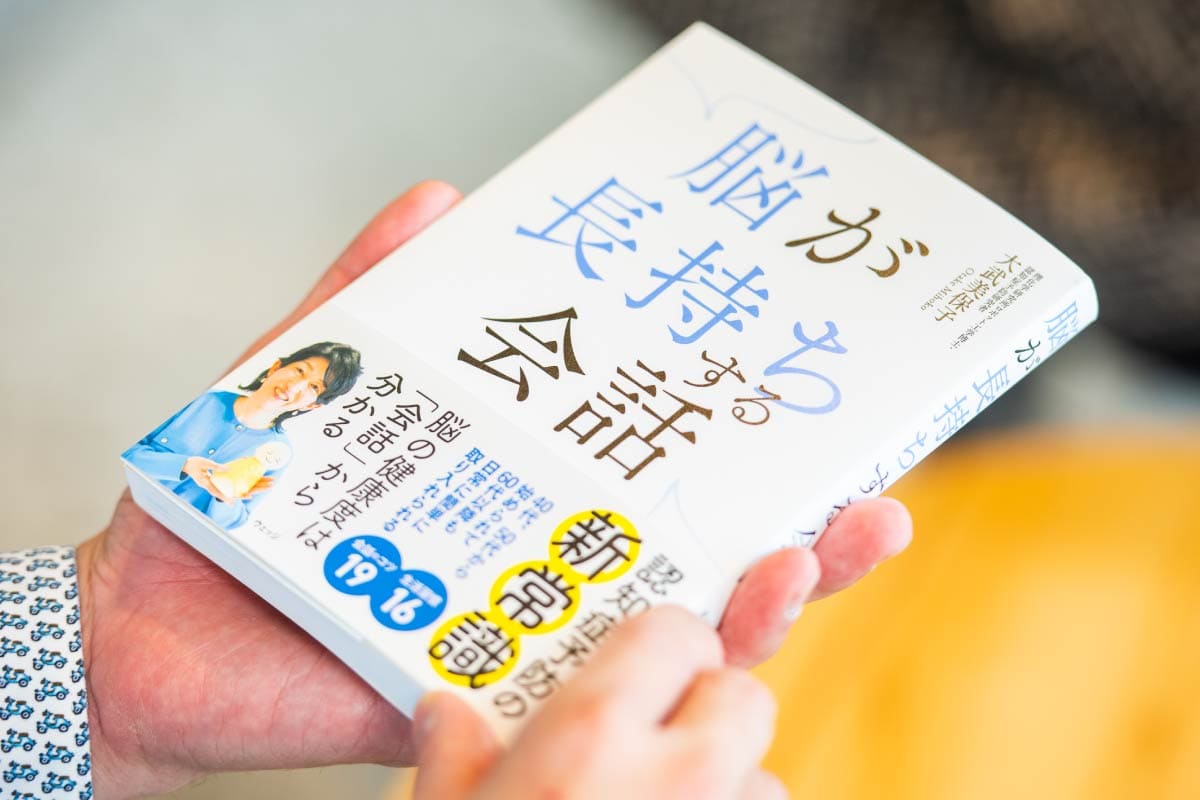
老化を遅らせる「運動」

堂上:会話のほかに、認知症予防に効果的なものはありますか。
大武:認知症発症を遅らせるというのは、①老化のスピードを遅らせること、②老化が進んでも認知機能への影響を小さくすること、の2軸があります。老化を遅らせるのが「運動」です。運動して代謝が上がると体の中の老廃物を捨てることができます。例えば、普段買い物にしか行かない人は、もっと運動が必要です。運動習慣がある人というのは、「週に2回以上、1回30分以上、1年以上、息の上がる運動をする人のこと」と厚生労働省では定義しています。
堂上:僕の母は買い物以外に運動をしていないかもしれないです。父も運動というとゴルフくらいかな。運動はやっぱり大事なんですね。
大武:体を動かすと、体を動かすための信号が脳から出てくるわけですが、歳をとって体が変化していったときに運動をしていないと、体の変化に脳の信号がついていけなくなります。例えば、転びやすくなる、足が思ったように上がらないなどが起こりますね。体を動かす=脳を作る、というところがあるので、やはり運動は大事です。我々団塊ジュニアの世代は、今運動をしておかないと20年後に筋肉が衰え始めてしまいます。
堂上:なるほど。僕は学生時代サッカーに熱中していたのですが、靭帯を切って入院して以降、ほとんど運動をしなくなりました。社会人になってからは夜遅くまで仕事をする日々が続いていましたが、最近、息子と毎朝サッカーをするようになったりパーソナルトレーナーに筋トレを見てもらうようになって、体が軽くなるのを体感しています。やっぱり運動は大事だなと思ったのですが、僕はたまたま息子からきっかけをもらったものの、多くの人はきっかけを掴みにくいと思います。大武さんはどんな運動をしていますか?
大武:マラソン好きの夫に苦しくなく走れる方法を教えてもらって、週に2〜3回、4km走るようにしています。走り方を学ぶと苦しまずに4㎞走れますし、体が柔らかくなります。走りながら研究したのですが、蹴った時に浮いている足が重力で引っ張られ、骨盤周りの筋肉が伸びるのも良いと思っています。
堂上:大武さんはいろいろなことが研究に繋がっていくのですね! あるコンサルティング会社の調査では、健康を意識して行動を変えられる人は10%以下だという結果があります。そこで僕は、①ポイントの獲得などインセンティブの設計、②ゲーム性などエンターテイメントの設計、③歩数を共有しあうなどコミュニティの設計の3つが重要だと考えています。
大武:習慣化はとても大切ですね。今、運動習慣のある人は40代女性で13%、50代女性で24%だと言われています。もしみんなが歯磨きをするのと同じくらい、当たり前に運動習慣を身につけられたら、未来は大きく変わると思います。散歩やラジオ体操などから始めてみて欲しいです。
必要な栄養素を詰め込んだ朝食

堂上:体が動かなくなってから困るのではなく、今行動を起こすことが重要ですね。睡眠という観点ではいかがでしょうか。
大武:睡眠も体の中の老廃物を捨ててくれるので大切です。
堂上:睡眠は自分自身にも、組織のウェルビーイングにも影響を与えると思っています。睡眠不足の時はイライラしてしまいますし、それが周囲に悪影響を与えてしまうし、脳にも悪い刺激がいっているんだろうなと思います。
大武:大切なのですが、私自身子育て中ということもあり、睡眠はしっかり取れていません。認知症のリスク要因はたくさんあって、例えば喫煙やアルコール過多、鬱なども挙げられるのですが、これら全てを完璧にクリアしている人はなかなかいないと思います。少しずつでも良いから始めてみること、また他でカバーすることが大事です。私の場合は睡眠が不足しがちですが、その分健康的な食事を摂ったり、運動をしたりするようにしています。
堂上:確かに全てを完璧にこなすのは難しいですよね。大武さんが食事で気をつけていること、習慣化していることは何でしょうか。
大武:必要な栄養素を摂れる朝食を考え、毎日ほぼ同じ内容のものを食べています。まず、キャベツと大根を細切りにしたサラダ。これにはシュレッドチーズをたっぷりかけて、煮干しと、紫蘇ニンニクかカツオニンニクのどちらかを入れています。そしてにんじん・切り干し大根・もやし・ひじき・わかめ・なめこ・豆腐・お麩が入った具沢山のお味噌汁。これは作り置きしています。あとは麦ご飯を卵かけご飯にするか、納豆ご飯にするかのどちらかです。卵かけご飯には、ちりめんじゃこ、ごま、オリーブオイルを混ぜ、もみ海苔をかけます。最初にゆず茶を飲み、最後にヨーグルトをいただきます。
堂上:ウィンナーとかハムなどのお肉は食べないんですね。
大武:チーズや卵、納豆、煮干しでタンパク質を摂っています。後は夕食でお肉やお魚を食べたり、たんぱく質の取れそうな昼食を摂ったりするようにしています。

堂上:なるほど。Welulluでも「食」は大きなトピックで、様々な記事を発信しています。とはいえ僕は白米が大好きでついつい食べすぎてしまいますし、企画書を作るときは片手にスナック菓子を食べるのが癖になっていて止められず、困っているのですが……。
大武:スナック菓子の代わりにもみ海苔を食べてみてはいかがですか? パリパリした食感もありますし、子どもたちもスナック菓子の代わりにもみ海苔を食べてハマっていますよ。
堂上:おお! 良いですね! チャレンジしてみます。
「脳が長持ちする」ための行動が当たり前の社会を目指して

堂上:「共想法」という言葉は、大武さんが生み出されたのですか。
大武:そうです。1960年代にバトラーという精神科医が「回想法」を提唱したのですが、それから寿命が伸び、新たな手法が必要だと考え「共想法」を編み出しました。共に想いを共有する、「コ・イマジネーション(Co-imagination)」が重要だと考えています。
堂上:僕はウェルビーイングという言葉を日本語訳するとしたら、「共生」がしっくりくるんです。共に生きる、それは人ともそうだし、自然や、自分とも共に生きるということだと思います。「共想法」にも繋がるなと思いました。
大武:私が代表を務めるNPO法人ほのぼの研究所では、高齢者の皆さんと「共想法」を毎月実践しています。今は60代以上の参加者が多いですが、認知症予防の当事者は40~50代だと考えていますので、ぜひ40~50代の方も、そして20〜30代の方にも参加してもらいたいです。
堂上:若い人たちにもぜひ参加していただきたいですね。最後に大武さんが今後やっていきたいことや、どんな社会をつくっていきたいか教えてください。
大武:研究者としては、会話が生き物の体に与える影響のメカニズムをもっと明らかにしたいです。例えば遺伝子の発現が変わるかもしれない、他の動物でも変わるかもしれないとか。生理的な変化も含めて脳がどう変わるのか、どういう状態の人に何がどう効くのか、仕組みをもっと明らかにし、それに基づいた技術を研究したいです。また研究だけでなく、社会実装として、「脳が長持ちする」という考え方が常識になり、運動や会話をするのが当たり前になる社会をつくりたい。そのために色々な発明をしていきたいと思います。
堂上:大武さんはやはり発明家ですね。虫を捕まえたり木に登ったりしていた少女が、発明家になっていく過程を見させてもらえた気がしました。脳が長持ちし、健康で生きる先には、きっと「幸せに生きる」というウェルビーイングな人生が待っていると思います。
会話がなぜ良いのか、ロジック的に説明することでみんなが信用し、行動を変えることが出来たらそれはひとつの発明だと思います。そして認知症予防とウェルビーイングは深い関連があることを改めて感じたので、僕らも一緒にそういった社会をつくっていきたいです。本日はありがとうございました!
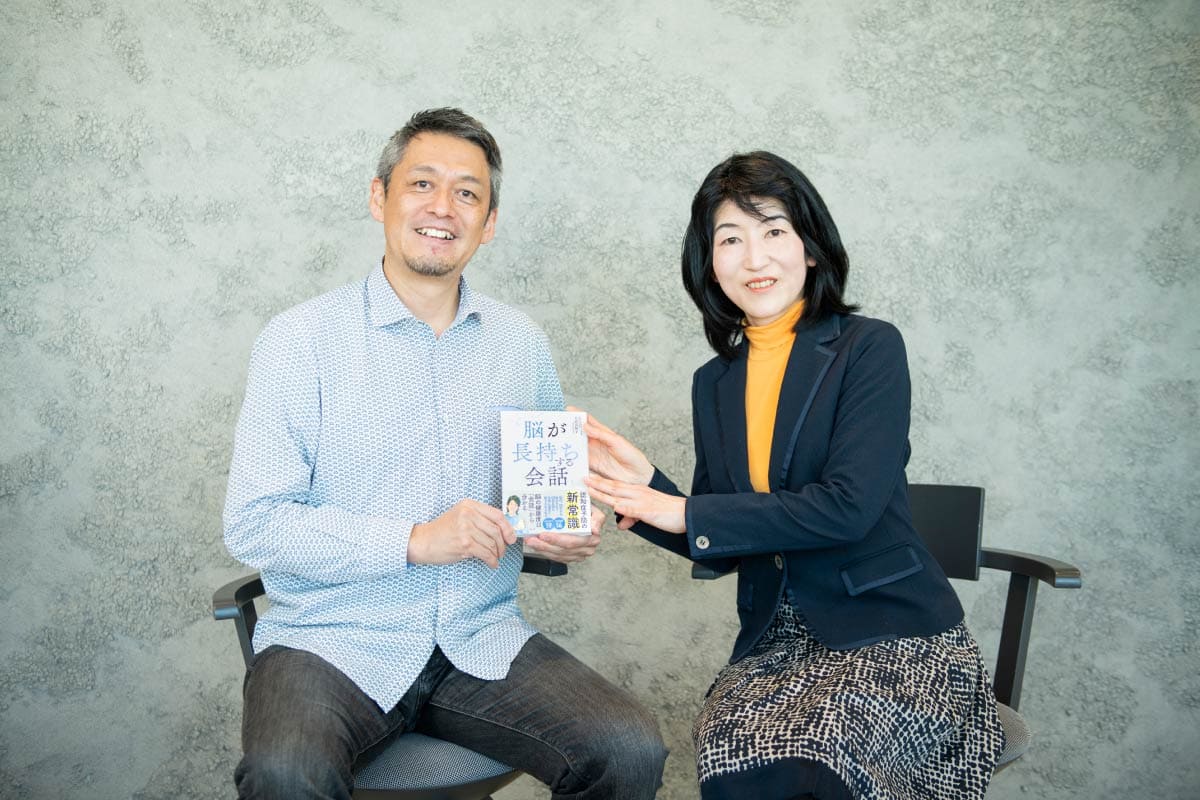

ロボット工学博士、理化学研究所 革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ 認知行動支援技術チーム チームリーダー。東京大学大学院博士課程修了。博士(工学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院特任助手、助教授、准教授などを経て現職。祖母の認知症をきっかけに、会話支援AIによる認知行動支援技術の開発に従事。会話訓練法として編み出した「共想法」と会話支援ロボット「ぼのちゃん」を活用した認知症予防支援にも取り組む。