
スポーツの世界では、ひとつの競技に専念することが当たり前とされてきた。
しかし、近年注目を集める「マルチスポーツ」という概念が、その常識を覆しつつある。異なるスポーツを複数経験することが、子どもたちの運動能力の向上や生涯スポーツの実践につながるとされ、研究が進められている。スポーツ用品メーカー「株式会社デサント」でマルチスポーツを体験できる場を提供し、筑波大学との共同研究にも乗り出している。
デサントの企業理念『すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを』を体現するために、どのような考えや想いを持ってプロジェクトを進行しているのか?株式会社デサント・牧さん、筑波大学教授・大山さんにお話を伺った。

大山 高さん
筑波大学教授/博士(スポーツ科学)

牧 太陽さん
株式会社デサント 経営企画室
2018年デサントジャパン株式会社に入社。野球カテゴリーの企画担当として、プロ野球球団のユニフォームやチームウェア等を企画。現在は経営企画室で新規事業開発、社会貢献活動に従事。学生時代は硬式野球部に所属し、小学校から大学まで野球一筋のスポーツ歴。高校時代には第81回選抜高校野球選手権大会に出場。
本記事のリリース情報
ウェルビーイングメディア「Wellulu」よりマルチスポーツに関する取材を受けました
秋・冬・春で種目を変える!アメリカの「スポーツサンプリング」制度

──まず始めにお伺いしたいのですが、「マルチスポーツ」を推奨している海外の事例について教えてください。
大山さん:アメリカの子どもたちは、秋・冬・春の3シーズンで取り組むスポーツ種目が異なります。このプログラム制度を「スポーツサンプリング」と言うのですが、いろいろなスポーツを「ちょっとかじって」自分が本当にやりたい種目を見つけることを目的としています。
単に身体的なスキルの向上だけでなく、主体的にスポーツを楽しむこと・生涯スポーツにつなげる機会を子どもたちに提供しているんです。
【日本の現状】スポーツとの関わり方

──私自身もそうなのですが、同じ種目を小・中・高と続けてきた身として、1年のなかで競技を変えるというイメージがしづらいですね…。
牧さん:そうですよね。実際に私たちデサントの社員も同じように「野球なら野球を続ける、サッカーならサッカーを続ける」みたいに同じ種目だけに没頭してきたスタッフの方が多いです。
大山さん:現状の日本だと「スポーツサンプリング」に対して、「中途半端・かじるだけで大したことしてない」なんて捉えられることもありますよね。
実際には自分の意思で「これをやりたい」と選ぶことで、内発的動機つまりスポーツを楽しむための原動力になります。また、このプロセスを経験した子どもたちは、成人後もスポーツを続ける傾向が強いとも言われています。
──「生涯、楽しんでスポーツを続けられる」機会の創出が、将来的な幸福度にもつながりそうですね。
大山さん:そのためにも、「スポーツサンプリング」や「マルチスポーツ」に対する意識を変えていくことが重要だと考えています。
日本では子どものスポーツとの関わり方が、本来の「スポーツを楽しむ」という部分から乖離してしまっているように感じます。たとえば、進学や推薦のために「スポーツを頑張る」という、進学のための“ツール化”が起きているように見えることさえあります。
なぜニュージーランドはラグビーが強いのか?

「1年中ラグビーするから、よくないのでは?」(指導者談)
大山さん:アメリカだけでなく「マルチスポーツ」を進めている国は、他にもいくつかあります。
ラグビーの強豪国・ニュージーランドもそのひとつです。クラブ活動に「シーズン制」が導入され、年2回スポーツを切り替えることが義務付けられています。
──半年間しか取り組んでいないのに、あんなに強いんですね…。(世界ランキング3位:2025年2月時点)
牧さん:「オールブラックス」の愛称で知られるニュージーランド代表と日本代表の試合は記憶に新しく、観戦した人も多いと思います。
オールブラックスの指導者に「なぜそんなに強いのか?」を聞いたところ、「日本は1年中ラグビーをやっているからよくないのでは?」と答えられた。という話も耳にしたことがあります。

大山さん:また、練習時間も日本とニュージーランドでは異なります。
オールブラックスの選手を最も多く輩出した学校では、週に5時間だけフィジカルトレーニングがおこなわれています。これに対して、日本の部活動では長時間の練習が一般的で、ほとんど毎日おこなわれていると思います。
半年間のみ・練習時間も週に2〜3日と短いにも関わらず、ニュージーランドはラグビーの強豪国として有名です。
──週にたった2〜3日とは…。それ以外はオフということですか?
大山さん:そうです。このオフを与えている理由は「ウェルビーイング(バランス)」という部分にあります。ニュージーランドの教育では、子どもたちがいろいろなスポーツを経験する、つまり「サンプリング」が奨励されています。これは「多様なスポーツに取り組むことで身体のバランスを保ち、アスリートとしてだけではなく、人としてのウェルビーイングが向上することにつながる」という考えが教育の根本にあるんですね。
──そう聞くとやはり日本の部活動は1つにとにかく入魂!というか、ほかを見る感覚はないですね。
マルチスポーツが子どものウェルビーイングを高める

大山さん:最近ニュージーランドでは、11歳から17歳の子どもを対象にした、1つのスポーツに集中するか、複数やるか、どちらがウェルビーイングが高くなるかという研究がおこなわれ、国際誌にも取り上げられました。
この研究では、世界中で広く採用されているOECD(経済協力開発機構)の基準を用いて「主観的ウェルビーイング」の測定をおこないました。これは参加者が自身の幸福感を1から10の尺度で評価するもので、7以上をウェルビーイングが高いと評価します。
その結果、3~5種類のスポーツをおこなう子どもたちは、1つの競技に集中する子どもよりウェルビーイングが高いことが明らかになりました。
──その結果をお伺いすると、複数のスポーツを楽しんでほしいと感じますね!
大山さん:ウェルビーイングを高める要因として「バランス」を取ることというのは、自律性と有能感、関係性(社会的な関わり)といった3つの観点から捉えられています。
まず、子どもが自分で決めるという自律性、自己決定感ですが、マルチスポーツであれば複数の選択肢から自分が種目を決めることが多いと思います。
次に、有能感ですね。運動を通じて「自分ができる」と感じる、つまり運動有能感なのですが、マルチスポーツではこの感覚を何度も経験できる機会があります。
あとは社会的な関わりですが、さまざまなスポーツに参加することで、出会う人々の幅が広がります。年齢や性別、背景の異なるバラエティ豊かな交流は、多様な人々との関係性の構築が可能です。

──ウェルビーイングを高める機会がとにかく多くなりますね。トップアスリートを目指すためには一つの競技に集中すべきだという意見の方が一般的な気もしますが、どう思われますか?
大山さん:単一のスポーツに専念することもよいことだと思います。ただ、燃え尽き症候群(バーンアウト)やケガの発症率が高くなることが最近では指摘されています。
スポーツは長い人生の中で健康や楽しさを支える重要な要素であるべきです。
ウェルビーイングの観点から見ても、複数のスポーツを経験する「マルチスポーツ」が、心身の健康を保ち、スポーツを生涯楽しむ基盤を築くうえで適していると言えます。
日本で「マルチスポーツ」を浸透させるために
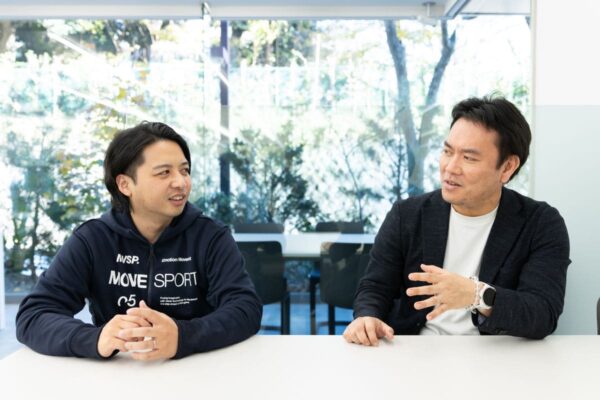
──先ほど「マルチスポーツ」を浸透させるためには、まずは意識を変えることから!とお伺いしましたが、具体的にどういったアプローチが重要だとお考えでしょうか?
大山さん:海外の事例をそのまま取り入れるだけでは、日本には合わない部分もあります。
日本には独自のよさがたくさんありますので、それを基盤にアレンジを加えることが大切だと思います。
具体的な例を挙げると、日本の子どもたちは小学1年生の頃から自分で歩いて学校に行くことが一般的です。これ自体が、子どもたちの社会性を育む貴重な機会になっています。
諸外国ではスクールバスなどによる送迎が多く、子どもだけで外を移動するという文化がほとんどありません。この「安全で子どもが自由に動ける環境」という日本の特性を、スポーツ教育にも活かすべきだと思います。
──確かに。地域の方と挨拶しながら、登下校する様子もよく目にします。その強み(安全な環境・社会とのつながり)をスポーツ教育にどう活かすべきでしょうか?
大山さん:学校施設をもっと地域のスポーツ活動に開放した方がよいと考えています。現在、多くの学校は外部の人の立ち入りを制限しており、クローズドな状態です。
しかし、学校が地域の人々や子どもたちが自由にスポーツを楽しめる場として開放されれば、多様なスポーツの接触機会を増やすきっかけになると思います。

──なるほど。ちなみに学校開放が具体的にどのような効果をもたらすとお考えですか?
大山さん:学校開放が進むことで、以下のような効果が期待されます。
- スポーツの多様な経験
学校の設備や遊具を利用することで、子どもたちがさまざまなスポーツに触れる機会が増えます。地域のコーチや保護者が指導に参加することで、競技の選択肢も広がります。 - 地域コミュニティの活性化
学校が地域スポーツの中心となることで、老若男女が交流する機会が増えます。ニュージーランドの学校は地域のスポーツ活動の場として積極的に開放されています。 - 安全性の向上
地域の人も巻き込んで、学校が地域全体で見守られる場として活用できれば、安全性を担保しつつスポーツの機会を増やせます。
また、指導者や保護者に対する啓発活動も欠かせません。
「成果を出すために努力する」だけでなく、スポーツを通じて心身の健康を育むことの大切さを子どもたちに伝え、楽しみながら成長できる環境を整える必要があります。
牧さん:また、「スポーツをする場所」の不足も近年の課題になっています。
豊島区とマルチスポーツ活動を進める活動をしているのですが、どこで開催するかという問題が最も大きなハードルになりました。学校が開放されれば、これが大きく解消されるはずです。学校という身近でアクセスしやすい場所が利用できれば、多くの人が気軽にスポーツを楽しむことができます。
【デサントの取り組み例】マルチスポーツ部

自律性・自己肯定感を高めるプログラム

──豊島区と取り組んでいる体験活動「マルチスポーツ部」について詳しく教えてください。
牧さん:「マルチスポーツ部」は、デサントが豊島区等と一緒に行っている地域スポーツ推進プロジェクトです。
デサントが掲げる「すべての人々にスポーツの楽しさを」という企業理念を軸に、子どもたちや地域住民が多様なスポーツを体験できる場を提供することを目指しています。
「マルチスポーツ部」という枠組みを立ち上げ、プログラムやイベントを実施しています。また、マルチスポーツの効果を科学的に検証するために、アンケートを通じて参加者の意識や行動の変化を調査し、筑波大学と共同で分析を進めています。
──マルチスポーツ体験だけでなく、研究や調査までおこなっているのですね。主な対象となるのは中学生なのでしょうか?
大山さん:小学生を対象にした活動も実施しています。
──小学生と中学生でプログラムの内容はことなるのでしょうか?
大山さん:「自己決定理論」の観点から重要とされる「自律性・有能感・関係性」を感じやすい環境を意識しています。
──「自己決定理論」とはどのような理論なのでしょうか?
大山さん:自己決定理論は、人間が満たしたい基本的な欲求として「自律性(自分で選ぶことができる)」「有能感(自分ができると感じる)」「関係性(他者とつながりを持つ)」の三つを挙げています。この欲求が満たされると、ウェルビーイングが高まると言われています。
この理論を軸にプログラムをつくることで、子どもたちが主体的に楽しみながら成長できる環境を整えています。具体的には、どのスポーツを体験するか?・どう参加するか?を子どもたちに選ばせることで、この3つの要素を満たすことにつながると考えています。
──これからの課題や展望について教えてください。
大山さん:私たちが提供しているプログラムが、子どもたちにどのような影響を与えるのかを定量的に測る準備を進めています。具体的には、自己決定理論の指標を用い、主観的ウェルビーイングを数値化して分析します。このデータを通じて、「マルチスポーツ」が子どもたちの幸福感や自己肯定感にどのような影響を与えるかを明らかにしていきます。
また、スポーツ活動中に「フロー状態」に入れるかどうかも注目しています。フロー状態とは、何かに深く没頭し、時間を忘れるほど集中している状態のことです。この状態を体験することが、スポーツ活動をより楽しいものにするだけでなく、自己成長にもつながると考えています。
新しい価値観を持つ大人との出合い

──「マルチスポーツ部」の中で、特に印象に残っているイベントについて教えてください。
牧さん:中学生向けプログラムで実施したブレイキンの体験が、特に印象に残っています。
──かなりアクロバットなスポーツ体験も入っているんですね!普段、生活をしている中であまり触れる機会は確かに少なそうです。
牧さん:はい。豊島区の中学生7名が参加し、9~11月の2ヶ月間・週1回のペースで、プロのダンサーに指導してもらいました。普段の部活動では体験できない新しいスポーツに挑戦する機会を提供できたのは非常に意義がありました。
そして、11月に開催された「TOSHIMA STREET FES」で練習の成果を発表してもらいました。初心者だった子どもたちが、短期間で本格的なブレイキンの技術を身につけ、多くの観客の前で素晴らしいパフォーマンスを披露したんです。
初めて体験するスポーツで「ここまでできた」という成功体験は、彼らの自己肯定感を大きく育んだと思います。
──発表する場も提供しているのが素晴らしいですね。成長を身をもって経験できるというか…。
牧さん:発表を見た保護者も、彼らの成長ぶりに感動されていました。
また、指導者との交流もいい経験になったと感じています。ブレイキンだけでなく、パルクールに取り組んだ子どもたちもいるのですが、普段の学校生活で接する大人とはまた違う個性的な人と交流する時間は刺激的だったと思います。
──確かに。さまざまな価値観を持つ大人とのコミュニケーションも重要な経験になりそうですね。
牧さん:指導者との交流を通じて、子供たちはスポーツを学ぶだけでなく、新しい価値観や世界観にも触れることができます。その過程で、表情や姿勢に大きな変化が現れ、人間的にも豊かになったと感じます。
子どもたちの運動能力を高め、新しい経験を!

──デサントが提供するプログラムでは、ブレイキンやパルクールだけでなく、他にも多様な種目が体験できると思います。どのようにスポーツ種目を選んでいるのでしょうか?
牧さん:イベントで選ぶスポーツは、大きく分けて三つの要素を考慮しています。まず一つ目は、 基本的な運動能力を育むことです。たとえば「走る」「投げる」「蹴る」といった動作は、どのスポーツでも基盤となる動きです。
二つ目は、地域性や主催者の意図です。豊島区などの都心では場所に限りがあります。そういった地域の特色やリソースを活かしたスポーツを選んでいます。また、主催する企業や団体が得意とするスポーツや関係するアスリートを招待することで、イベントがより魅力的にもなります。
三つ目は、子供たちにとって新鮮で楽しい体験を提供することです。普段の部活動や習い事では経験できないスポーツを取り入れることで、子供たちの好奇心を刺激し、「こんなスポーツもあるんだ!」と気づいてもらえる場にしたいと思っています。
──実際にプログラムを通じての反応はいかがでしょうか?
牧さん:非常にポジティブな反応が多かったです。
8月に開催した別のマルチスポーツイベントのアンケートでは、9割以上の保護者が「単一のスポーツではなく、多様なスポーツを経験させたい」と回答しています。子どもたちだけでなく、親御さんから「マルチスポーツ」という考え方を初めて知った方も多く、「こういうアプローチがあるんですね」と驚かれていました。
中には「こうした環境がもっと身近にあれば、子供たちにとって非常に良い経験になるのでは?」という具体的な要望を寄せていただいた方もいました。
──なるほど。最後に、今後マルチスポーツをどのように広めていく予定でしょうか?
牧さん:地域の教育委員会や行政とも連携しながら、マルチスポーツの価値を伝えていきたいと思います。そのためには、子どもたちだけでなく、親御さんや地域の方々にもスポーツの楽しさを実感してもらうことが大切です。
また、今回の「TOSHIMA STREET FES」のようなイベントを活用し、スポーツを「体験して楽しむ」だけでなく、「見て応援する」文化を育むことも重要だと考えています。まだ試行錯誤の段階ですが、一歩ずつ進めていきたいと思っています。
Wellulu編集後記:
今回の取材を通じて、マルチスポーツが単なる運動スキルの向上にとどまらず、子どもたちのウェルビーイングや自己肯定感の向上にもつながるという点が非常に印象的でした。海外のように複数のスポーツを経験することで、より柔軟で多様な運動能力を育むという考え方がもっと浸透していけばいいなと思いました。
スポーツは「続けること」だけがすべてではなく、「楽しむこと」「自分に合った形で関わること」が大切なのかもしれません。

1979年生まれ。東京都府中市出身。ニュージーランドの現地高校を卒業し、2000年に立命館アジア太平洋大学へ入学。大学卒業後は三洋電機、楽天ヴィッセル神戸、博報堂等の民間企業にて主にスポーツの宣伝広報業務に従事。その後、自身が得た海外での運動部活動(シーズン制)の経験をベースにマルチスポーツ教育政策研究をはじめる。著書に「マルチスポーツを科学する(青娥書房)」他がある。