
ストレングス&コンディショニングの世界的権威である「NSCA」の日本支部、「NSCAジャパン」の施設にて、研究に裏付けられたトレーニングを実際に体験!子どもから大人まで身につけたい怪我の予防や、健康で楽しくスポーツし続けるために大切なポイントなど、詳しいお話を伺ってきました。

吉田 直人さん
特定非営利活動法人 NSCAジャパン/ヒューマンパフォーマンスセンター ストレングス&コンディショニングコーチ
本記事のリリース情報
【メディア情報】ウェブメディア「Wellulu(ウェルル)様」よりNSCAジャパンが取材を受けました
「NSCAジャパン」のトレーニング体験へ

今回体験にやって来たのは、千葉県流山市にある「NSCAジャパン」のトレーニング施設「Human Performance Center」(以下「HPC」)。HPCは、NSCA会員が使用できる施設で、知識の普及や指導者の教育・育成などに関するさまざまな設備をそろえている。
施設内には講義や実技指導をおこなう会議室もあり、週末は施設をクローズしてセミナーや研修会を開催することもあるそう。

さらに、HPCでは一般の人々を対象とした少人数制グループレッスンもおこなっており、1時間程度のストレッチや軽い筋力トレーニング、継続プログラムを通して参加者の健康改善や運動習慣の定着を目指している。
まずは早速トレーニングウェアに着替え、いざ体験スタート!
カウンセリングで自分の身体について知る

吉田さん:普段はどのような運動をされていますか?
──たまにランニングをするくらいで、ジムに通ったりはしていません。
吉田さん:現在、肩こりや腰痛など、気になる身体の部位はありますか?
──デスクワークが多く、慢性的な肩こりに悩んでいますが、とくにケアもできていない状態ですね…。また、移動手段としてよく自転車に乗るので足の筋肉はあるほうですが、上半身にはあまり筋肉がありません。腕立て伏せなどのトレーニングも苦手で、上半身と下半身の筋肉のアンバランスさが気になっています。
吉田さん:そうなんですね。トレーニングを通しての目標はありますか?

──体重を落とすダイエットのような数字的目標ではなく、見た目的に引き締まった身体づくりを目標としたいです。上半身の筋肉がなく、筋トレも苦手だからこそ、腹筋や腕まわりが鍛えられている身体は憧れますね。
吉田さん:ランニングや自転車に乗ることが多いとのことですが、有酸素運動のしすぎも筋肉がつきづらい原因となります。健康のためには、やはり筋肉も重要です。筋肉は加齢とともに落ちていってしまうので、トレーニングをして筋肉量を維持したり、落ち幅を少なくするのが大切ですよ。
また、肩こりの原因にも筋肉が関係しています。人間の頭は意外と重く、それを肩や首の筋肉が支えています。男性に比べ、女性のほうが肩こりに悩む人が多い理由に、肩の筋力不足があります。もともと女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、肩こりの不調を感じやすいんです。
──体重を落とすダイエットのような数字的目標ではなく、見た目的に引き締まった身体づくりを目標としたいです。上半身の筋肉がなく、筋トレも苦手だからこそ、腹筋や腕まわりが鍛えられている身体は憧れますね。
吉田さん:ランニングや自転車に乗ることが多いとのことですが、有酸素運動のしすぎも筋肉がつきづらい原因となります。健康のためには、やはり筋肉も重要です。筋肉は加齢とともに落ちていってしまうので、トレーニングをして筋肉量を維持したり、落ち幅を少なくするのが大切ですよ。
また、肩こりの原因にも筋肉が関係しています。人間の頭は意外と重く、それを肩や首の筋肉が支えています。男性に比べ、女性のほうが肩こりに悩む人が多い理由に、肩の筋力不足があります。もともと女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、肩こりの不調を感じやすいんです。

──マッサージではなく、トレーニングで筋肉をつけることが肩こりの改善につながるんですね!
吉田さん:筋肉のほかに、姿勢も肩こりに影響します。デスクワークだとつい肩が前にでやすく、肩まわりへの負担が大きくなります。ここで、現在の姿勢を確認してみましょう!いつも通りに立ってみてください。

トレーニング前の立ち姿・正面

トレーニング前の立ち姿・横
吉田さん:本来耳の下に肩がくるのが正しい姿勢ですが、だいぶ肩が前にきているのがわかると思います。また、おそらく普段バッグなどを同じ肩にかけていますか?左右の肩の高さに差が見られますね。
──本当だ…!改めて鏡の前に立って自分の姿勢を見てみると、身体の歪みがわかりますね。ずばり右ばかりバッグをかけるくせがありますが、右肩が下がっていますね…!意識して肩に力を入れないと、耳の下にきません。
吉田さん:誰にでも身体の左右差はありますが、悪化すると歪みとなり、不調につながっていきます。疲れにくい身体をつくるために、本日はトレーニングで身体を正しい姿勢にしていくことを意識しながらおこなっていきましょう!
──鍛えるというよりも、トレーニングを通して身体を整え、日常生活を正しい姿勢で過ごせるようになるイメージですね。まき肩、そして肩こりを改善するべく頑張ります!
【体験1】肩甲骨、背骨(胸椎)、股関節のストレッチ
筋トレだけでなく、柔軟性や可動域、バランスなど、対象者に合ったトレーニング内容にカスタマイズするのが「ストレングス&コンディショニング」の考えの特徴。カウンセリング内容から、本日の体験では肩まわりや腹筋など、上半身中心にトレーニングをおこなうことに。

まずは、マットの上でストレッチポールを使って肩甲骨まわりをほぐしていく。前後比較するために、何もない状態でマットの上に仰向けになったときの背中の密着度を覚えておこう。吉田さん指導のもと、ストレッチポールの上で腕を上下左右に動かしたりと、肩甲骨まわりをしっかり動かしていく。最後に再びストレッチポールを外してマットの上で仰向けになり、背中の密着度を感じる。

──ストレッチ前に比べ、マットに密着する背中の面積が増えた気がします!
吉田さん:ストレッチポールの上でおこなうことで、肩甲骨がより動きやすい状態になります。日常生活では動かしづらい部分を意識的に動かすことで、身体の変化が感じられますよ。運動パフォーマンスの向上やスムーズな日常動作のためにも、普段から肩甲骨はよく動かしてくださいね。

肩甲骨をほぐした後は、背骨のストレッチ。四つん這いの姿勢になり、背中を丸めたり反らせたりと、背骨を意識しながらしなやかに動かしていく。
──肩甲骨と背骨のストレッチで、すでに身体があたたまってきました。
吉田さん:筋肉と関節がよく動かせている証拠ですね。「モビリティ」といって、単純なストレッチとは異なり、身体の可動性を高めることを目的としています。筋肉と関節を動かしながら、筋肉と神経の連動を高めることは、怪我の予防や健康的な身体づくりの基本です。よりしなやかで動ける身体づくりのために、強さだけでなく柔らかさやバランスを意識したトレーニングも意識してみてください。

──つい筋肉にばかり集中しがちでしたが、関節を意識することも大切なんですね。
吉田さん:関節には、動かすべき関節と安定させるべき(あまり動き過ぎない)関節があります。肩甲骨・胸椎・股関節は動かすべき関節であるのに対し、腰は安定させるべき関節です。反り腰になると腰痛を感じるように、安定させるべき関節を動かしてしまうと痛みが生じてしまいます。また、動かすべき関節をうまく動かせていないと、腰が代償として動き、結果として怪我につながります。トレーニングで動かすべき関節を正しく動かして可動域を広げ、怪我のしにくい身体をつくっていきましょう。
──関節から正しい姿勢づくりは始まっているんですね。

肩甲骨、背骨の後は、股関節のストレッチ。動かすべき関節をよく伸ばし、ストレッチで身体全体があたたまったところで、本格的に動いていく準備はばっちり!
【体験2】上半身の筋肉トレーニング

まき肩を改善し、肩こりの不調を解消することを目的にカスタマイズしてもらったトレーニングを実践。バンドを使った肩甲骨まわりのエクササイズは、上がりがちな肩や反り腰に注意しながら、肩甲骨を寄せるイメージでおこなう。
吉田さん:後ろ(背中)側のトレーニングの後は、前側(胸)側のストレッチもおこないます。肩甲骨を鍛えた後に大胸筋をストレッチするなど、前後バランスのとれたトレーニングが効果的です。

──右よりも左のほうが痛いような、身体の硬さを感じます。
吉田さん:左右差を感じることも、自分の身体を知る上で大切です。まき肩を改善するためには、より背中を強くするために、前側を1種目に対し、後ろ側を2種目おこなうのがバランス的におすすめですよ。
次は、腕立て伏せに挑戦してみましょう!女性の場合は苦手な方も多いと思うので、ベンチを使って膝立ちの状態でおこなっても大丈夫です。

吉田さん:手を肩幅程度に広げ、指先はまっすぐかやや内側に向けます。指先が外側を向くと肩がねじれ、怪我のリスクが高まるので気をつけましょう。手幅を狭くすると上腕三頭筋に、広くすると大胸筋に効果があります。
──床での腕立てはほとんどできませんが、ベンチを使うことで身体のフォームを意識しやすいです。

吉田さん:ただ、どうしても反り腰になりがちなので、腰痛のリスクがあります。頭から腰まで真っ直ぐの姿勢をより意識するためのツールとして、棒を後頭部・肩甲骨・腰の3点にしっかり当てた状態で維持しながらもう一度やってみてください。
──ツールを利用して身体に正しい姿勢を覚えさせるのもわかりやすいですね!
【体験3】下半身の筋肉と腹筋のトレーニング

上半身の後は、下半身のトレーニングにもいくつか挑戦。スプリットスクワットは、両足を前後に開いておこなうスクワット。通常のスクワットよりも腰への負担が少なく、股関節や足の筋力をバランス良く鍛えられる。腰を反りやすい人や、スクワットが苦手な人におすすめ。
──股関節をよくストレッチしたこともあり、いつもより大きく動けている気がします。
吉田さん:初心者は自重で始めてみて、フォームに慣れてきたらダンベルやケトルベルなどを使用して負荷をつけてみてください。負荷を加えることで、下半身の筋肉をより効果的に鍛えられますよ。

吉田さん:トレーニングでは、「正しいフォーム」と「適切な負荷」が大切なポイントです。フォームが崩れると、鍛えたい筋肉ではなく、ほかの部位に余計な負担がかかります。また、負荷が軽すぎても効果が薄く、重すぎると怪我のリスクが高まります。これらのポイントを意識してトレーニングに取り組むと、より高い効果が期待できますよ。
──正しいフォームと負荷でのトレーニングが、筋力アップだけでなく、全身のバランス改善や怪我の予防につながるんですね!

吉田さん:最後は体幹トレーニングとして腹筋をおこないましょう。ここでも反り腰にならないことが、より腹筋を鍛え、怪我のリスクを減らします。手をお尻の下に置くことで、坐骨が後傾し、反り腰を防ぐ効果がありますよ。

吉田さん:腹筋は、身体の重心のバランスのとり方が重要。自分の身体の重心がわかっている状態で腹筋を動かしていけるようになると、体幹が安定し、スポーツや日常動作でのバランス感覚が向上します。ストレングス&コンディショニングのトレーニングでは、スポーツパフォーマンスだけでなく、転倒予防の観点などでもバランス感覚を大切にしています。自重のトレーニングを中心に、身体の重心やバランス感覚を養っていただけたらと思います。
──自分の身体の重心の感覚を知ること。脳と神経と筋肉がうまく連動してこそ、正しく動けるんですね!
トレーニング前後での身体の変化

トレーニング後の立ち姿・正面

トレーニング後の立ち姿・横
──鏡の前に立ってびっくり。肩の位置が後ろに下がり、耳の下に近づきました!
吉田さん:少しでも身体を動かすことによって身体の感覚センサーが活性化され、自然によい姿勢がつくりやすくなるんです。トレーニングを通して、身体を動かすことの重要性が伝わったらいいなと思います。
初めてのストレングス&コンディショニングのトレーニング体験。鏡に映る自らの姿勢の変化に、トレーニングのやりがいを感じる。まき肩の悩みが改善しただけでなく、血流もよくなりすっきりした気分で体験は終了。
インストラクター吉田さんにインタビュー

トレーニング体験後は、インストラクターの吉田さんにストレングス&コンディショニングトレーニングの特徴など気になる疑問を聞いてみた。
「怪我予防」の考えから生まれたNSCA
── まず、「NSCA」について教えてください。

吉田さん:NSCAとは「National Strength and Conditioning Association(ナショナル・ストレングス&コンディショニング・アソシエーション)」の略で、アメリカに本部を持つ国際的教育団体です。研究に裏付けられた知識の普及と、健康やスポーツ現場への応用を支援するために、1978年に設立されました。NSCAジャパンは、1991年に設立された最初の支部です。
── 日本支部は30年以上の歴史があるんですね。NSCA発足にはどのような背景があったのでしょうか?
吉田さん:NSCA発足の背景に、アメリカではアメリカンフットボールが盛んな文化の中、同時に怪我が多いという課題がありました。「こんなに怪我が多いスポーツが本当によいものなのか?」という疑問をきっかけに、怪我を予防するためにトレーニングコーチが集まってつくった団体がNSCAです。設立当初から「怪我の予防」を第一の目標としています。
約30年前の日本でも、「怪我の予防」というと、治療などの対処が主流で、NSCAが提唱する「トレーニングによる予防」という考え方はほとんど浸透していませんでした。NSCAの怪我の予防の考え方を日本に持ち込み、広めていこうとしたのがNSCAジャパンの活動の始まりです。怪我の予防に加え、競技力向上や一般の方々の健康増進もミッションとして掲げています。
──アメリカも日本も、始まりは「怪我予防」だったんですね。
吉田さん:NSCAの活動の特徴の1つに、研究と現場の密接な連携があります。とくにアメリカには軍隊があるため、効率的に体を鍛える必要性が高く、研究も盛んです。たとえば、筋肉をつけるために最適なトレーニングのセット回数や休息時間の長さなど、細かな部分まで科学的に分析されています。研究成果は、アメリカのNSCA本部に集約され、リサーチ集としてまとめられます。その中でも影響力の高い論文は専門誌に掲載され、全世界に共有されるんです。
現在はスポーツ科学の発展により、サッカー選手やラグビー選手の走行距離や速度などの「スポーツパフォーマンス」も、GPSを使用して記録できるようになってきています。栄養や睡眠などのリカバリー面も注目されており、睡眠時間とパフォーマンスの向上の研究も盛んです。世界中の研究者が、価値のある研究として専門誌に掲載されることを目指しているんですよ。

──科学の進化はすごいですね!スポーツの現場と研究の連携について、さらに詳しく教えていただけますか?
吉田さん:NSCAの理念に「研究と現場をつなぐ」ことがあります。スポーツの現場でわからないことはたくさんあります。研究者が現場で収集したデータを研究し、指導者が研究結果を活かしたトレーニングをする。「研究は研究、現場は現場」ではなく、2つを相互に補完し合い、最適なトレーニングや指導法を構築していくのがNSCAの重要な役割だと考えています。
たとえば、高齢者のトレーニング指導をおこなう際、まず研究者が、「高齢者がどのような運動負荷に耐えられるか」「どのようなトレーニングが有効か」を研究します。そして、実際に現場でその知見をもとにプログラムを試し、指導者が効果をフィードバックします。こうしたプロセスを繰り返すことで、科学的根拠にもとづきながらも個々のニーズに対応した指導が可能になります。
──研究に裏付けられた根拠のあるトレーニングだからこそ、安心・納得してトレーニングができますね。

吉田さん:科学的根拠のあるトレーニングといえど、年齢や性別、体格などの個体差もあります。NSCAの指導者は、科学的な知識を習得したうえで、カウンセリングをもとに一人ひとりに合わせたプログラムをカスタマイズするスキルが求められます。相手に寄り添いながら、科学にもとづいた指導をおこなうことが、トレーニング効果を最大化するために欠かせません。
現在、NSCAジャパン全体の会員数は約1万人で、その中の約8割が資格取得者です。資格はおもに2つあります。1つは「CSCS(Certified Strength and Conditioning Specialist)」で、こちらはアスリート向けの指導を専門とする資格です。もう1つは「NSCA-CPT(Certified Personal Trainer)」という資格で、こちらは子ども、女性、高齢者、妊婦さんなど、幅広い層に対応するパーソナルトレーナー向けの資格です。どちらの資格も、NSCAの会員になってから試験を受けることができ、約700ページにおよぶテキストで勉強しているんですよ。
資格者の活躍の場は多岐にわたり、トップアスリートの現場やパーソナルジムのほか、医療分野でも増えてきています。治療だけでなく、怪我の予防やリハビリをサポートするために、医師や栄養士が資格を取得されるケースもありますよ。
──NSCAの知識が他職種に活用されることで、より質の高いサポートが可能になりそうですね!

吉田さん:そのほか、以前はトップアスリートが中心でしたが、今では中高校生の部活動にもトレーニングコーチが入った科学的なトレーニング指導が取り入れられるようになりました。私自身も中学校の部活動に月一度の指導をおこなっています。マシンこそ使用しませんが、ストレッチや体幹トレーニング、走り方、自重のトレーニングなど、怪我を防ぐための基礎的な動きづくりなどを中心に指導していますよ。
スポーツには、どうしても怪我のリスクがともないます。だからこそ、子どものころから予防のためのトレーニングを始めることが必要であると私たちは考えます。怪我の予防のためのトレーニングは、いつの年代にも重要です。
──小さいころから正しい怪我予防の知識を身につけておくことで、将来的な健康習慣や身体づくりにつながりますもんね。
吉田さん:たとえば、ジャンプ力を高めるトレーニングを正しいフォームでおこなうと、パフォーマンスの向上だけでなく、怪我のリスクも減少します。また、トレーニング効果をモニタリングすると、「3か月でジャンプ力が3センチ伸びた」と子どもたちのモチベーションも上がり、達成感も得られるんですよ。
怪我をして「やりたいのにできない」という状況は、身体だけでなく気持ちの面でも落ち込みやすい時期ですよね。そのために怪我の予防は重要で、正しいストレッチやトレーニングが欠かせません。私たちとしては、ただ単に早く復帰させるだけでなく、以前よりもよい状態で戻れるようなプログラムを提供できることが理想です。怪我をした場合の個別プログラムを作成することも私たちの役目ですね。
しかし、NSCAはトレーナーの世界では広く知られているものの、一般の方々への認知度はまだまだ低いのが現状であり、課題です。私たちのミッションである正しい知識の普及のために、スポーツ選手だけでなく、一般の方にも「正しいストレッチやトレーニング」の重要性を知ってもらい、生活に取り入れてもらいたいと考えています。

──大人も子どもも笑顔で楽しくスポーツを続けるために、ぜひ多くの人に知ってもらい、トレーニングをしてほしいですね!
吉田さん:はい。そのまま習慣になるまで続けていただけると理想です。習慣化してしまえば、毎日の歯磨きと同じ。寝る前に、毎週金曜日に、それぞれに習慣を決めて、自分の身体のコンディショニングを整えていっていただきたいです。
また、私たちの施設では、小学生から学生トレーニングの枠を設けて受け入れています。小学生だと、なかなか公共の施設では受け入れてもらえず、十分なトレーニングができません。そこで、HPCでは中学校で部活動をやりたい、上を目指したいという子どもたちに向け、トレーニングをおこなっています。トレーニングは誰にとっても必要です。そのためにも、なるべく間口を広げ、ストレングス&コンディショニングを感じてもらい、パフォーマンスアップに繋げてもらいたいという想いがあります。
── 目的とやり方が変わるだけで、運動はどの世代にとっても必要ですね。
吉田さん:タイミングによっては、小学生の横でプロアスリート選手がトレーニングしていることもあります。トップアスリートと一般の方や子どもたちが同じ空間でトレーニングをおこなえるのも、この施設の特徴ですね。アスリートから刺激を受け、夢や目標を抱くきっかけになれば嬉しいですね。
施設内はスペースが広く、走る、ジャンプする、などいろいろな動きができる環境を整えています。単なる筋トレだけではなく、全身を使った「動きのトレーニング」に重点を置いていますね。また、フリーウェイトのマシンを中心に揃え、利用者が自分の身体をしっかりコントロールしながらトレーニングできるようにしています。体験していただいたように、マシンに頼るのではなく、自分の重心やバランス感覚を意識して動くことが重要です。
筋機能と体力を高める「ストレングス&コンディショニング」
── NSCAの「ストレングス&コンディショニング」とはどのようなトレーニングですか?
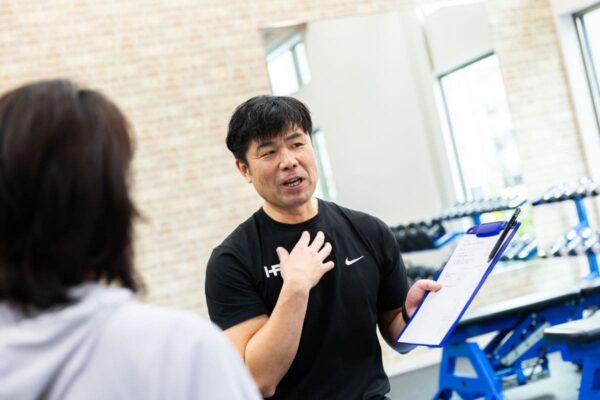
吉田さん:「ストレングス」は、一般的に筋力のイメージが強いと思いますが、NSCAではさらにパワー、筋持久力、スピードなどの筋機能を含めています。思い通りの角度・スピード・力の大きさで身体を動かすための脳と神経と筋肉の連動を、NSCAの「ストレングス」は目指しています。
「コンディショニング」は、柔軟性、バランス、心肺持久力などの体力要素をトレーニングする身体準備です。アスリートなら本番で最大パフォーマンスができるために、一般の人なら腰痛や肩こりなど身体の不調の改善のために、身体を整えることがコンディショニングです。
──あえて「ストレングス&コンディショニング」と分けたのはなぜですか?
吉田さん:コンディショニングの中にも、筋力やパワーなどのストレングスの要素が入っているんですが、それぞれを強調するためにあえて分けて表現しました。筋肉は、動きや代謝などに関わる大きな役割をもっていますが、健康のためには筋トレだけでなく、いろいろな要素が必要です。人間の身体は、加齢とともに変化し、筋肉や関節が硬くなったりと思い通りに動きづらくなります。よい状態を維持するために、筋トレのほかにも、柔軟性や可動域を上げるようなコンディショニングのトレーニングが大切になってきます。
──大人から子どもまで必要であると思いますが、とくにトレーニングをおすすめしたい年代などはありますか?
吉田さん:やはり、動けるうちに動くことが大切です。とくにおすすめしたいのは50代で、仕事や家事が少し落ち着いてきて時間に余裕が生まれやすいタイミングです。50代から少しずつでもトレーニングを始めて運動を習慣化できることが、60代、70代になったときの健康維持に大きく役立ちます。毎日やる必要はなく、週末に軽く身体を動かすだけでも効果はあるので、50代はその習慣を身につける絶好の時期だと思いますね。

──本格的な身体の不調や痛みを感じる前に始めることがポイントですね。また、トレーニングといえば男性のイメージが強かったですが、体験時に女性のほうが筋肉が少ないため肩こりになりやすいと伺い、女性にもどんどん挑戦してほしいと感じました。
吉田さん:そうですね。男性に比べて女性は筋肉量が少なく、とくに上半身の筋肉が弱い傾向があります。肩こりや腰痛を解消するためにも、本日体験していただいたようにぜひトレーニングをしていただきたいです。いきなりダンベルを使ったハードなトレーニングをする必要はなく、ショルダーバッグを使った肩の上げ下げ運動でも効果があります。簡単なエクササイズなど、自宅や身近な環境でできる運動から始めるだけでも違いがでてくるので、少しずつ続けてみてくださいね。
──運動が苦手な人でも、日常生活の中で取り入れられそうですね!
吉田さん:運動が苦手だったり、億劫に感じたりする方は、「日常生活の中でできる運動」を取り入れるのが効果的です。たとえば、エスカレーターの代わりに階段を使ったり、通勤や買い物の際に早歩きしたり。早歩きはとくに大事で、「健康寿命」にも大きく関わると言われています。早歩きは、加齢とともに衰える速筋繊維(早く動く力を司る筋肉)を刺激するため、意識的におこなうと筋力の低下を緩やかにします。「ウォーキング」と構えるよりも、毎日の動作の中での「ながら運動」の感覚を大切にしてください。携帯見ながら、歯磨きしながら、電車に乗りながら…無理せず、ハードルを下げてできるところから始めるのがポイントですね。
ただ、身体が硬くなってしまうのは、ウォーキングや筋トレでは改善できません。姿勢改善や怪我予防の観点からも、ストレッチは意識的に取り入れることをおすすめします。
健康を自分で守るために。子どものころから正しい知識を

──ジュニアスポーツにも力を入れられているとのことですが、 お子さんをもつ親世代へのアドバイスがあれば教えてください。
吉田さん:少年野球・少年サッカーなどスポーツの専門化が進み、練習量も増加していることから、子どもたちの怪我のリスクは増えてきているのが現状です。そして、怪我を防ぐためにはやはりトレーニングが重要。とくに成長期の子どもたちは、身長が急激に伸びる時期に筋肉や関節が硬くなりやすく、そのまま放置すると怪我につながるリスクが高まります。家でもできるストレッチや筋トレなど、「当たり前」と言われる基礎的なトレーニングで十分なので、ぜひ習慣化していただきたいですね。
子どものうちに柔軟性を高めておくと、大人になっても身体が動かしやすくなり、スポーツでのパフォーマンス向上や怪我予防にもつながります。幼少期からストレッチを習慣化し、身体の柔らかさを維持すると、将来的にスポーツの世界を目指したいと考える子どもにとってよい準備になりますよ。
──子どものうちの柔軟性が、大人になったときの柔軟性を決めるんですね!

吉田さん:怪我の中には、完全には治らなかったり、身体のクセになってしまったりするものもあります。そうなると、なによりも大事なのは「怪我をしない・させない」こと。怪我の予防のためのトレーニングとあわせて、やりすぎないことも大切です。
NSCAでは、「Long-Term Athlete Development(LTAD)」、つまり「長期選手育成計画」という考え方を提唱しています。これは、短期的な成果を求めるのではなく、選手としての長いキャリアを見据えた段階的な育成をおこなうものです。小中高と成長の段階に応じたトレーニングプログラムを設計しており、子どものうちは柔軟性とスピードを重要視しています。子どもの身体の成長や発達に合わせてトレーニングを段階的に進めることで、将来にわたって怪我なく高いパフォーマンスを維持できる体作りを目指します。
アメリカでは、筋力トレーニングの授業がある高校もあります。フォームや負荷のかけ方など、正しいトレーニングの方法や知識を学ぶことで、自分の健康を自分で守る力を育むことができます。学生のうちに筋トレや柔軟性を身につけておけば、大人になって必要なときに思い出せますよね。
いろいろな情報が溢れる中で、子どもたちの健康や成長をサポートするためには、正しい知識を選んで、日常に活かすことが大切です。そのためにもNSCAは、正しい知識の普及により励んでいきたいと思います。
──まさに人生に活きる知識になりますね。本日はありがとうございました!
Wellulu編集後記:
エビデンスにもとづいた知識をもつ資格者のインストラクターさんのもと、信頼感と安心感をもって、伸び伸び身体を動かせた体験トレーニング。自分の身体の不調や、一つひとつのトレーニングの動きを理解しながら進めることができました。驚いたのは、行きと帰りで自分の姿勢と歩くスピードが違うこと!意識とトレーニングで身体は変えられる。すべての世代の人々が、今日も明日も楽しくスポーツできる健康な身体でいるために、ストレングス&コンディショニングの考えがさらに普及することを願います。

CSCS, NSCA-CPT, NSCA ジャパンマスターコーチ
元森永製菓(株)ウイダートレーニングラボヘッド S&C コーチとして、育成年代からプロ選 手まであらゆる競技のアスリートを指導したほか、ミス・ユニバース・ジャパン・ボディメ イキングスペシャリストとして、モデルらの身体作りにも従事。その後、ジャパンラグビー トップリーグ Honda HEAT ヘッド S&C コーチとして 5 年間従事し、2017 年 4 月より現職。