インフォーマル・パブリック・ライフ
飯田美樹さんの著書「インフォーマル・パブリック・ライフ」の出版記念パーティに呼んでいただいた。世界の人々を惹きつける街に共通するルールを読み説いた一冊だ。
ウェルビーイングな街づくりは、いろいろなところでスマートシティの文脈から出てくる。特に海外では、いろいろな街が行政を中心につくる街、企業がデータを集めながらつくる街など様々だ。バルセロナやドバイはいつも街のあるべき姿をリードしている。
それが、本当に自分たちが住みたい街なのか?
総勢50人以上の人たちがこの出版パーティに参加していた。ミラツクの西村さんの声掛けにより、Welluluで対談いただいた、たくさんの顔見知りの方たちともお会いできた。帯にコメントを書かれている吉見俊哉(東京大学名誉教授、國學院大学観光まちづくり部教授)さんの本の書評も素晴らしかった。
ニュータウンの孤独からパブリックの再生へ。もうひとりのジェイコブズの誕生。
プライベートとパブリックの重なり合う「あわいところ」から生まれる空間、そして都市のスピードを落とすことで、見えにくいものが見えてくる。生活実感の場から、自分らしい生き方をしている街。
飯田さんのお話も聞かせていただき、人が惹かれる街とはどんなものか、あらためて共感しかなかった。そして、「インフォーマル・パブリック・ライフ」(英治出版)を早速読ませてもらった。

街の発展のために一番大事なポイントはビジネスと同じで、「人を大切な人間として扱うこと」である。そこに来た人を歓迎し、彼らが心地よいと思う場のデザインを提供することである。
「エリアの歩行者空間化」確かに自動車社会において、街のちょっとした風景を見ることもせず、移動を楽しまない。そして、周りを見て歩くだけで新しい発見があるのが分かる。
「座れる場所を豊富に用意する」東京にはちょっとくつろげるベンチが少ない。座る場所があって、はじめて自分の中で心の余白を持つことができるのだろう。少しの間の休憩がスローな生活をつくれるということだ。
コペンハーゲンのヤン・ゲールの「SLOW CITY」という本を昔、読んで面白かった。まさに、歩きたくなる外観があり、座れる場所があるだだけで、心に余裕をもたらすのだろう。本書の中でも紹介されていた。
「ハイライトの周りにアクティビティを凝縮させる」強力な磁場をもつハイライトをもつことで、その街のシンボルになるし、求心力をもって人を惹きつけるのだ。歴史的建造物がまさにそうだろう。あと、この前訪れた直島は、島のいたるところにアートがあり、自然と人工物が共生していた。本書の中では、オープンカフェも磁場をもつものと紹介されていた。
「エッジから人々を眺めていられる場所をつくる」ハイライトのエッジに、人々を眺めていられる場所をつくることである。境界部分に人を滞留させる仕組みがあるのだ。背後には壁などで守られている中で、隅の真ん中の広場でいろいろな人が集まれる場所だ。そこは自然を眺めるのではなく、日常にある人間の普段の生活を眺める。
「歓迎感を感じられるエッジをつくる」そのエッジが統一感と歓迎感が必要とのことだ。エッジに「あたたかさ」が必要とのことだ。確かに、閉じすぎず、シンプルすぎず、何かそこに居心地の良い人間のあたたかさや、自分が受け入れられている感じ(包み込まれいる感じ)が必要なのだろう。
「朝から夜まで多様な用途を混合させる」商店と飲食店、住宅、オフィスのように、用途の異なるものを同じ小さなエリアの中に混ぜることである。そこには多様な人が集まり、その多様が新たな文化を生んでいくのだろう。生物学のことばでエコトーンという言葉を聞いた。山と海の間の移行帯に、多様な生物が共生している場だ。そこから新たなカオスがイノベーションを生んでいくのだろう。変わり続ける街は多様な人がいるのだろう。
「街路に飲食店があること」にぎわいをもたらすためにエッジに設置すべきアクティビティは、老若男女、観光客や外国人などが滞留し、足取りをゆっくりさせることである。立ち止まったり、座ったりできる。横浜中華街や上野アメ横なんかはそんなイメージか?
飯田さんは、オープンカフェをこよなく愛していることが分かった。そして、そういった都市設計がパブリックとインフォーマルの狭間で、新たな生態系が生まれてくるのだろう。
街も生き物である。本書を読んでそう思った。人間と自然が一体となって、そこに行き交う人間が、時間をゆっくりにして、何か新しい刺激に出会う。そんな街がウェルビーイングな街なんだろう。
西村さん、飯田さん、素敵な本をご紹介いただきありがとうございます。僕もスローな時間とスローな街を探索できるようにします。この出版パーティが、まさにインフォーマル・パブリック・ライフを体現するような時間だった。



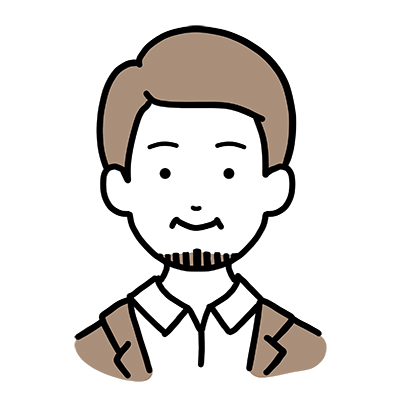
堂上 研 Wellulu 編集部プロデューサー