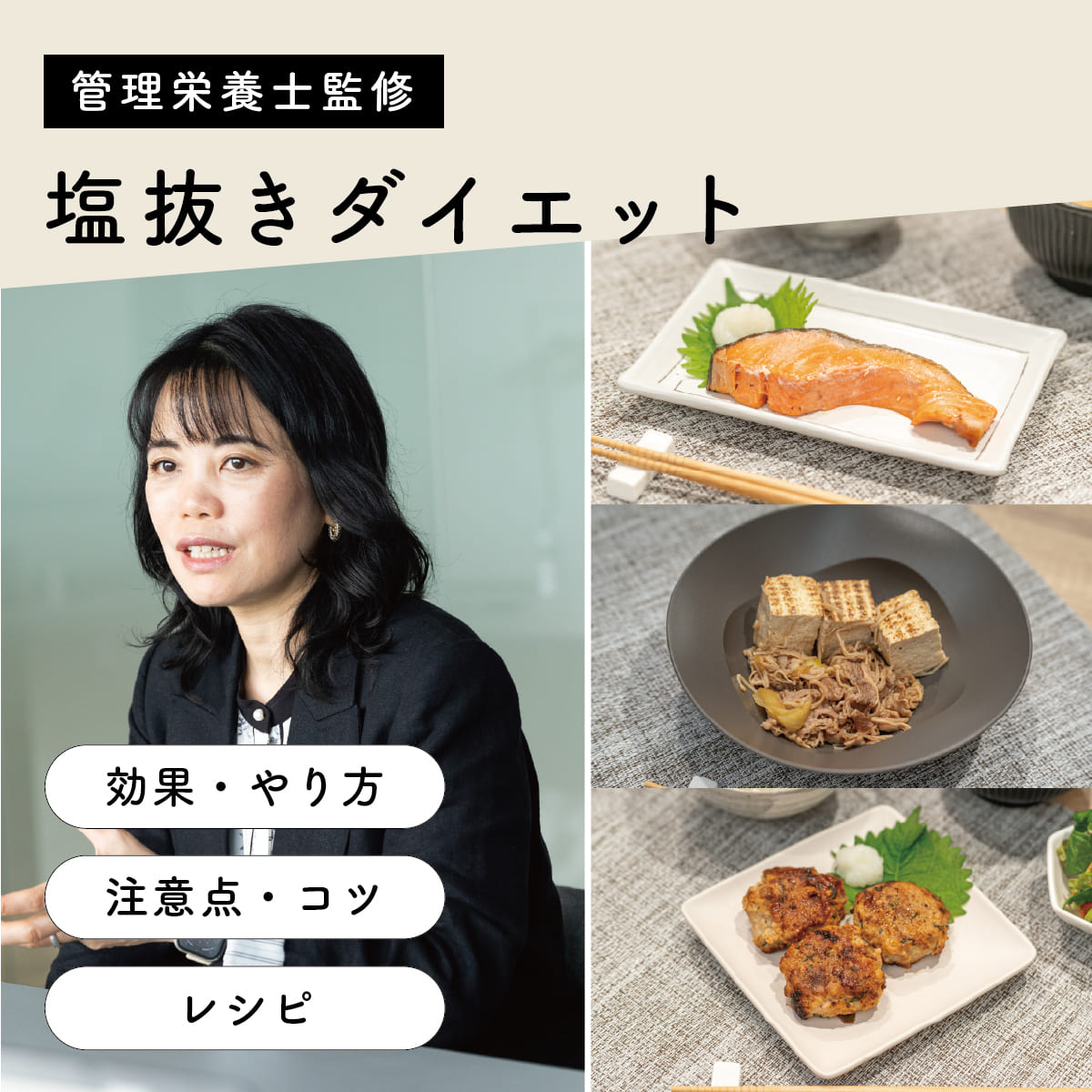
「塩抜きダイエット」は、塩分を控えることでむくみを取りやすくなり、とくに女性の間で人気が高まっている。一方で、正しいやり方や注意点を知らずにおこなうと、健康に悪影響が出ることもある。この記事では、塩抜きダイエットの効果や正しいやり方、注意点などを紹介。
この記事の監修者

金丸利恵さん
おうちごはん研究家 管理栄養士
塩抜きダイエットって?塩分摂取を適量に保つ効果

塩抜きダイエットは塩分を控えることで身体の余分な水分を取り除き、一時的に体重を減らすことを目指す減量法。適度に塩分を控えるとむくみがとれて見た目がすっきりしたり、体重が減ったりなどの変化が起きやすくなる。
- むくみが解消して身体がすっきりする
- 味覚が敏感になり食欲がコントロールしやすくなる
- 血圧が安定して健康的な状態を保ちやすくなる
- 代謝が上がって体重が落ちやすい体質になる
むくみが解消して身体がすっきりする

塩分が多い食事をとると、身体に余分な水分が溜まってむくみやすくなる。
反対に、塩分の摂取を適度に抑えると体内の水分バランスが整い、むくみの解消につながる。その結果、顔や身体がすっきりして見え、身体が軽く感じられやすくなる。とくに、むくみによる顔や足の不快感や違和感がある人は、日々の塩分摂取量を見直してみよう。
味覚が敏感になり食欲がコントロールしやすくなる

塩分が多い食べ物は味が濃く、食欲を増進させるといわれている。そのため、普段から塩分の多い食事をしていると、必要以上に食べすぎてしまう可能性が高まる。
日ごろから塩分控えめの食事を続けていると味覚がリセットされ、食材本来の味や香りを感じやすくなる。薄味でも満足できるようになると過度な味つけをしなくても食事を楽しむことができ、自然と食欲もコントロールしやすくなるため、食べすぎ防止にもつながる。

塩分を制限してから1週間ほど経つと、これまでの食事が塩辛く感じられるようになります。まずは、汁物や麺類、漬物、佃煮、スナック菓子など、塩分の多い食品を控えることから始めましょう。
なお、和食は健康的なイメージがありますが、味噌や醤油などの塩分が多い調味料が使用されており、実際には塩分が多い場合も少なくありません。反対に、クリーム系やオリーブオイルなどで調理した洋食は塩分が少なく、自然な味覚に慣れたいときにおすすめです。
血圧が安定して健康的な状態を保ちやすくなる

塩分の摂取量が多いと高血圧になりやすく、脳や心臓、腎臓などさまざまな臓器に負担がかかる。一方、塩抜きダイエットをおこなうと血圧が安定しやすくなり、心血管系の健康につながる。
とくに、高血圧の人や生活習慣病予備軍の人は、普段の塩分摂取量を見直すことで健康管理もしやすくなる。最近は若い人の高血圧も増えているため、塩分のとり方には早いうちから気を配ることが大切。
代謝が上がって体重が落ちやすい体質になる

身体の水分がうまく循環すると、血液の流れがよくなって栄養素や酸素が効率的に全身に運ばれる。
また、老廃物の排出がスムーズになることで、基礎代謝も正常化してより効率的にエネルギーが利用されやすくなる。理想の身体を無理なく維持できるよう、痩せやすく太りにくい体質を目指そう。
塩抜きダイエットの正しいやり方

- 1日の塩分摂取量は適正範囲までセーブする
- カリウム豊富な野菜や果物を意識して食べる
- 塩分の多い加工品・お菓子は避ける
- 調味料に含まれる塩分量にも注意する
1日の塩分摂取量は適正範囲までセーブする

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」によると、男性は1日に7.5g未満、女性は6.5g未満の塩分をとるのが理想的。
これを超えるとむくみやすくなったり、将来的な健康リスクが高まる可能性があるため、とりすぎには十分注意したい。ダイエットはもちろん健康のためにも、塩分は毎日適量範囲内で摂取しよう。
なお、塩抜きダイエットといっても完全に塩を排除するのは避けるべき。塩分は身体に必要不可欠なもので、不足すると体調不良など健康に悪影響が出てしまう。塩抜きダイエットをおこなうときは身体への負担も考慮しつつ、適度に制限するのが大切。

レトルトカレーや炒め物などの既製品や総菜には、加熱した野菜を混ぜると全体の量が増え、かさが増えた分を少し減らして食べると塩分濃度を無理なく下げられます。味噌汁などの汁物も同様に水やお湯で薄める場合もありますが、薄めた味噌汁をすべて飲んでしまうと塩分摂取量を減らすことはできません。
かさましして薄味にする場合は摂取量も減らすことを意識しましょう。また、サラダのドレッシングはなるべく控えめにするか、味つけされていない野菜も一緒に食べるようにしましょう。
カリウム豊富な野菜や果物を意識して食べる

カリウムは塩分であるナトリウムと同時に働き、身体の塩分バランスを整える役割がある。カリウム豊富な野菜や果物を意識して食べると、塩分をとりすぎた際のむくみの軽減などが期待できる。
カリウムが豊富な食材には、ほうれん草やバナナ、アボカド、スイカ、キウイなどがある。塩分をスムーズに排出するためにも、これらの食材を積極的に取り入れよう。

カリウムは水に溶けやすいため、しっかりとりたいときは調理法を工夫する必要があります。たとえば、食材は洗ってから切る、茹でずに蒸す、電子レンジで加熱する、スープは汁ごと食べるなどすると、カリウムを効果的に摂取しやすくなるでしょう。
塩分の多い加工品・お菓子は避ける

インスタント食品や市販のお菓子、菓子パンなどの食品には想像以上に多くの塩分が含まれているため、ダイエット中はなるべく避けたいもの。一見、薄味に思える練り物やソーセージのような加工品も、実際はかなりの塩分を含んでいる。
塩抜きダイエットをするなら、基本は自炊メインの食事をするのがおすすめ。自炊の場合、塩分の摂取量を自分自身でコントロールできるため、思わぬ塩分過多を防ぎやすい。また、コンビニやスーパーで買い物する際はパッケージをしっかりチェックし、塩分が多いものは避けるよう心がけよう。

加工肉や佃煮、チーズをはじめ、健康的なイメージのある酢飯や味ご飯、漬物も意外と塩分が多いです。漬物の中でも古漬けや梅干しはとくに塩分が高いため、塩抜きダイエット中は食べすぎに注意しましょう。
調味料に含まれる塩分量にも注意する

意外と見落としがちなのが、調味料の塩分。市販の調味料には塩分が多く含まれているものが多く、使い過ぎると塩分の摂りすぎにつながる。
一般家庭で使用する機会が多く、塩分量が多い調味料は以下のとおり。
- 中濃ソース:15g(約大さじ1杯)につき塩分量1.0g
- ケチャップ:15g(約大さじ1杯)につき塩分量0.6g
- 濃口醤油:15g(約大さじ1杯)につき塩分量2.9g
- 赤色辛口味噌:15g(約大さじ1杯)につき塩分量2.3g
- ドレッシング(胡麻ドレッシング):15g(約大さじ1杯)につき塩分量0.5g

ポン酢は酢の割合が多いため、塩分量は比較的少なめです。逆に、塩こうじやナンプラー、コンソメ顆粒、鶏がらスープの素は意外と塩分量が多く、使い勝手のよい調味料ではありますが使用量には十分注意しましょう。
塩抜きダイエットをする際の注意点
- 水はこまめに飲む
- 体調の変化には常に気を配る
- 薄味の食習慣を身につける
水はこまめに飲む

塩分を控えるとのどが渇きにくくなることがあるため、脱水のリスクが高まる。そのため、塩抜きダイエット中は、いつも以上に水分を意識してとることが大切。とくに運動した後やお風呂上がりは汗をかくため、普段より多めに水分を摂取したい。
気温や運動量にもよるが、1日に必要な水分は約1.5~2L。常に適切な量の水分が体内に保たれるよう、喉が渇く前にこまめに飲むことを心がけて。
なお、1時間以上運動する場合は、水分だけでなく塩分も補給すべき。水分に対して0.1~0.2%の塩分を目安に調整するか、スポーツドリンクを活用しよう。

塩分を極端に減らすと体内のミネラルバランスが崩れ、低ナトリウム血症を引き起こす可能性があります。身体に影響が出過ぎない範囲での塩分制限を心がけましょう。
体調の変化には常に気を配る

塩抜きダイエットをしている間は、日々体重や体調を確認すること。定期的に体重を計る習慣をつけると、身体の状態や変化を把握しやすくなる。
もしめまいや疲れなど普段と違う体調の変化があった場合は、無理をせずにダイエットを中止しよう。自分の体調を最優先に考え、必要であれば専門家への相談も検討しよう。
薄味の食習慣を身につける

健康な身体を維持する秘訣は、普段から薄味の食事を心がけること。減量できたからと濃い味つけに戻すと、せっかくリセットされた味覚がもとに戻ってしまったり、むくみがひどくなって体重が増えたりする可能性があるため、注意が必要。
必要以上の塩分摂取を控えるためにも、食材本来の味を楽しむ食習慣は続けたいもの。薄味でもおいしいと感じられる工夫を取り入れながら、毎日の食事を楽しもう。
塩抜きダイエットの強い味方!薄味でもおいしくするコツ

- 下ごしらえ・調理方法を工夫する
- 天然だしの旨みを活用する
- コクが強い食べ物で風味を変える
- 酸味や辛みがある食べ物・調味料を使う

減塩調味料は通常と異なる製法で作られているため、人によっては味に違和感があったり、満足しづらいと感じたりする場合もあります。また、減塩だからとたくさん使ってしまう傾向もあり、通常の調味料を少量使った方がよい場合もあるでしょう。基本的には食材本来の味を活かした調理を意識して、減塩調味料に頼りすぎないことが大切です。
下ごしらえ・調理方法を工夫する

食材の下ごしらえを丁寧におこなえば、調味料に頼らなくてもおいしい料理に仕上がる。たとえば魚は昆布で締めたり、肉は叩いて柔らかくしたり、野菜は細かく切れ込みを入れるなど、旨みをアップさせる方法はたくさんある。
とくに、蒸し料理やグリル料理は素材の甘さや旨みが引き立つため、塩抜きダイエット中の献立にぴったり。カロリーオーバーにもつながりにくく、より高い減量効果が期待できる。
天然だしの旨みを活用する

かつおや昆布、いりこ、しいたけなどの天然だしを使うのも1つの手。だしは料理に深みを与え、香りや味わいを豊かにしてくれるほか、各食材の風味も引き立ててくれる。あっさりした味つけでも自然な深みを出せるため、ぜひ積極的に活用しよう。
ただし、顆粒だしは塩分が多いため、塩抜きダイエット中は避けた方が安心。あくまで天然の食材を利用して、自然な旨みや風味をプラスしよう。
コクが強い食べ物で風味を変える

無塩バターやチーズ、オリーブオイルなどコクがある食材は、料理の味わいを一層引き立てたり、風味を変えたりするのに役立つ。たとえば酸味と甘みのバランスがよいトマトは、フレッシュさを出したいときに最適。
また、無塩バターはほかの食材にはないクリーミーさとリッチな風味で、料理の深みを格段に高めてくれる。食材によって合う料理はそれぞれなので、好みや気分に合わせて複数の食べ物を取り入れてみよう。
酸味や辛みがある食べ物・調味料を使う

酢やレモン汁、わさび、一味唐辛子、山椒など、酸味や辛味が強い食べ物は薄味でも満足感を得られやすい。
たとえば、酢やレモン汁は料理に爽やかな酸味を加え、食欲をそそる効果が期待できる。また、わさびや一味唐辛子、山椒などの辛味をプラスすると、あっさりした味付けの中にも深みや刺激を感じられ、食事がより楽しくなる。
さらに、ハーブやスパイスを使えば、エスニックな味つけを楽しむことも可能。バジルやコリアンダー、クミン、ターメリックなどは料理に独特の風味を与え、異国情緒あふれる味わいを演出してくれる。さまざまな酸味や辛味を活用し、普段の食事にアクセントを加えてみよう。

薄味の料理をおいしく食べるには、ブラックペッパーやカレー粉などもおすすめです。ブラックペッパーは料理に軽く風味を加えたいときに、カレー粉は料理にパンチを与えたいときに活躍します。カレーを作るときはカレールーの分量を減らしカレー粉で補うと、塩分控えめでスパイシーに美味しく仕上がりますよ。
【編集部おすすめ】塩抜きダイエットにおすすめのおかずレシピ

- 鮭の塩焼き
- 肉豆腐
- れんこんと大葉のつくね
鮭の塩焼き

【材料(2人前)】
- 2人分
- 鮭:2切れ
- 塩:小さじ1/2
- 酒:大さじ1
- 米油:適量
【レシピ】
- 鮭は両面に塩を振って5分ほどおく。
- フライパンに米油をひき、中火で1を両面焼く。
- 酒を入れ、蓋をして1~2分蒸し焼きにする。

塩を控えめにして素材の旨味を活かし、従来の塩焼きよりも塩分を抑えた一品です。酒を入れて蒸し焼きにすることでふっくらとした仕上がりになります。
肉豆腐

【材料(2人前)】
- 牛こま切れ肉:150g
- えのき茸:100g
- 焼き豆腐:150g
- 調味料
- 水:100ml
- 顆粒和風だし:小さじ1
- しょうゆ:大さじ1
- みりん:大さじ1
- 酒:大さじ1
- 砂糖:大さじ1
- 米油:小さじ1
【レシピ】
- えのき茸はさいて食べやすい長さに、焼き豆腐は4等分に切る。
- フライパンに米油をひいて中火で熱し、牛こま切れ肉とえのき茸を入れて炒める。
- 牛こま切れ肉に火が通ったら、調味料と焼き豆腐を入れて中火で煮立たせる。
- 10分ほど煮込み、味がなじんだら完成。

肉豆腐は、低カロリーで高タンパクな焼き豆腐を主役にした、ダイエット中にもおすすめのメニューです。牛こま切れ肉で旨味を加え、えのき茸をプラスすることで食物繊維が豊富になり、満足感がアップ。調味料は控えめにしながらも、だしの風味で塩分を抑えた味わいに仕上げています。
れんこんと大葉のつくね

【材料(2人前)】
- 鶏ももひき肉:300g
- れんこん:50g
- 長ねぎ:10cm
- 大葉:5枚
- (A)味噌:小さじ2
- (A)黒こしょう:少々
- 米油:小さじ2
- 酒:大さじ1
【レシピ】
- れんこんは厚さ2mmのいちょう切り(水煮の場合は大きめのサイコロ状にカットでもOK)、長ねぎと大葉はみじん切りにする。
- 鶏ももひき肉、長ねぎ、大葉、(A)を入れて練り混ぜる。粘りが出てきたら1のれんこんを入れて混ぜる。
- 2を8等分にして丸く成形する。
- フライパンに米油をひいて中火で加熱する。3を入れて片面2分ずつ焼き、焼き色がついたら酒を入れて弱火にする。蓋をして2~3分蒸し焼きにする。

鶏ももひき肉を使い、脂質を抑えつつ高タンパクなヘルシーメニューです。シャキシャキとしたれんこんの食感が楽しめ、食物繊維が豊富で満腹感も得られます。長ねぎと大葉で香りと風味を引き立て、塩分控えめでも満足できる味付けに仕上げました。従来の照り焼きタレを使ったつくねに比べて塩分を抑えつつも、食べ応えのある一品です。
塩抜きダイエットに関するQ&A

塩抜きダイエット中の外食は控えるべき?
A:完全に控える必要はないが、適切なメニュー選びがポイント。

外食を完全に避ける必要はありませんが、メニューを選ぶときはナトリウムとカリウムのバランスに注目しましょう。カリウムはナトリウムの効果的な排出に必要な栄養素で、果物や野菜、海藻類に豊富に含まれています。
外食時には、スープを控えめにし、サラダを味付けなしで食べたり、バナナやリンゴなどの果物をプラスしたりすると、過度な塩分の蓄積を防ぎやすくなります。また、あっさりした味付けの料理やソテーなど、調理法がシンプルなものを選ぶことも大切ですよ。
塩抜きダイエットはコンビニ食でもできる?
A:可能。塩分表記を確認して選んだり、野菜や果物と組み合わせたりするのがおすすめ。

コンビニで売られている食品は、パッケージに含有塩分が記載されています。塩抜きダイエット中は、1日の目安である6gを基準に、朝食1.5g、昼夜各2.5g程度の塩分摂取を目指しましょう。炒め物やピラフなどにはカット野菜を追加すると、塩分を抑えつつボリュームを増やせます。
ただし、塩分を気にしすぎて食事量を極端に減らすのはおすすめできません。過度な制限は代謝低下を招く恐れがあり、かえって太りやすい体質になってしまう可能性があります。ご飯など塩分を含まない食材を中心に、必要な栄養素はしっかり確保することを心がけましょう。
塩抜きダイエットで食べてもいいものは?
A:白米や穀類、野菜など、塩分を含まない食べ物全般。

白米や穀類は塩分を含まないため、塩抜きダイエット中の主食に適しています。カロリーオーバーには注意しつつ、適度に取り入れましょう。しかし、同じ主食でもラーメンやうどんなどの麺類は塩分が強いので注意が必要です。
なお、野菜はなるべく生や蒸した状態でとり、味付けは控えめにしてください。味噌汁など塩分が多くなりやすい料理は、作る際に具材を多めにすると少ない味噌でも旨みを感じやすくなります。
塩抜きダイエットの効果はいつから実感できる?
A:個人差があるため、3週間程度様子を見ながら続けるのがおすすめ。

塩抜きダイエットの効果を実感する時期には個人差があるため、まずは薄味に慣れることが重要です。最初の1週間は薄味の食事に慣れる期間とし、その後2週間ほど様子を見ながら続けましょう。時間をかけて薄味に慣れていくと、塩分が控えめの食生活が身につきやすくなります。健康的な減量のためにも、即効性を求めるのは避けてくださいね。
塩分をとりすぎたときはどうすればいい?
A:過度な心配は不要だが、水分をしっかり取り、翌日からは塩分控えめの食事を意識したい。

私たちの身体には、血液中の塩分濃度を一定に保つ「恒常性」という機能があります。そのため、一時的に塩分を多くとってしまっても、あまり心配する必要はありません。
ただし、塩分を取りすぎた後はしっかり水分をとり、翌日からはまた塩分を控えること。野菜や果物も多く取り入れて、栄養バランスの整った食事を心がけましょう。とくに忘年会シーズンなど、外食が増える時期は塩分過多になりがちなので、翌日からの調整を意識するのが大切ですよ。

1995年給食会社に入社し、給食管理、レシピ開発などの業務に携わる。出産を機に退職し、育児中は特定保健指導員として生活習慣改善の支援をしながら、料理教室を主宰し、地域で食育活動を広げる。2020年に分子栄養学認定カウンセラー取得。オーソモレキュラーの特徴である個体差を重視した栄養指導でダイエット、体調不良改善のカウンセリングを行う。コロナ禍を機にオンラインにて、料理教室、栄養講座、社内研修などに関わる。オンライン料理教室「4品×4人分作れる!管理栄養士のカラダが喜ぶ絶品おうちごはん」は、3年間で受講者1900人を超える。執筆活動は、WEB媒体にレシピ・コラムの掲載、会員誌、ムック本など。料理のプロが教えるサイトE・レシピに料理家登録して866人のファンを集める。野菜とスパイスを活用したレシピに定評がある。
【資格】
・管理栄養士
・分子栄養医学研究会 認定指導カウンセラー
・臨床分子栄養医学研究会 PNTトレーナー
・ナチュラル&ミネラル食品アドバイザー
・食生活アドバイザー2級(FLAネットワーク協会認定)
・国際薬膳食育師3級(国際薬膳食育学会認定)
・スパイスコーディネーターマスター(SCA認定)