
「すべての人が一度きりの人生を楽しみ抜く世界を目指す」。
そんな志を持って、スポーツカルチャーブランド“GRIT NATION”を立ち上げた林 周一郎さん。本質的な運動理論と 運動を楽しむコミュニティをかけ合わせ、「GRIT=やり抜く力」を相互に高めあえる世界の構築のため日々奮励している。
今回は、林さんが運営する“動作を鍛える”パフォーマンススタジオ「GRIT NATION Shibuya」にお伺いし、Wellulu編集長の堂上研が話を聞いた。人生を変えたというラグビーとの出会い、日本におけるフィットネス文化の課題、そして、林さんの目指すウェルビーイングな社会とは一体。

林 周一郎さん
株式会社GRIT NATION Founder/CEO

堂上 研
株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長
1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。
脚は速いのに運動神経が悪い……ガリ勉小学生時代

堂上:本日はよろしくお願いいたします。開放的ですごく素敵なジムスタジオですね!
林:「GRIT NATION Shibuya」までお越しくださり、ありがとうございます! よろしくお願いします。
堂上:「GRIT NATION」はずっと気になっていたので嬉しいです。本日は事業の話はもちろん、林さん自身の人生についてもお聞きしていきたいと思います。早速、生い立ちからお伺いできればと思うのですが、林さんはどんな幼少期をお過ごしでしたか?
林:なんだか早熟で生意気な子どもでした。幼稚園のお絵かきが文部大臣賞を受賞して調子に乗り、トランポリンの大会で優勝してまた調子に乗って。かけっこも得意で、口が達者でした。
堂上:すごいなぁ。器用な子どもだったんですね。
林:それが残念なことに、運動神経が悪いことに徐々に気づいていくんですよ。身体能力は高くても、今でもボールはうまく投げられないし、道具を使うスポーツ全般でセンスがないんです。剣道、野球、テニス、バスケなど、たくさん習い事をさせてもらいましたが、どれも人並み以下でした。
堂上:それは苦しかったですね。習い事はいつまで続けられたんですか?
林:小学5年生になる頃には習い事は一切やめて、中学受験に向けて勉強に集中しました。
堂上:そういえば、林さんは慶應義塾中等部のご出身でしたね。今でこそ中学受験をする子どもは増えましたが、当時はまだ珍しかったのではないですか?
林:今は受験が当たり前ですもんね。あの頃は毎日楽しそうに遊ぶ友人がうらやましかったです。私が友人と遊んでいい日は、週に1回だけ。本当に勉強漬けの毎日でした。

堂上:受験といえば、息子が勉強に行き詰まったときに、「試験のために必死に暗記をする理由が分からない。AIがある時代なのにどうして必要なの?」と聞いてきたことがありました。一理あるなと思い、AIに尋ねてみたんです。そしたら“忍耐力を高めるため”という回答が出てきて、「なるほどな〜」と妙に納得したことがあります。
林:忍耐力か…。それは確かに受験で身についた気がします。
堂上:Welluluの対談でも、時々受験の話題があがるのですが、親と子どもの両方が悩んでいる印象があります。もしかしたら、受験の仕組み自体がウェルビーイングじゃないのかもしれないですね。
林:特に日本は、やりたいことができる学校に行くためではなく、偏差値を上げることでより選択肢を増やすための受験という感覚が強いように思います。自分が親になった今、子どもの選択肢を増やしてあげたい気持ちはすごく分かりますが、結局子ども本人に意思のない“よかれと思って”のお膳立ては、子どもと自分を苦しめてしまいます。
堂上:今の話を聞いて、上皇后美智子様の「『幸せな子』を育てるのではなく、どんな境遇に置かれても『幸せになれる子』を育てたい(※)」というお言葉を思い出しました。
※出典:「歩み 皇后陛下お言葉集」(海竜社)
林さんのおっしゃる“よかれと思って”は、子どもが転ばないように、目の前の小石を勝手にどけている行為に近いかもしれません。親が、子どもの幸せになれる道を整備してあげているようにも見えますが、一方で、子どもが自分の力で立ち上がる経験を奪っているとも言えます。もしも、子どもが自分の意思で進んだ道ならば、状況に応じて自分で考えて動くようになりますよね。それって、子どもの成長にとても必要なことかもしれません。
林:おっしゃるとおりですね。誰かに与えられた道なのか、自分で選んだ道なのかでは、同じ道のように見えても意味合いが大きく違いますからね。
やっと見つけた自分の居場所、個性を認めるラグビーが人生を変えた

堂上:受験以降の学生生活で印象に残っているエピソードはありますか?
林:当時は、漫画『SLAM DUNK(スラムダンク)』とマイケル・ジョーダンの影響で、体育館に人が入りきらないほどバスケットボールが人気でした。もちろん、僕もやりたかったんです。でも、1年生はボールに触らせてもらえずに外周を走ってばかりだったので、友人とラグビー部に体験入部したら、人生が変わるほどハマりました。
堂上:へえ! チームプレイや道具が必要なスポーツは苦手だとおっしゃっていたので、意外です。
林:今でも苦手ですが、ラグビーには苦手なりに生きる道があるんですよね。それまでスポーツで報われないことが多かったのですが、休み時間にも校舎の隙間で練習するほどハマりました。
堂上:おお! たとえば、ラグビーのどんなところが魅力的でしたか?
林:私は脚が速いけれど不器用なわけです。サッカーや野球のように全ての技術が一定以上必要な競技だと、どうしても一流になれない。しかし、ラグビーはひとつでも秀でた個性があれば、チームの役に立てるスポーツなんです。
堂上:確かにラグビーは、多様な人たちがプレーしているスポーツですね。足が遅くても、ガタイが良ければフォワードとして活躍できますしね。
林:そうなんです! 他のスポーツでは活躍できなかった人でもチャレンジしやすいことが魅力のひとつですね。高校や大学から始めて日本代表になれるスポーツは稀ですから。
堂上:なるほど! しかも、ラグビー部の人たちは、ラグビー愛で溢れている印象があります。
林:私の場合、これまでチームスポーツで力を発揮できない苦しさから救ってくれたのがラグビーでした。初めてチームスポーツで役に立てて、「居場所ができた!」と感じました。競技の勝ち負けは別として、様々な個性が受け入れられるその文化に感謝しているから、ラグビーを愛している人が多いのかもしれませんね。

堂上:本当に素敵なスポーツですね。
林:最初の仕事を選ぶ上でもラグビーの影響が大きかったんです。ラグビーに没頭した12年間に、ラグビージャージが大きく変わりました。デザインや素材の変化を目の当たりにする中で、スポーツアパレルに関わってみたいと強く感じるようになり、ご縁をいただいた三菱商事の繊維本部の扉を叩くことにしたんです。
堂上:なるほど。そこでもラグビーと繋がってくるんですね! そこから一転、起業に踏み切った背景にはどんなことがあったのでしょうか?
林:じつは中学生の頃から自分でビジネスをしたいという思いがあったんです。
堂上:え、中学生の頃からですか!
林:ヨーロッパのバカンス文化に憧れて、一所懸命働いたら、毎年1カ月まとめて休みをとって、行ったことのない場所や、やったことがないことをやりたいと思っていました。父親から日本のサラリーマンはそんなに休めないと言われ、サラリーマンになりたくなかったんですが、学生時代はラグビーしかしてこなかったので、就職してビジネスを学ばせてもらいました。
堂上:日本はまだ長期休暇は取りづらい環境ですからね。しかし、どうしてフィットネス業界で起業をしたのですか?
林:自分軸では、心から良いと思えることを生業にしたかったからです。私が心の底から信じられるもの、すなわち自分を救ってくれたスポーツの力で、人々の生活をもっと鮮やかにできるんじゃないかと。この分野なら人生をかける価値があると思ったんです。
また、スポーツが生涯を通じて人生を豊かにすると信じていますが、日本は諸外国と比べてもあまりにも運動文化が根付いていません。この状況をなんとかしてから、次世代に繋ぎたいという思いもあります。
都会っ子の野生化計画! 子どもの常識が変われば未来が変わる

堂上:「GRIT NATION」についても、詳しく教えてください。
林:「GRIT NATION」は、アスリート界でしか知られていない本質的な身体理論を、世界に還元するハブになりたいと思っています。ダイエットやボディメイクとは異なるパフォーマンスを高めるメソッドを、体験・体感する場所として渋谷にスタジオを作りました。“動作を鍛える”をコンセプトとしたセミパーソナルトレーニングを、子どもから大人まで楽しんでもらっています。
堂上:セミパーソナルトレーニングとは?
林:8名までの少人数クラスのことです。パーソナルトレーニングよりもリーズナブルに受けられて、かつ、一緒に頑張る仲間の存在がモチベーションになります。
堂上:一緒に頑張れる仲間ができると、楽しく続けられそうですね! ウェルビーイングな状態を維持するためには適度な運動も大切です。習慣化していくためには、どんなことが必要だと考えますか?
林:何よりも楽しさが先に来ることですね。欧米ではあくまでスポーツは遊びの一種で、子どもにはいきなり競わせずに、段階的に競技性を高めていきます。一方で日本の体育教育や部活の文化は、最初から競争が前面に出ていて、誰しもが楽しむということが難しい。ナイキは日本に運動文化が根づかない理由を「部活のトラウマ」と呼ぶほど、18歳でスポーツをやめてしまう子がとても多いんです。
堂上:なるほど! その点、日本の教育は段階的とは言えないかもしれませんね。体育の授業でも運動が苦手になる子がいましたし、学生時代の部活を振り返ってみても、できなかったことの罰としてウサギ飛びをさせられたことがあり、辛い記憶しか思い出せません(笑)。
林:特に私たちの世代は厳しかったですよね。現在とは異なり、科学的にパフォーマンスを高めるより、精神修行的な練習が多かったです。
堂上:当時は、先生やコーチが圧倒的な地位を確立していたので、「スポーツ=厳しいもの」という印象が刷り込まれているように思います。それではなかなかフィットネスに投資しようと思えないのも、納得の結果かもしれませんね。

林:大人にとって運動は努力してやるもの。そのイメージを変えようと頑張っていますが、次世代を担う今の子どもたちの教育にも力を入れていきたいです。もし子どもたちの運動に対する常識が変われば、彼らが大人になったときには運動は努力ではなく当たり前の楽しみになっているはずですから。
堂上:先ほど、キッズ向けトレーニングもあるとおっしゃっていましたよね。僕も3人の子どもを持つ親なので、気になっていました!
林:ありがとうございます。「GRIT NATION Zero」では、「都会っ子の野生化」をコンセプトに、今後の発達の土台となる運動プログラムを提供しています。
堂上:都会っ子の野生化……?
林:山など自然の中は地面が凸凹しているので、そこで過ごせば体の順応力が高まります。しかし、都会での生活は地面があまりにも平らなので、人間本来の身体機能が失われてしまう。
そこで「GRIT NATION Zero」では、スタジオの中に障害物を配置して、バランス・スピード・コントロールの3つを遊びの中で高めていくことと、月に1回以上は登山など自然に触れる機会を提供することで、野生の感覚を取り戻す設計となっています。子どもの可能性を広げるための、競技に入る前のみんなに必要な土台を鍛えるイメージです。
堂上:とても魅力的です! 対象年齢は?
林:4歳から10歳までです。年齢に応じた2グループのクラスを用意しています。
堂上:ええっ。僕の一番下の子どもは11歳になるので、もう参加できない……! もっと早く教えてほしかったです(笑)。
自分の価値観に正直に、やり抜く人が溢れる社会をめざして
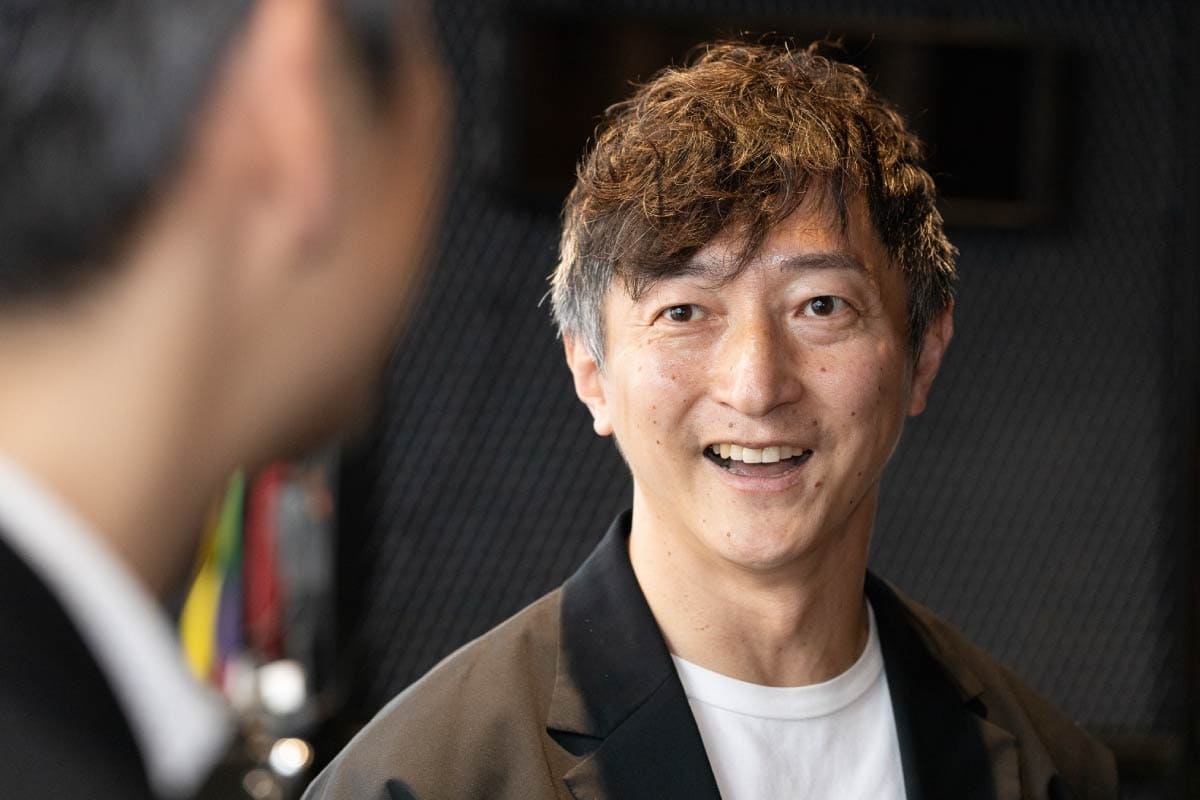
堂上:林さんは何している時が一番楽しいと感じますか?
林:そうだなぁ……。ラーメン店でラーメンを作っているところを見るのが好きだったりします。
堂上:意外な視点ですね! 面白いので、ぜひ詳しく教えてください。
林:店主が湯切りしている姿を見ながら、「なぜ、この人はラーメン店を開くことに決めたのだろう」「エリアの決め手は何だったのか」など、思考を広げることが楽しいんですよね。私は、ゴールよりも、今に至るまでのプロセスに興味があるんです。誰しもにドラマがありますから。
堂上:なるほど。僕も妄想族なので気持ちが分かります(笑)。しかし、なぜラーメンなんですか? 好きだからですか?
林:振り返ると、受験勉強に行き着くのですが。ラーメンは100点を取ったときにだけ食べられる、ご褒美メニューだったんですよ。トラウマかな……? 今でもラーメンには特別な想いがあるんですよね。
堂上:イノベーションを起こすためには、「禁止を禁止すること」が可能性を広げると考えていましたが、以前、Welluluの対談で「ある程度の『制約』も必要ではないか」という話が出ました。制約の中をかいくぐろうとすることからこそ、創造性や原動力が生まれることもあるのだと。その観点では、林さんが禁止が多いご家庭で育ったことで、打破しようとするチャンスが多い環境だったとも言えるかもしれませんね。
林:確かに! ダメと言われるからやりたくなる。壁がなければ越えたいという欲求は生まれないですもんね。面白いなぁ。
堂上:では、最後に未来についても教えてください。今後、林さんがチャレンジしてみたいことは何でしょうか?
林:私の夢は、まさにブランド名である『GRIT NATION』な世界の実現ですね。
アメリカの心理学者の研究によると、成功する人の共通点は「GRIT(やり抜く力)」とされていますが、この力が多くの人に宿っている社会の状態を「GRIT NATION」と呼んでいます。自分の価値観に正直に、そこに対してやり抜くことができる人がたくさんいる世の中のほうがいいじゃないですか。生きている間に実現する気はしないのですが(笑)、少しでも山を登って次世代にバトンを渡したいですね。
堂上:素晴らしいですね。「GRIT(やり抜く力)」を育むためにはどうしたらいいのでしょう?
林:それこそウェルビーイングということに繋がるのではないでしょうか。心身の健康はもちろんのこと、良い仲間や適切なプレッシャーがあればこそ頑張ることができる。みんながGRIT(やり抜く力)を育む社会の実現は、ウェルビーイングな社会の実現と同じことなのかもしれません。
堂上:自信を持ってやり抜く人たちが増えれば、挑戦の数も増えるでしょうし、失敗に対して寛容な社会になりそうですね。
林:失敗をゆるす文化も日本には足りないと感じます。挑戦と失敗の総量が増えるということは、社会がウェルビーイングに向かっていると言えそうです。
堂上:その良い循環をつくっていきたいですね! 林さんの話は共感することばかりで、僕たちWelluluが目指す世界と近しい想いだと感じました。何か一緒に取り組みができたらいいですね。あっという間に時間が経ってしまいましたが、いかがでしたか?
林:とても楽しい時間でした。堂上さんの質問に答える中で、新しい自分の価値観に出会える瞬間もあって、たくさんの気づきを得られました。
堂上:それは嬉しいです! 多様な人との対話は、改めて自分との対話のきっかけになりますよね。本日は本当にありがとうございました!
林:こちらこそありがとうございました!

撮影場所:GRIT NATION Shibuya

慶應ボーイのラガーマンから、三菱商事の商社マンへ。典型的なエリート街道を歩んできたが、世界のトップアスリートを進化させてきた職人との出会いをきっかけに、2017年「進化を楽しむ」スポーツカルチャーブランド”GRIT NATION”を創業。
https://www.gritnation.jp/