
老若男女問わず気軽に始められ、心身の健康から生活習慣病の予防など幅広い効果が期待できるウォーキング。効果を最大限に引き出すポイントやコツが気になる人も多いはず。この記事ではウォーキングの効果はもちろん、歩く時間帯や所要時間による効果の違い、年齢別のウォーキング量などを紹介。
この記事の監修者

中野ジェームズ修一さん
フィジカルトレーナー
ウォーキングで得られる効果

ウォーキングによって得られる効果は様々。とくに心肺機能の高まりや糖尿病予防など、健康な身体づくりに役立つのは嬉しいポイント。一方で、ダイエットのためにウォーキングを始める人も少なくないが、ウォーキングは運動強度が低く、脂肪燃焼や筋肉量向上の効果は得られにくい。
- 心肺機能が向上し持久力が向上する
- 高血圧や糖尿病の予防と改善に役立つ
- 骨密度が上がりロコモ予防になる
- ストレス解消ができ心の健康につながる
- 脳が活性化して認知機能が向上する
- 筋肉が柔軟になり腰痛改善につながる
心肺機能が向上し持久力が向上する

30分以上のウォーキングを習慣化すると、心臓が血液を全身に効率よく送り出せるようになり、酸素供給能力が向上する。体内への酸素供給量が増えることで、長時間のエネルギー供給が可能となって持久力が上がり、日常生活はもちろん、長時間の運動にも耐えられるように。
ウォーキングだけでダイエットすることは運動強度の観点からも難しく、もう少し強度が高い早歩きやジョギングと交互におこなうなど工夫が必要。ただし、ダイエットに必要な運動をしっかりこなせる体力づくりという観点では取り入れるのも1つの手。
高血圧や糖尿病の予防と改善に役立つ

適度な運動強度のウォーキングは血液循環を促進し、血管の柔軟性が高まることで高血圧の予防と改善に役立つ。また筋肉を動かす時間が増えることで食後に生成される糖を吸収しやすくなる。そのため、食後の血糖値を下げるインスリンの効果が高まり、糖尿病の予防にも。
骨密度が上がりロコモ予防になる
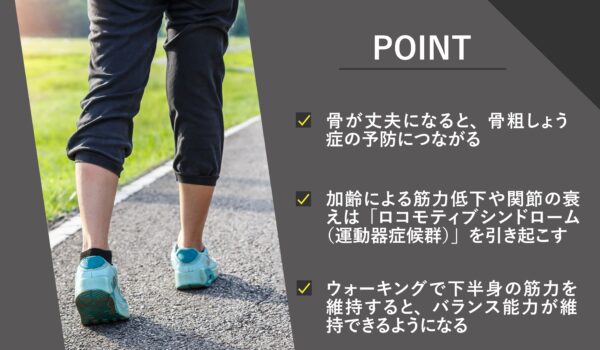
脚に適度な衝撃を与えることで骨が形成され、骨密度が上昇する。骨が丈夫になることで、骨折しやすくなる骨粗しょう症の予防につながることも。
加齢による筋力低下や関節の衰えは、身体を支え動かす「運動器」の機能が低下した「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」を引き起こすが、ウォーキングを通じて下半身の筋力を維持するとバランス能力が維持でき、転倒や骨折のリスクを下げることに役立つ。
ストレス解消ができ心の健康につながる

外で身体を動かす機会を作ることで心が落ち着き、日常のストレスから距離を置ける。とくに自然豊かな場所を歩くことで、音や香りなど五感が刺激される。ウォーキング中は脳からセロトニンやドーパミンなどのいわゆる「幸せホルモン」が分泌され、気分の安定や前向きな感情をもたらす効果が期待できる。
脳が活性化して認知機能が向上する

ウォーキングによって脳への血流が増加し、酸素と栄養の供給が活発になることで脳が活性化。また2009年に発表されたアメリカの研究によると、適度な有酸素運動はBDNF(脳由来神経栄養因子)の発現をうながし、海馬の体積を増やしたり、認知機能の改善に役立つ効果が確認されているとのこと。
筋肉が柔軟になり腰痛改善につながる
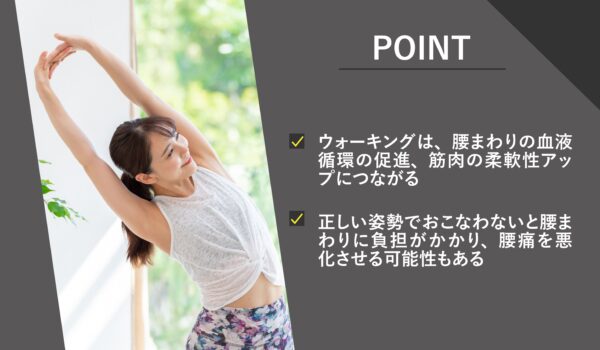
腰まわりの筋肉が固まってしまうと腰痛になりやすくなるが、ウォーキングをすることで腰まわりの血液循環の促進、筋肉の柔軟性アップにつながる。ただし、正しい姿勢でおこなわないと腰まわりの筋肉に負担がかかり、かえって腰痛を悪化させることもあるため注意が必要。
ウォーキングの効果が出るまでの期間

- 体力の向上が感じられるのは「最短1〜2週間」
- 「2〜3ヶ月」継続すると身体の変化を感じられる
体力の向上が感じられるのは「最短1〜2週間」
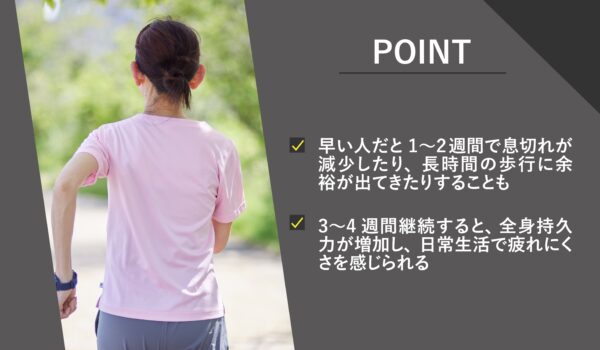
早い人だとウォーキングを始めて1週間、2週間と経過するにつれて、息切れが減少したり、長時間の歩行に余裕が出てきたり、体力面での変化を実感できることも。個人差はあるものの、3〜4週間ほど継続すると心肺機能の向上によって全身持久力が増加し、日常生活で疲れにくさを感じられる。
「2〜3ヶ月」継続すると身体の変化を感じられる
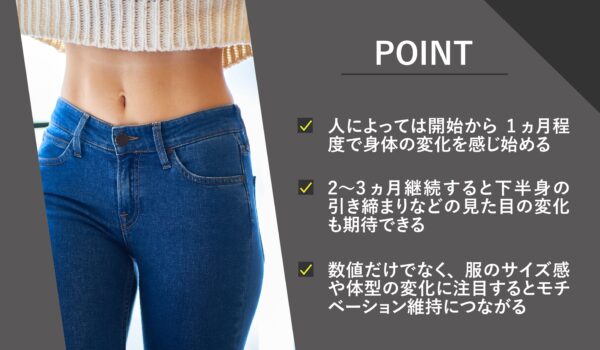
人によっては開始から1ヵ月程度から身体の変化を感じ始め、2〜3ヵ月継続すると、ウエストまわりのサイズダウンや下半身の引き締まりなど、見た目の変化も期待できる。数値だけでなく、服のサイズ感や体型の変化にも注目することでモチベーション維持につながる。
ウォーキングの効果を高める歩き方

- 背筋は伸ばし視線は15mほど先に向ける
- 腕は90度に曲げ後ろまで大きく振る
- かかとから着地してつま先で蹴り出す
- なるべく週に3〜4回習慣づけておこなう
- 心拍数は最大心拍数の60〜80%程度を維持する
- 汗ばむ程度の速歩きを意識する
背筋は伸ばし視線は15mほど先に向ける

背筋を伸ばして顎を引き、視線は15メートルほど先を見据えることで、正しい姿勢を保てる。地面を見下ろすと首や肩に余計な力が入り、疲労の原因になるため注意が必要だ。
腕は90度に曲げ後ろまで大きく振る

自然な振り幅で腕を前後に振ることで胸や背中の筋肉が動くだけでなく、上体を安定させるために体幹部の筋肉も使うため、全身運動に。軽くこぶしを握り、ひじを90度程度に曲げ、前後に自然とリズミカルに振ることでバランスの取れた歩行が可能に。歩幅が広がる効果も期待できる。
かかとから着地してつま先で蹴り出す

ひざを伸ばしたままかかとから着地し、足の裏全体で地面を感じたら軽く膝を曲げてつま先で地面を蹴り出すように歩く。この一連の動作を繰り返すことによって足首やひざへの衝撃を軽減しながら、効率的に前に進める。ただし着地の際にかかとを意識し過ぎてしまうと、ふくらはぎの筋肉に負担がかかる可能性があるため、足裏の中心から着地するイメージでおこなおう。
なるべく週に3〜4回習慣づけておこなう

WHOが推奨している週の運動時間の目安は150分。1日おきに20〜30分間おこなうことで、150分の運動時間を確保しやすく、運動習慣を無理なく継続できる。ただし、ダイエットなど体型をシェイプアップしたい場合は、筋トレにかける時間をウォーキングよりも多くし、筋肉に負荷を与えることが大切。
心拍数は最大心拍数の60〜80%程度を維持する

ウォーキング中の適切な心拍数は、脂肪燃焼なら最大心拍数の60〜80%、体脂肪率を減らして健康維持を目指すのであれば最大心拍数の50〜70%を目安にしよう。最大心拍数の目安は「220−年齢」で計算でき、たとえば40歳の場合、90〜126回/分が適切な運動強度の範囲となる。
汗ばむ程度の速歩きを意識する

ゆっくりとした歩行では十分な運動強度とはいえず、ウォーキングの効果は出づらい。軽く汗ばむ程度で速歩きを意識しておこなうのが重要。会話ができるかできないか程度での強度を維持しよう。
ウォーキングはいつ取り組んでもOK!時間帯による効果の違い

ウォーキングを含む運動は継続することが大切。そのため、「どの時間帯にやるべきか」ではなく「どの時間帯なら続けやすいか」を考えるようにしよう。ここでは、時間帯別のメリットを紹介。
- 【朝】1日の代謝が上がりやすくなる
- 【昼】午後の眠気防止にも役立つ
- 【夕方】仕事終わりのリフレッシュに
- 【夜】夕食後の血糖値急上昇予防・睡眠の質が向上
【朝】1日の代謝が上がりやすくなる
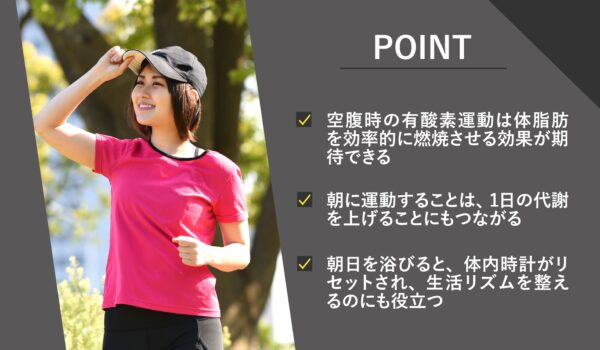
空腹時の有酸素運動は体脂肪を効率的に燃焼させる効果が期待できるため、ダイエット目的なら朝がおすすめ。とくに午前中は代謝が低いため、朝に運動することで1日の代謝を上げることにもつながる。また、朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、生活リズムを整えられることも。

脳のウォーミングアップにも朝の適度な運動が効果的です。重要な仕事や難しい課題、プレゼンテーションなどが控えていたら、ギリギリまで睡眠を取るより身体を動かして脳のウォーミングアップも一緒におこなうのがおすすめです。
【昼】午後の眠気防止にも役立つ
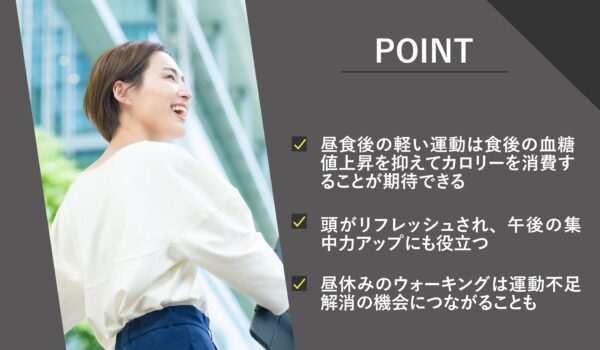
昼食後の軽い運動は食後の血糖値上昇を抑えてカロリーを消費することが期待できるだけでなく、頭がリフレッシュされ、午後の集中力アップや眠気の予防に役立つことが期待できる。また、デスクワークの多い現代人にとって昼休みのウォーキングは運動不足解消の機会につながることも。

昼のウォーキングには気分転換や午後の眠気予防の効果が期待できます。ただ、季節によっては外出自体が億劫になってしまうことも。夏は日が落ちてから、冬は最高気温をマークする過ごしやすい時間帯におこなうと続けやすくなります。
【夕方】仕事終わりのリフレッシュに
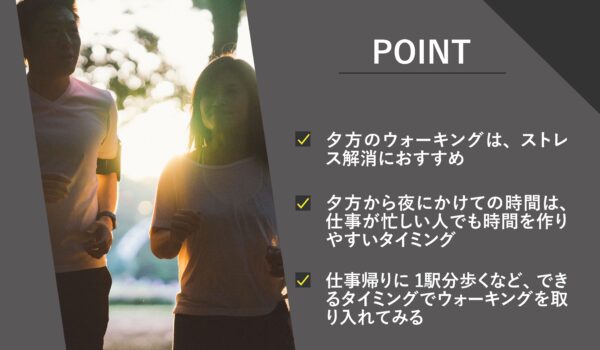
夕方のウォーキングは、1日の疲れを癒やすリフレッシュやストレス解消におすすめ。また仕事がひと段落する夕方から夜にかけての時間は、仕事が忙しい人でも比較的時間を作りやすいタイミング。仕事帰りに1駅分歩いてみるなど、できるタイミングでウォーキングを取り入れてみよう。

仕事終わりにウォーキングの予定を入れておくことで1日の振り返りの時間にもなり、プライベート時間のメリハリがつきやすくなります。
【夜】夕食後の血糖値急上昇予防・睡眠の質が向上
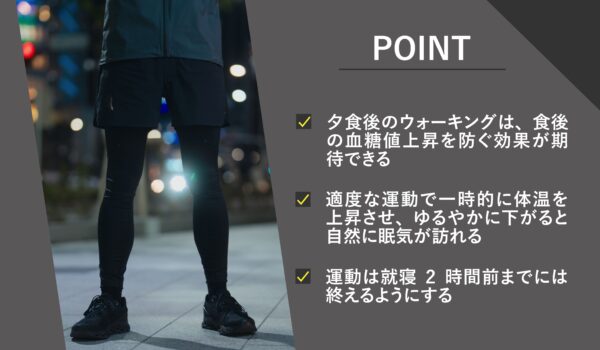
夕食後にウォーキングを取り入れると、食後の血糖値上昇を防ぐ効果が期待できる。
また、深い睡眠で脳と身体を休ませるには、体温が適切に下がっていることが重要。適度な運動で一時的に体温を上昇させ、ゆるやかに下がるなかで自然な眠気が訪れたら、質のよい睡眠につながるだろう。ただし、運動によって身体が興奮してしまうとかえって寝つきが悪くなるため、就寝2時間前までには終えるよう。

食後の血糖値上昇を抑制する効果を期待する場合は、空腹時でなく食後にウォーキングを取り入れましょう。
以下の記事では、睡眠の質を高めるための具体的なやり方や睡眠前のルーティンを紹介。身体の疲れや睡眠に関して悩みがある人はチェックしてみて。
朝までぐっすり寝る方法は?質のいい睡眠をとるポイントを解説
5人に1人が睡眠に満足できていない 厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査報告」によると、20歳以上の約2割が睡眠の質に不満を抱えている。現代人が睡眠時間を確.....
【年齢別】1日の効果的な歩数(目安)

ウォーキングをおこなう上で簡単な目安になる指標の1つが「歩数」。歩数計はもちろん、スマートフォンの機能にあらかじめ搭載されていることもあるため、誰でも簡単に把握できる数字でもある。
ここでは、年齢別で目安となる歩数を紹介。通勤通学など日常の歩数にプラスしてどれくらい歩く必要があるか把握してみよう。
- 【20~64歳】8,000歩/日
- 【65歳以上】各6,000歩/日
【20~64歳】8,000歩/日

20〜64歳の目標歩数は、1日8,000歩(厚生労働省 健康づくりのための身体活動基準に基づく)。1,000歩の所要時間は約10分が目安。通勤や買い物といった普段の生活動作に加えて積極的に階段を利用する、1つ前のバス停で降りて歩くなど、日常生活での工夫を取り入れよう。

仲間と一緒に取り組む環境を作るのもモチベーション維持に効果的です。歩数に応じて寄付や特典が得られるアプリなどを活用し、ウォーキングに対するリターンを得られると目標にしやすいですね。
【65歳以上】各6,000歩/日
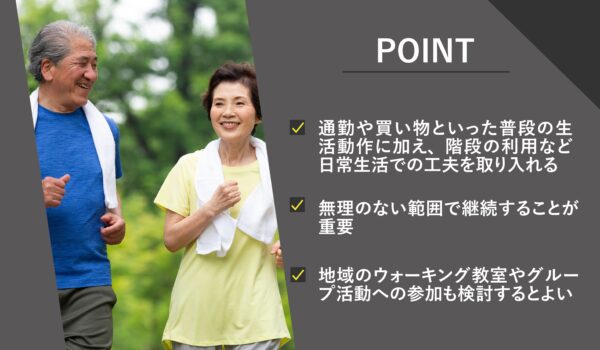
65歳以上の目標歩数は、1日6,000歩(厚生労働省 健康づくりのための身体活動基準に基づく)。ウォーキングは転倒予防や認知機能の維持に効果的なため、無理のない範囲で継続することが重要。地域のウォーキング教室やグループ活動への参加なども検討したい。
ウォーキングの効果を高めるコツ

ウォーキングの効果を高めようと無理をするのは禁物。自身の体力レベルや体調に合わせたペースからはじめ、徐々に歩ける距離や速度を高めていくようにしよう。
- 無理のない速さと距離から始める
- こまめに水分補給をおこなう
- ひざや腰に痛みを感じたら休む
- 天候が悪い日は室内で歩く
無理のない速さと距離から始める
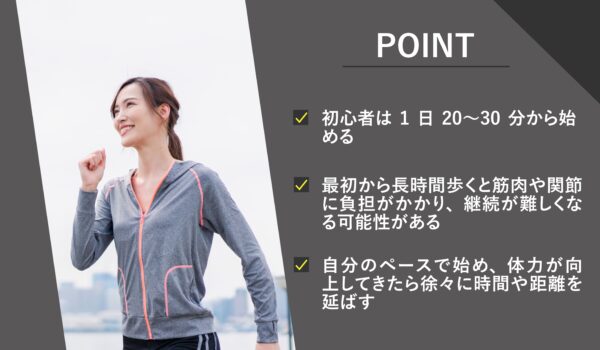
初心者は1日20〜30分から始めよう。最初から長時間歩くと筋肉や関節に負担がかかり、継続できなくなる可能性も。無理をせず自分のペースで始め、体力が向上してきたら徐々に時間や距離を延ばす。無理なく習慣化につなげよう。
こまめに水分補給をおこなう
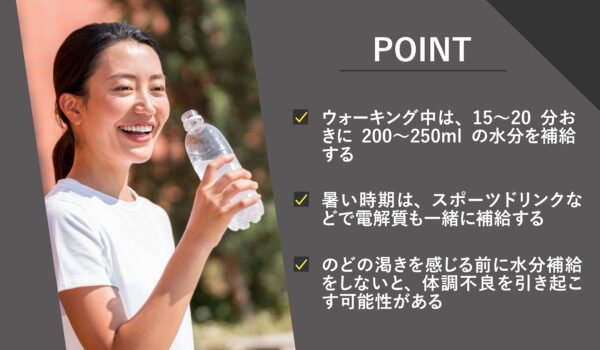
ウォーキングの前後はもちろん、最中は15〜20分おきに200〜250mlの水分を補給しよう。暑い時期はとくに注意が必要で、スポーツドリンクなどで電解質も一緒に補給。のどの渇きを感じてからでは遅く、体調不良を引き起こす可能性もある。

ドリンクボトルを携帯できるランニングポーチも販売されているので、運動に集中しながら水分補給をできる工夫をしてみましょう。
ひざや腰に痛みを感じたら休む

身体に違和感や痛みがあるにも関わらず無理に歩き続けると、症状が悪化し長期的なダメージにつながる可能性がある。痛みを感じたら運動は中止して休息をとり、痛みが続く場合は医師に相談しよう。
天候が悪い日は室内で歩く
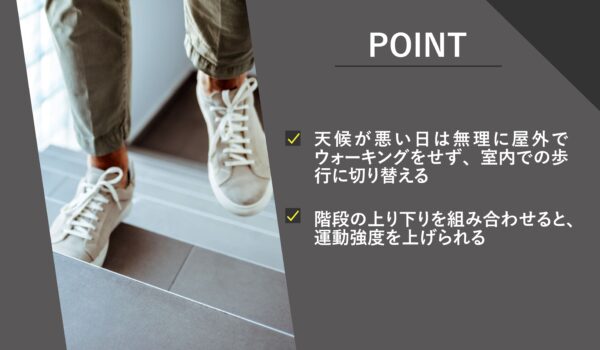
雨や強風、猛暑日などは無理に屋外でウォーキングをおこなうのでなく、商業施設や駅の構内など、室内での歩行に切り替えよう。階段の上り下りを組み合わせることで、運動強度を上げることもできる。

自宅で有酸素運動をおこなうなら踏み台や室内の階段を利用した「踏み台昇降」がおすすめです。テレビをみながら運動することもでき、取り組み方によってはジョギングやランニング並みのエネルギー消費も可能です。
ウォーキングの効果に関するQ&A

どのくらいで身体の変化が感じられる?
A:1ヶ月ほど

筋肉量の増加や体脂肪減少については効果は期待できないものの、1ヶ月ほどで心肺機能の向上や体力アップを感じられるでしょう。
「ゆっくり歩き」と「速歩き」どちらがよい?
A:速歩き

ウォーキングによる運動効果を高めるためには速歩きがよいでしょう。また歩く距離よりもスピードを意識する方が消費エネルギーも高まりやすくなります。
ウォーキングのやりすぎは太ると言われるのはなぜ?
A:筋肉量が少ない状態で同じ運動を長時間繰り返すと、怪我につながり活動量が減る

筋トレをしないで有酸素運動だけを行うと筋肉量は減ってしまうため、エネルギー消費量も下がってしまいます。また、筋肉量が少なくなっている状態で同じ運動を過度に繰り返すと関節を傷め、活動量が減り、結果として体重増加につながる可能性があります。
ウォーキングマシンを使うのと外で歩くのでは効果に違いがある?
A:外で歩くと自律神経が整いやすい

ウォーキングマシンを使っても問題ありませんが、外で歩くのと比べて飽きやすい場合もあります。室内は温度が一定ですが、外を歩く際は気温差に身体が適応しようとすることで自律神経が強化されるというメリットがあります。
室内でウォーキングの代わりになる運動ってある?
A:踏み台昇降やエアロバイクなど

室内でおこなう場合は、代わりの運動として踏み台昇降運動やエアロバイクなどがおすすめです。踏み台昇降であればランニングやジョギング並みのエネルギーを消費でき、階段でおこなえば場所もとりません。エアロバイクも強度が高ければ脚の筋肉が鍛えられる運動です。
ウォーキングと水中ウォーキングはどっちが痩せやすい?
A:どちらも一長一短がある

水中ウォーキングは身体の負担が少なく、ひざなどにかかる負担は少ないですが単体だと十分な運動にはなりません。効果を得たい場合は、陸上ウォーキングを30分、水中ウォーキングを30分組み合わせておこなうのがおすすめです。

アメリカスポーツ医学会認定運動生理学士として、運動の大切さを広める活動を行っている。2014年からは青山学院大学駅伝部のトレーナーも務めており、東京神楽坂にある会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB100」で一般の方やアスリートを指導。「科学的根拠に基づき、必ず結果を出す」が合い言葉で熱意のある指導を常に心がけている。