
「マイナビは“人”がすべてです」。そう繰り返すのは、同社サステナビリティ・トランスフォーメーション推進室の山本智美さん。
「働き方改革」「ダイバーシティ推進」「ウェルビーイング経営」など、いま企業の人への向き合い方が問われるなかで、山本さんは「サステナビリティ」という大きなテーマと向き合っている。
マイナビが大切にしてきた文化とは何か。多様性を育む組織づくり、そして彼女自身の使命感とは? 山本さんのこれまでのキャリアと、企業がこれから進むべき「人を起点とした組織のあり方」について、Wellulu編集長の堂上研が話を伺った。

山本 智美さん
株式会社マイナビ取締役 常務執行役員
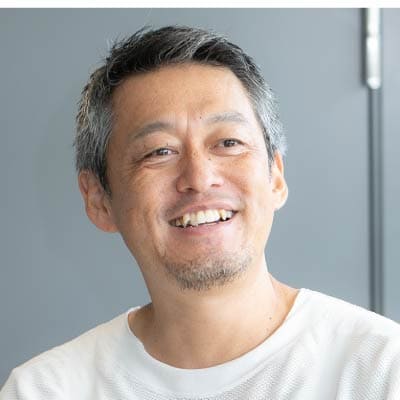
堂上 研
株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu編集長
1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。
破天荒に突き進む「我が道」精神

堂上:今日は山本さんの生き方や働くことへの考え方、人への思いについて、じっくりとお話をうかがいたいと思ってます。まずはリラックスして、ご自身のことをたくさん話してもらえたら嬉しいです! たとえば、子どもの頃ってどんな子だったのかなとか、ご両親にどう育てられたのか……。そんなところからお聞きできればと思います。
山本:私、多分、破天荒だったんだと思います。30代の頃、当時の社長に「お前は破天荒だな」って言われたことがあって。そのときは「えっ、何のこと?」と思ったんですが、自分の行動を振り返ると、確かに……って思うところもあります。
堂上:ぜひ、その“破天荒エピソード”を聞かせてください!
山本:子どもの頃は放任主義で育てられました。親から「これをやりなさい」なんて言われた記憶はなくて、いつも自分の意思で決めてましたね。自分でやりたいことを見つけて、親に「これがしたい」と伝えると、だいたいさせてもらえていたんです。
だから仕事で「破天荒」って言われたのも、自分の普通だと思ってるスピード感でどんどん進めちゃうところがあるからかもしれません。
堂上:なるほど。その“破天荒”というのは、「芯がぶれない人」という意味も含まれているかもしれませんね。小さい頃から夢中になったこととか、今でもハマってることってありますか?
山本:お稽古ごとはいろいろやっていました。習字もピアノもやっていたんですが、一番ハマったのは「洋裁」ですね。大学時代はアルバイト代のほとんどを洋服につぎ込んでいました(笑)。
堂上:そこまで洋服に惹かれた理由って何だったのでしょう?
山本:自分探しです。自分に似合うもの、自分らしさを表現できるものを求めていたんだと思います。既製品では物足りなくなって、自分でデザインして作るようになったんです。
堂上:すごい行動力ですよね。まず手を動かしてみて、進めながら考えるタイプなんですね。
山本:はい。走りながら考える、まさにそのスタイルです。

堂上:小さい頃のお話を聞いていると、山本さんはまさに新規事業開発に向いている人だなと感じます。破天荒という言葉の奥には、自分で道を切り拓く力があるということですよね。
山本:そう言ってもらえると嬉しいです。でもマイナビに入ったときは、じつは出版志望だったんですよ。女性誌を作りたくて「編集長を目指そう!」と意気込んで入社しました。ただ当時は新卒社員はほとんど、新卒採用領域の法人営業部隊に配属されるのがお決まりで、私もまずはそこからキャリアがスタートしました。
堂上:そこからどうやって出版領域へ?
山本:30代前半で奇跡的に出版事業へ異動できたんです。広告営業を経て、念願の編集の名刺をもらいました。その後、新雑誌の立ち上げメンバーとして、編集者が広告も取りに行く。そんな働き方も経験しました。
堂上:編集者として「0→1」に挑戦されたわけですね。
山本:そうですね。とにかく、売れるものを作らないと生き残れない世界でした。書店で競合雑誌を隅から隅までチェックして、どんな広告が載っているのか、どんな特集が読まれているか……徹底的に研究しました。正解がないなかで、自分で掴み取るしかない。そんな経験が、今の私の“筋肉”になっています。
仕事と遊びが曖昧な現代だからこそ「余白」を大切に

堂上:山本さんを見ていると、すごく楽しそうにお仕事されている印象があります。それってマイナビの社風なのでしょうか? それとも、山本さん自身がマイナビにマッチしているのか……。
山本:よく他社の方から「マイナビさんって、ジャングルみたいだよね」って言われるんです。いろんなところにいろんな生き物がいて、カオスなジャングル。でもそれが妙に腑に落ちて。じつはうちってすごく多様なんですよ。
堂上:いい表現ですね。最初から多様性を意識して採用していたんですか?
山本:今でこそ「ビジョナリーカンパニー」や「理念採用」と言いますが、私が入った頃のマイナビはそういう採用はしていなかったです。事業自体が面白いから、自然と面白い人材がドアノックしてきてくれる。欲しい人材像を絞って採用するというより、結果的にいろんな人が集まって多様性が生まれていましたね。
堂上:僕らエコトーン社も、多様な人が集まることで新しい生態系をつくると考えています。多様な人とぶつかり合うことで、新しい気づきが生まれる、そんな空気感が大事だなと。
山本:そうですね。毎日新聞社グループという影響もあるかもしれません。メディアの自由なカルチャーがあって、「もっといろんなことをやろう」という風土がありました。たとえば、中国との文化交流プロジェクトとか。
堂上:文化交流? それはまたユニークな……。
山本:前社長の発案で、学生さんや先生をクラブ活動単位で中国に連れて行って、現地の学生と交流するっていう取り組みがありました。社員が添乗員になって、生徒さんたちをサポートするんですけど、今思えばすごくユニークな経験でしたね。
堂上:そういう「遊び」が会社のなかにあるのって素敵ですね。ただ最近は、多くの企業でその「余白」がなくなってきてる感じがします。ステークホルダーへの対応が求められるなかで、遊びが減っている。山本さんはその「遊び」をどう考えていますか?
山本:やっぱり社会全体の閉塞感が影響している気がしますね。コンプライアンスやリスクマネジメントで守るべきものが増えた結果、余白が削られていく。でも昭和の経営層って、猛烈に働きながらも「遊び」をつくっていたと思うんです。本能的にバランスを取っていたというか。
堂上:今は仕事と遊びがゆるく混ざり合っているぶん、余白の境目も曖昧になっている気がしますよね。
山本:そうなんです。そして、会社が大きくなればなるほど、管理主義的になっていく。時間的な制約も強まるし、ハラスメントリスクも増えるし……。
堂上:もちろん昔ながらの働き方が正解ではないけれど、ウェルビーイングに働くためには余白も欠かせません。そんななか、マイナビさんのような大きな企業が「働く価値観」を変えていけば、社会に与えるインパクトも大きいですよね。
山本:まさに、今、私たちはそのターニングポイントにいると感じています。まだ変わりきれていないけれど「変わらなければいけない」というその危機感は、強くなってきていると思います。
すべては「人」ありき。個を大切にするマイナビの文化

堂上:山本さんは、小さい頃から破天荒にチャレンジしてきて、マイナビに入っても「やりたい」と言い続けて、いろんなことを実現されてきたんですよね。そういう人たちがもっと増えれば、働く人のエンゲージメントもウェルビーイングも高まるんじゃないかと思います。
最近だと「サステナビリティ」「多様性」「ウェルビーイング」みたいな言葉が、全部一緒に渦巻いてる感じがしていて。そんななかで、山本さんが考える「サステナブルに働ける環境」って、どんなものですか?
山本:社員一人ひとりが自分らしく働けて、仕事も遊びも楽しめる。そんな状態が「サステナブルな組織」だと思います。
堂上:マイナビさんならではの、そういった状態を支える仕組みってありますか?
山本:特徴的なのは「全社表彰式」ですね。年に一度、事業部を超えて活躍した社員を表彰します。コロナ禍前までは賞金に加えて海外を含めた顕彰旅行もついていて、役員も一緒に行っていました。
堂上:それは素敵ですね。大きな会社になればなるほど、現場と経営層の距離って開きがちですが、そういう機会があるのは貴重だなと思います。
山本:私も事業責任者としてラスベガスに行ったことがあるんですが、100人で行ったのは圧巻でした。社員のご家族も驚くんですよ。「お父さん(お母さん)、100人でラスベガス行ったの? マイナビってすごい会社だね」って(笑)。それも含めて社員が楽しく働ける空気が生まれるんですよね。そういうお金や時間をかける企画は、社員にも会社の労いの意が伝わり、私はすごく良いと思っています。
ただ、コロナ以降は少し形を変えて「パーパスデー」という全社イベントに移行しました。表彰式は今も続いていますが、もっとスマートに、けれど「人を讃える文化」はちゃんと継承しています。
堂上:社員一人ひとりと向き合う姿勢は、やっぱりマイナビさんの文化なんですね。
山本:そこは揺るがないですね。マイナビは「人」がすべてですから。とはいえ大企業になってくると、どうしても一人ひとりと対話するのが難しくなる。だから、1on1のような縦のコミュニケーションはもちろん、横のつながりを生む仕掛けも意識しています。
堂上:たとえば、どんな仕掛けがあるんでしょう?
山本:事業部を超えた手上げ式の研修プログラムですね。マネジメント研修やAI研修など、テーマはさまざまです。自ら手を挙げた社員が集まって、部署を超えて学ぶ場が用意されています。けっこう人気で、多くの社員が積極的に参加してくれています。
堂上:いいですね。そういう場に積極的に手を挙げる人が増えているのは、組織が進化してる証拠ですね。それに、部署を超えて別のコミュニティが生まれるのも素敵ですね。
僕たちがウェルビーイングについて調査していてわかったのが、「複数のコミュニティを持っている人ほど、ウェルビーイング度が高い」ということなんです。たとえば、会社でのチームと家庭の2つだけが居場所だと、どちらかがうまくいかなくなった時に孤独感や閉塞感を感じやすくなる。でも、別のコミュニティがあれば、そこで気持ちを切り替えられるし、リフレッシュできるんですよね。
山本:その点、マイナビは多事業展開しているからこそ、部署を超えた多様な人たちが自然とコミュニティを形成できる土壌があると思います。
堂上:経営層と現場がフラットに話せる文化もそうですし、多様な人が集まる“ジャングル”のような会社だからこそ、自然とコミュニティが生まれているんですね。
サステナビリティ推進の本質は「社員の幸せ」

堂上:山本さんは今年から、サステナビリティ・トランスフォーメーション推進室にいらっしゃいますよね。企業文化の変革にもつながる重要なテーマだと思うのですが、山本さん自身は「サステナビリティ」をどう捉えていますか?
山本:じつは私、まだ“サステナ1年生”で、今まさに学んでいるところなんです。ただ、強く感じているのは、サステナビリティは「本業への貢献」そのものだということ。サステナビリティって、どこか特別な取り組みに聞こえがちですが、本業と一心同体なんですね。
着任直後に日本を代表する企業のサステナビリティ責任者の方々とお話しする機会があって、「サステナビリティは経営そのものであり、本業にどう組み込み、本業をどうトランスフォーメーションするか」という本質を掴めた時に、私の中で霧が晴れたような感覚がありました。それ以降、迷いなく「どう本業とつなげ、本業を押し上げるか」を軸に、当社の強みを発揮しながら、その一線上に、社会(世界中)とのつながり方・社会への貢献をあたり前に考える、というシンプルな思考に着地しました。
だからこそ、社員一人ひとりが、事業に向き合うのと同様に、サステナビリティを「自分ごと」として向き合えるようにすることが、私の役割だと思っています。
堂上:まさに経営の本質ですよね。サステナビリティを語る際には「誰のためのものか」という問いも大切だと思いますが、山本さんはまずは“社員のため”と考えていらっしゃるわけですね。
山本:はい。会社のサステナビリティは、社員一人ひとりのサステナビリティと同義と考えています。ついては、社員の幸せが、企業のサステナビリティのバロメーターになると思います。社員がいきいきと持続的に活躍できる環境づくり(健康経営とも同義)が、持続的に高成長できる長寿企業をつくり得る。そのような企業こそが、社会課題に向き合い、真の社会貢献を成し遂げる存在となり得る、サステナブルな企業と考えます。
堂上:同感です。僕も、企業や社会のウェルビーイングを考えるうえで「まずは自分を好きになる」「自分を大切にする」ことを大事にしています。社員一人ひとりがウェルビーイングであることが、結果的に社会やステークホルダーとの良好な関係を築くベースになるんですよね。
山本:本当にそう思います。いまの時代、たった一人の社員の不満や不幸が、企業全体の綻びにつながることだってある。だからこそ「個」としての社員に、どれだけ真摯に向き合えるかが、企業の持続可能性を左右すると思っています。
堂上:マーケティングの世界では「CSV(Creating Shared Value)」という言葉があります。CSRの先にある考え方で、本業を通じて社会に価値を還元していくというものですが、まさにサステナビリティと本質は同じですよね。
山本:そうですね。サステナビリティのトップランナーとも呼ばれる某アパレルメーカーの経営者とお話しする機会があったんですが、彼らのスタンスに感動しました。たとえば、壊れた商品を持ち込まれた時、普通なら新しい商品を提案しがちですが、同社は必ず「お直ししましょう」と伝えるんです。目先の売上を追う前に、顧客との信頼関係を大事にする。この考え方がまさにサステナビリティの本質だと感じました。
堂上:素敵なお話ですね。それは社員との関係性にも通じますよね。企業と社員、企業と社会、どれも「信頼」がベースになっています。
山本:まさに。社員一人ひとりとの信頼関係を大切にすることが、サステナビリティの根幹だと思っています。
これからの経営に欠かせない同質性からの脱却と管理から信頼へのシフト

堂上:先ほど「マイナビは“人”です」とおっしゃっていたのが、すごく印象に残っていて。人が起点になる会社運営は、これからますます重要になります。ただ、人は多様であるからこそ、価値観の押し付けが起きることもある。それはウェルビーイングを阻害する要因にもなりえますよね。そうならないために、企業はどう変わるべきだと思いますか?
山本:「同質性からの脱却」こそが、今の企業が向き合うべきテーマだと思います。似た価値観だけで物事を決めていくと、すぐに限界が来るんですよね。だからこそ、外からの風を取り入れて、常にアップデートし続ける風土が必要。同質性が強くなりすぎてしまった組織は、意図的に壊すくらいの勇気も必要かもしれません。
堂上:まさに多様性ですね。ウェルビーイングに働くためには、自分たちが知らなかったことに気づかせてくれる環境が欠かせません。マイナビさんの社内でも、部署を越えたコミュニケーションの仕掛けなどはありますか? 先ほどの研修のような形で、越境的なつながりをつくっているとお聞きしましたが。
山本:もちろん部署内ではコミュニケーションの機会を設けていますが、正直まだ足りない部分もあります。最近強く感じているのは、「サステナビリティは“横軸”を刺す存在だ」ということです。現場もコーポレート部門も、それぞれが真剣に全力で業務に向き合っている。だからこそ、部署を超えてつなぐ「横串」の存在が必要なんです。それこそが、私たちの役割なんだと思っています。
堂上:伊能美和子さんが提唱している「ヨコグシスト®︎」ですね。
山本:私も伊能さんのような、人と組織をつなげるヨコグシスト®︎精神を大切にしたいと思っています。
堂上:サステナビリティも、ウェルビーイングも、結局は「横串」の思想に集約されている気がしますね。お互いを越境して、お節介を焼いて、つながっていく。そんな関係性が、本質なんじゃないかと思います。
山本:もうひとつ大事なのは、管理や支配ではなく、信頼にシフトすることだと思います。縛るのではなく、社員を信じて任せる。そういう信頼関係がなければ、サステナビリティは実現しません。

堂上:その考え方は、まさにWelluluでも大切にしている視点です。信頼があるからこそ、人は力を発揮できるし、組織はしなやかに持続可能になっていきます。
山本さんが目指す「サステナビリティな会社」はどんなものでしょうか。
山本:私は、「公」と「私」は切り離せないものだと思っています。プライベートを犠牲にしてまで働いていたら、どこかで限界が来る。ですので、「社員一人ひとりがワクワクしながら、最大のパフォーマンスを発揮できる環境」をつくりたい。
長年、現場で人材紹介サービスのマッチングに携わってきた経験からも思うのですが、社員を管理するのではなく「解き放つ」ことこそが、個の強みを発揮させる最も効果的な方法なんです。そのために、ミスマッチを防ぎ、社員が活きる適正な配置や成長機会を設計していくことが、企業の責任だと感じています。
堂上:そこにAIやテクノロジーのちからが絡んでくる未来も見えますね。
山本:もちろん、AIも重要です。でも、最終的には「人」がすべてです。私たちは長年、人材紹介業を通じて“人と組織のマッチング”に向き合ってきました。このノウハウこそ、これからの経営や組織づくりに求められるものだと思っています。
この業界で大切なのは、人と組織をつなぐ“マッチング”の部分なんですよね。求人媒体は「集める手段」として大事ですが、集まった人材とどう向き合い、どうつなぐか。その“ソフトの部分”が本質であり、そこにはやっぱり「人の力」が必要なんです。私たちには、1千人を超えるプロフェッショナルな人材コンサルタントがいて、この存在こそが事業の核であり、今後も成長を支える要となります。
堂上:AIが進化しても、最後に判断するのは人。だからこそ「人を信じる力」や「人を活かす力」が問われていく時代になりそうですね。
山本:そう思います。テクノロジーが進化するほど、人のちからが軽視されがちになりますが、最後の最後で意思決定をするのは人です。それを忘れた瞬間、会社は崩れてしまう。だから私は、何があっても「すべては人に帰ってくる」という原点だけは忘れないようにしています。
堂上:そのお話を伺って、山本さんは10年後、20年後もきっと「破天荒」でいらっしゃるんだろうなと思いました。
山本:もっと破天荒かもしれませんね。ヨコグシスト®、極めますから(笑)。
堂上:その進化、楽しみにしています! 今日は貴重なお話を本当にありがとうございました!
山本:こちらこそ、楽しかったです! ありがとうございました。


1994年、毎日コミュニケーションズ(現・マイナビ)に入社。就職情報事業本部営業6年、出版事業本部 広告営業・編集3年担当。2002年から紹介事業の立ち上げに携わる。2004年事業責任者に就任。2007年分社化、毎日キャリアバンク社長に就任。2012年合併後、2016年取締役就任。
2020年取締役常務執行役員へ。2022年にヘルスケア&ウエルネスセグメントセグメント長就任。2025年からサステナビリティ・トランスフォーメーション推進室。中学生の子どもを持つワーキングマザー。