
腰痛や肩こり、不眠。その原因は、実は「寝具」にあるかも?寝具は毎日の健康を支える基盤であり、質の高い睡眠を実現するための大切な要素。日本寝具寝装品協会(JBA)は、科学的エビデンスに基づく「ヘルスケア認定寝具™」制度を通じて、安心して選べる寝具の普及を推進している。また、専門人材「睡眠環境・寝具指導士」の育成を進め、生活者に寄り添ったアドバイスを届けている。本記事では、専務理事・村本修一氏に、寝具の重要性と協会の取り組みについて伺った。

村本 修一さん
一般社団法人 日本寝具寝装品協会 専務理事
本記事のリリース情報
ウェルビーイングに特化したWebメディア「Wellulu」にて「ヘルスケア認定寝具制度」と「睡眠環境・寝具指導士」に関するインタビューを受けました。
私たちの睡眠を支える「寝具の重要性」を再認識する

── 本日はよろしくお願いします!まずは寝具についてお伺いをしたいです。寝具ってなんとなくで選びがちですが、睡眠の質に対して影響を与えるのでしょうか?
村本さん:はい。睡眠の質を左右する大きな要素の1つが寝具です。マットレス、枕などが身体をしっかり支えることで寝姿勢や体圧分散が整い、背骨や腰の負担を減らせます。こうした基盤が整うことで深い眠りにつながりますね。
── なるほど。では、間違った寝具を選んでしまうとどうなりますか?
村本さん:腰痛や肩こりが出やすくなります。柔らかすぎるマットレスは腰が沈み込み、硬すぎるものは肩や背中に圧力がかかります。枕も高さが合わないと首に負担がかかり「寝違え」につながります。
── 寝具を選ぶとき、多くの人は価格やデザインで決めがちですよね。
村本さん:確かに「値段」や「見た目」で決める方が多いです。ですが、睡眠の質を考えると「身体に合っているか」が最優先です。布団カバーなどは比較的自由に選べますが、マットレスや枕は体格や寝姿勢に合わせて選ぶ必要があります。
── 実際に合う寝具を見つけるには、どうしたら良いのでしょう?
村本さん:一番大事なのは「体験すること」です。販売店で実際に寝てみて、自分の身体に合うか確認してください。最近は専門スタッフが寝姿勢を見てアドバイスしてくれるお店もあります。ネット情報や口コミだけで判断するのはリスクがありますね。
── 1度試すのは大切ですよね。ただ、私もそうなのですが、実際にお店で試しても、正直「これでいいのかな?」とわからない部分もあります。
村本さん:確かに自分で判断するのは難しいですよね。短時間で完璧に判断するのは難しいですが、ポイントを絞って確認すると良いです。例えば「横向きで肩が痛くないか」「仰向けで腰が沈みすぎないか」などですかね。専門家に相談すれば、客観的に寝姿勢を見てもらえるので安心です。
── ポイントだけ絞れば判断できる気もしました。また、「合わない」をベースに決めるのもありだなと思いました。例えば、ホテルでは寝づらいとか、普段と違う環境だと眠れない、という人も多い印象でこのやり方でも判断しやすいと思いました。
村本さん:それはよくありますね。普段お使いの寝具とホテルの寝具は硬さや高さが違うため、身体が慣れていないと眠りにくくなります。逆に、ホテルの寝具のほうが合っていて「家よりよく眠れる」と感じる人もいるかもしれません。結局は、自分に合う寝具をどう選ぶか?が大事ということですね。
── いろんな寝具を試して身体の声に耳を傾けることが大切ですね。今使っている寝具も改めて自分に問いかけてみようと思いました。
村本さん:はい。朝起きたときに腰が痛い、肩が重いと感じるなら寝具が合っていないサインです。寝具は毎日の健康を支える基盤なので、ぜひ時間をかけて選んでください。
寝具の機能を科学的根拠(エビデンス)から判断する「ヘルスケア認定寝具」制度の役割と意義
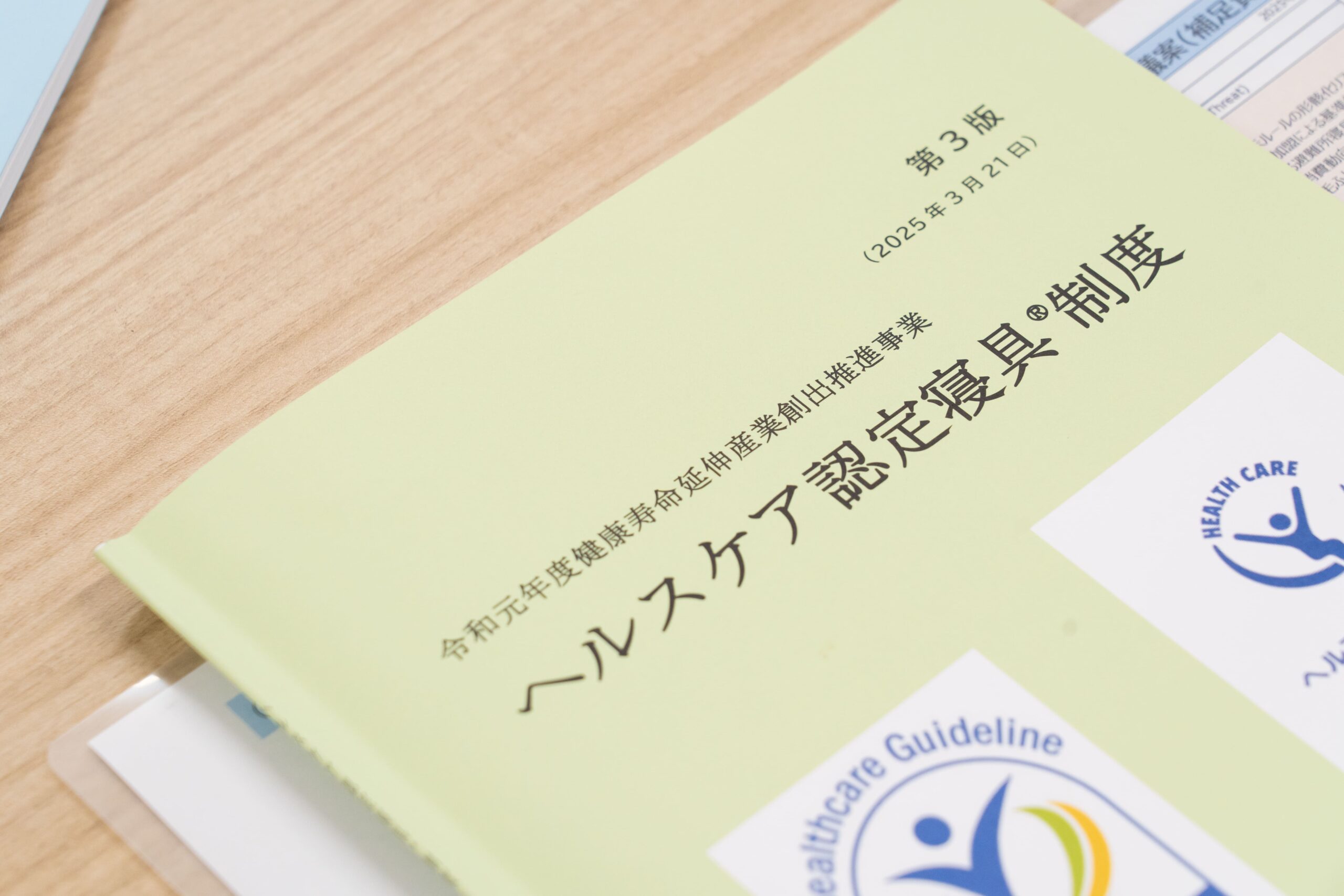
── 寝具の重要性は理解できました。日本寝具寝装品協会では、「ヘルスケア認定寝具」という制度があると思うのですが、どのような背景でそのような制度が生まれたのでしょうか?
村本さん:様々な背景があるのですが、大きな1つとして国が進めている「健康寿命の延伸」があります。厚生労働省をはじめ、政府も「睡眠の質改善」を健康政策の一部として位置づけています。その流れの中で、経済産業省の「ヘルスケアガイドライン等のあり方」ふを踏まえ、寝具業界としても「客観的に健康をサポートできる寝具」を明示する必要があり、「ヘルスケア認定制度」が立ち上がりました。
── ヘルスケア認定制度で認定されていると、消費者にはどんなメリットがあるのでしょう?
村本さん:最大の利点は「根拠が明確な寝具を選べる」ことです。単に「寝心地がいい」ではなく、専門的な検証やエビデンスに基づき「睡眠をサポートする」ことが確認された製品を選べるわけです。これによって、消費者は安心して購入でき、業界全体としても品質向上につながりますね。
── 認定基準はどのようになっているのですか?
村本さん:主に3つの機能で整理しています。1つ目が「睡眠健康機能」で快眠や休養をサポートする役割です。2つ目が「衛生機能」で、例えば清潔性や利便性など、日常的に快適に使えるかどうか。3つ目が「メンテナンス機能」で、丸洗い・防水性など寝具が本来の役割を果たせるような手入れの項目です。大きくはこの3つが生活者の睡眠を支える要素だと思っていますが、それらに加えて「企業の社会性」も評価項目として意識しています。
── 社会性というと、少し難しく聞こえますね。
村本さん:ここでいう社会性とは「持続可能な製造や事業活動に取り組んでいるか」という点です。消費者に安心して選んでもらうには、製品の性能だけでなく、企業の姿勢や社会的責任も重要です。認定制度ではそうした背景も含めて示すことを目指しています。
── なるほど。こうした観点をエビデンスをもとに認定していると思うのですが、審査はどのように行われているのですか?
村本さん:各団体や専門家の意見を取り入れながら、審査項目を設定しています。単に業界内部で決めるのではなく、医療や学術機関とも連携し、公平性を保つ形で調査・検証を進めています。審査の結果、認定マークを付与する仕組みです。
── 認定基準は1つの機能だけでも取得できるのですか?
村本さん:はい。例えば、「眠りの質改善」や「疲労のリカバリー」や「スリープテック」など、特定の分野に特化した機能でも認定を受けられます。ただし、総合的な得点基準を満たす必要があるため、もっとも重きを置く「睡眠健康機能」に加えて「衛生機能」や「メンテナンス機能」など複数の基準を組み合わせて評価されることが多いです。
【各機能の評価項目】
https://www.jba210.jp/healthcare/
── 消費者は認定内容をどのように確認できるのでしょうか?
村本さん:認定を受けた製品は、公式ホームページで「どの機能で認定されたか」が明示されます。たとえば「疲労のリカバリー+血流への作用」「体圧分散性+寝返り性」など、複数の基準を満たす場合もあります。製品ごとに違いがあるので、消費者は自分のニーズに合わせて選ぶことができます。
── 認定を取得する企業側の動きについてはいかがですか?
村本さん:企業によっては「睡眠健康機能」に特化してエビデンスを準備するケースもあります。逆に「衛生機能」に強みを持ち、そこで認定を取得する企業もあります。いずれも「第三者が評価した証明」となるため、企業にとっては信頼性の向上につながり、消費者にとっては安心材料となります。
── 認定制度を今後どのようにしていきたいですか?
村本さん:今後はさらにエビデンスの充実が求められますし、より充実させていきたいと考えています。例えばスリープテックとの連携や、AI・センサーを使った睡眠データの活用など、新しい技術が加わる可能性があります。制度としても時代に合わせて進化し、より実証的で信頼性の高い仕組みに育てていきたいと考えています。
「寝具の専門家」によるアドバイスで生活者の睡眠はどう変わるか

── 寝具のエビデンスも重要ですが、自分にあった寝具を選ぶためにはそれをアドバイスしてくれる販売員も重要になると思います。その中で、睡眠や寝具に関して、専門家の資格制度があると伺いました。どのようなものなのでしょうか?
村本さん:12年ほど前に「睡眠環境・寝具指導士」という資格制度を作りました。体系的に睡眠と寝具を学べる仕組みです。寝具の商品開発や売場での相談の場などで、専門的な知識を持つ人材を育てることが目的です。
── 資格制度が始まった背景には、どんな課題があったのでしょう?
村本さん:当時は睡眠についてしっかりと学ぶ機会が限られていました。医療の現場以外で専門性を持つ人材が少なく、寝具を販売するスタッフも「経験や勘」に頼る部分が大きかったんです。それを体系的に補強するために資格制度が導入されました。
── 睡眠といってもヘルスケア寄りの内容から専門的な内容まで幅広いと思います。専門家が学ぶ領域の中で、特に大切な分野はどこですか?
村本さん:やはり「睡眠環境学」ですかね。睡眠の生理と心理に加え、睡眠環境の構成要素には、温度・湿度・光・音・香りなどの要因が睡眠に与える影響は大きいです。資格試験でも環境学に関する科目は難易度が高いですが、それだけ重要視されています。
── こういった環境は専門家はもちろん、一般生活者の人も身につけておくべき視点ですよね。一般の人なども受けているのでしょうか?最近はリカバリーウェアや端末を使ったスリープテックも増えており、生活者の睡眠リテラシーも徐々に上がっている印象です。
村本さん:そうなんです。ウェアラブル端末で睡眠データを取る人が増え、一般の方の関心も高まっています。こうした流れもあり、資格講座の受講者数は年々増加しています。睡眠を「感覚」ではなく「データ」で理解する流れが強まっていると感じます。
── 逆に睡眠環境以外に学ぶことはありますか?
村本さん:生活習慣も大切です。カフェイン、アルコール、ニコチンの摂取は睡眠に直結します。さらに体内時計や睡眠ステージなど、睡眠のメカニズムを理解することも欠かせません。これらを理解することで、不眠や寝付きの悪さの原因を見極めやすくなりますね。
──「メカニズム」と聞くとわかりづらい印象があるので、こういった知見をアドバイスしてくれるのは助かりますね。
村本さん:「睡眠環境・寝具指導士」の役割は、生活者自身では気づきにくい原因を客観的に指摘できるところです。寝具の選び方だけでなく「生活習慣の改善」も組み合わせることで、多くの方が眠りの質を改善できています。さらに最近は、厚労省とも連携した資格制度の整備が進んでおり、社会的な信頼も高まりつつあります。
これからの寝具は「可視化」と「パーソナライズ」の時代へ

──近年、ライフスタイルが一気に変わったことで、生活者の睡眠事情も大きく変化したと思います。
村本さん:時代変化への対応のスピードが激しくなり、ストレス化社会の中での働き方にて、運動不足や生活リズムの乱れが引き起こされやすくなり、疲労感を感じる人が多くなりましたね。結果として、睡眠の質にも影響していると思います。
──徐々に生活者も企業も睡眠を意識する傾向が高まってきたと思います。そのような中、寝具に対してどのような役割が求められるとお考えでしょうか?
村本さん:今後は「可視化」と「パーソナライズ」が進むと考えています。睡眠データを活用して「自分に合った寝具」が自動的にレコメンドされる仕組みです。実際に大手メーカーでは、AIやデジタル技術を取り入れた商品開発が始まっています。
── それは面白いですね!具体的にはどのようなイメージですかね?
村本さん:例えば「睡眠スコア」に基づいて、その人に最適なマットレスや枕を提案するシステムです。その人の睡眠事情や睡眠の癖などの「データ」を取得できれば、最適なレコメンドができますよね。AIやテクノロジーが発展したからこそ、できることだと思います。
最近はスマートリングを使って「睡眠状況の可視化」ができるようになりましたが、それを元に商品を提案する・選ぶという動きも一般化していくでしょう。
── そういった際に寝具の機能や役割が明確になっている「エビデンス」の仕組みや、それを説明できる「人」の役割は重要になっていきそうですね。今日は素晴らしい話をありがとうございました!


寝具大手で約38年のキャリア。市場調査、商品開発をはじめ、多様な販売チャネルでの営業を経験。商品企画・販売企画・新規店舗出店まで、事業全般を網羅する幅広い経験が強み。お客様のニーズを深く捉え、市場に響く商品と販売戦略を実行し、売上拡大に貢献。
一般社団法人 日本寝具寝装品協会HP:https://www.jba210.jp/