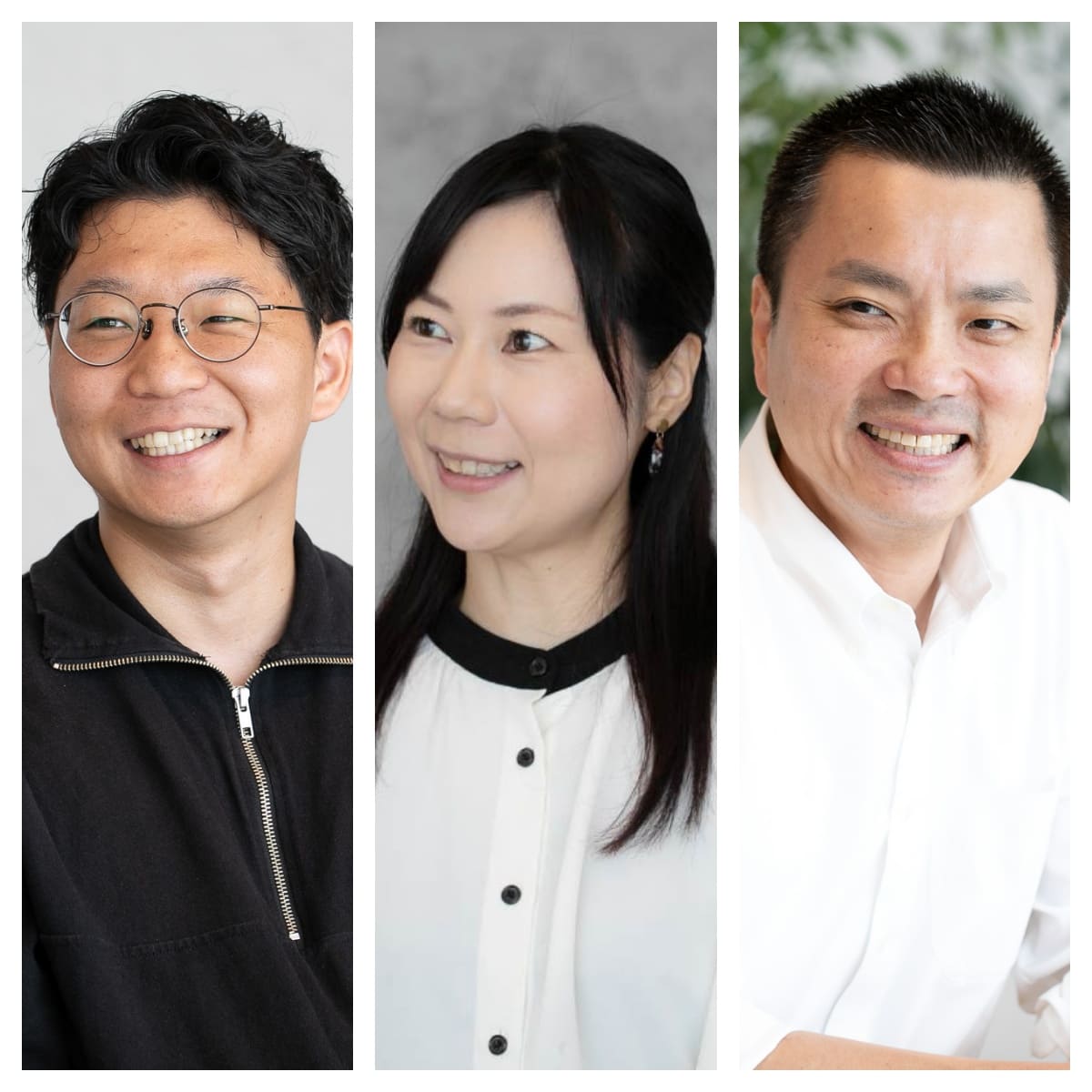
自動車の内装材に用いられる高機能な合成皮革の分野で、世界有数の技術力を誇る共和レザー株式会社。そんなモビリティの会社が、ファッションや日常生活に寄り添うブランドとして、2021年にスタートさせたのが「Sobagni(ソバニ)」プロジェクトだ。
前編では、ブランド立ち上げの背景や構想について、事業部長の柳川大介さんと、企画を担う鈴木賢さんに話を伺った。
後編では、実際にその現場を動かしているプロジェクトメンバーにフォーカス。営業やデザイン、素材調達など異なる分野の専門性を持つ3人が、どんな思いでこの挑戦に向き合っているのか。Wellulu編集長・堂上研がウェルビーイングの視点から、「プロジェクトに関わる人たちの幸せ」に迫る。

岩井 吉則さん
共和レザー株式会社 モビリティ事業部 商品開発ユニット 商品開発部 企画室長/経営企画センター 経営企画部主査

新村 早苗さん
共和レザー株式会社 Sobagni事業部 企画部 東京営業所
デザイナーとして、新商品開発、画像制作やwebの商品ページ制作を担当。2025年より東京営業所に移り、新プロジェクトに参加する。

山本 起生さん
共和レザー株式会社 Sobagni事業部 業務部 東京営業所
ウレタン合皮の原反調達に携わったのち、2025年より「Sobagni」プロジェクトに参加。原反調達や契約関連などの社内事務を担当する。

堂上 研
株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長
1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。
共和レザーが仕掛ける新プロジェクト「Sobagni(ソバニ)」

堂上:前編では、事業部長の柳川さんと、企画部 主任の鈴木さんに、ブランド「Sobagni(ソバニ)」立ち上げの背景や想いを伺いました。後編では、その構想を実行に移している現場メンバーのお三方、新村さん、山本さん、岩井さんにご登場いただきます。
まずは、それぞれ自己紹介からお願いします。
新村:企画部の新村です。地元・浜松で入社し、これまでは画像編集やECサイトの商品ページのデザインなどを担当してきました。浜松のSobagniオフィスで商品撮影に関することや、画像編集などを担当してきました。新プロジェクトの「Sobagni(ソバニ)」に携わることになって、2025年5月に初めて東京に引っ越してきたばかりです。

堂上:それは大きな変化ですね! 実際に暮らしてみて、東京はいかがですか?
新村:とにかく刺激的です。街も人も活気があって、毎日新しい発見があります。生活スタイルも浜松とは大きく違うので、東京に暮らすお客様の目線でも物事を見ることができるようになった気がします。その気づきを、ブランドづくりに活かしていきたいです。
堂上:僕も大阪から東京に出てきた時、同じようにワクワクしたのを思い出します。大学受験の日、あまりにも東京が刺激的で、母に「帰らずにもう1泊する」と電話して。実際はホテルを取ってなくて、歌舞伎町のマクドナルドで夜を明かして、始発で渋谷に行ったんです。ハチ公前のベンチで寝落ちして、写真を撮ろうとした観光客に「ちょっとどいてください」って起こされたのはいい思い出です(笑)。新村さんも、きっと東京でたくさんの経験を積まれていくのでしょうね。
山本:業務部の山本です。僕も今年の5月から東京に赴任しました。バイクや車が好きなので、正直なところ東京転勤は気が乗らなかったのですが(笑)、今は新しい生活を楽しんでいます。
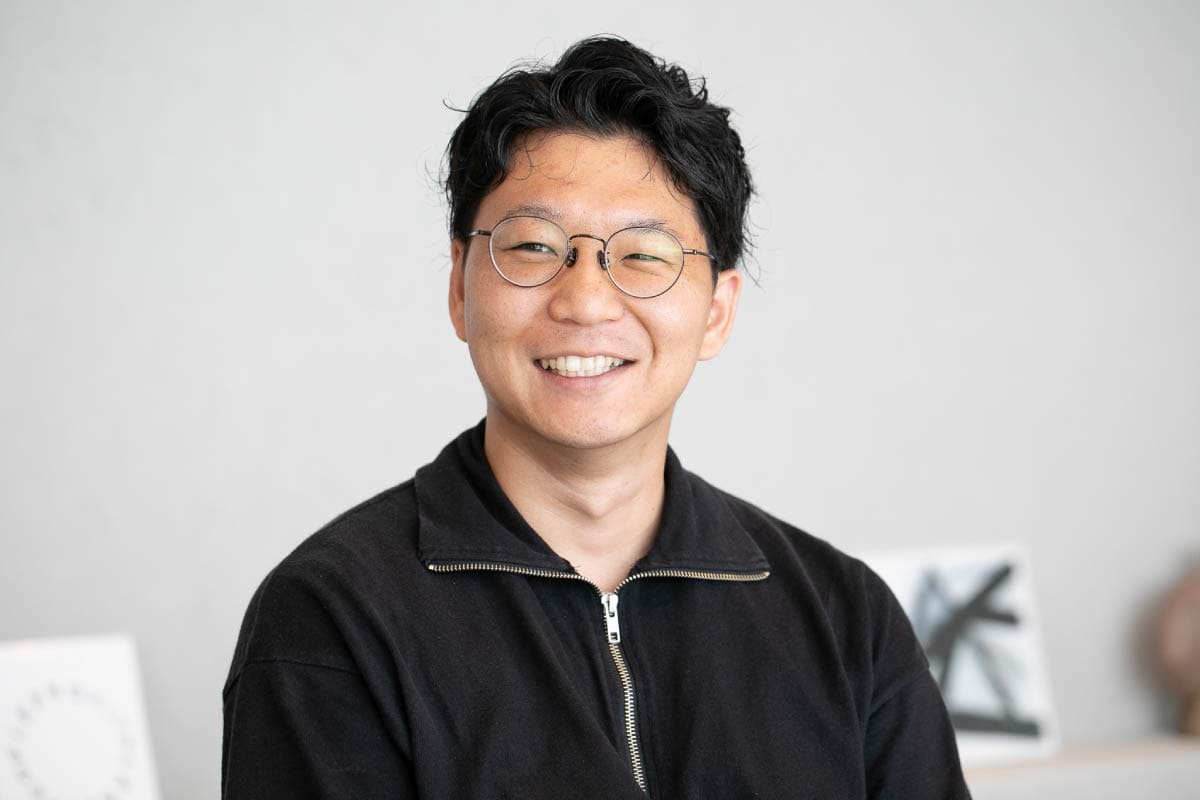
堂上:たしかに、バイクや車好きには東京の道はなかなか走りづらいですもんね。でも、きっとここでも新しい発見がありますよ。
山本:そうですね。以前は、原反(加工前の素材)の調達業務を担当していました。その経験を活かして、今は「Sobagni(ソバニ)」での原反調達や社内での仕組みづくり、契約関連などの業務を行っています。
岩井:私は1999年入社で、3人の中ではいちばん社歴が長い岩井です。
堂上:お、それは僕と同い年かもしれませんね。勝手に同期感あります(笑)。
岩井:入社当初はウレタンの工場勤務でした。その後は浜松と東京で営業を経験し、現在は企画室に在籍しながら海外案件も担当しています。アメリカ、中国、インドなど、海外市場に向けた商品の拡販を進めつつ、今回の「Sobagni(ソバニ)」プロジェクトにも参加することになりました。

堂上:海外では、どんなお客様に製品を納めているんですか?
岩井:日本と同様、自動車OEMおよびTier1などの部品メーカーです。
堂上:そもそも共和レザーさんの主力は車の内装ですよね。家具やファッションとはまた別の市場という印象がありますが、ソファなどはやってこなかったんですか?
岩井:かつては家具などのインテリア系も手がけていましたが、今はグループ会社がその分野を担っています。
堂上:なるほど。そして、そこから「Sobagni(ソバニ)」で新たな挑戦が始まったところですね。
僕はみなさんと出会ってから、合成皮革のイメージがガラッと変わったんです。「軽い!」「丈夫!」「水にも強い!」って驚くことばかりで。昔の「合皮」のイメージとはまったく違いました。
岩井:ありがとうございます。昔はファッション用の合皮は、見た目や手触り重視で、耐久性はそこまで求められていませんでした。でも自動車の内装は違います。長期間持ちこたえる耐久性が求められるので、強くてしなやかな素材が開発されてきました。その技術を、「Sobagni(ソバニ)」での新しい展開にも活かしていけたらと思っています。
堂上:共和レザーさんは加工技術を持っているので、モビリティだけでなく暮らしにも広げられる。加工技術の応用で、今後の展開がますます楽しみになりますね。
共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】
世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」
使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。
その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。
「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。
日本人らしさが宿るものづくり

堂上:みなさん自身のウェルビーイングについてもお聞きしていきたいと思います。最近、楽しいと感じること、ワクワクしていることは何でしょうか?
新村:やっぱり仕事ですね。Sobagniでの仕事は今までにないものをゼロからつくっていく挑戦で、毎日が新鮮です。知識や経験を組み合わせながら、チームで意見を出し合ったり、必要な情報を自分で探したり、色んな人に話を聞きに行ったり……。完成に向けて着実に進んでいる実感があって、とても充実しています。
堂上:今のお話には、3つのウェルビーイングの要素が詰まっている気がします。
1つ目は、「誰かのために」という利他的な視点を持って取り組んでいること。
2つ目は、異なる専門性を持つ仲間たちとチームで取り組むこと。
3つ目は、まさに挑戦し続けること。
どれもWelluluが大切にしている価値観です。
プライベートでは、最近何か新しく始めたことはありますか?
新村:じつは、東京に来てから「雅楽」を習い始めました。浜松では茶道をやっていたのですが、東京ならではの体験をしてみたくて。最初は武道や殺陣にも興味があったのですが、調べていくうちに雅楽に惹かれました。

堂上:それはまた意外な選択ですね! どうして雅楽に?
新村:元々「和」の文化が好きなんです。自分を癒すような時間を持ちたくて。雅楽って、西洋音楽みたいにテンポを機械で合わせたりしないんです。周りの空気を読んで、音を重ねていく。それが日本的で、とても奥深くて、面白いなと感じています。
堂上:「空気を読む」ことで音を合わせる。まさに日本人ならではの感覚だと思います。
「Sobagni(ソバニ)」プロジェクトでも、“日本人の心”というのはテーマになっていくんだろうなと思います。音や香りといった五感で感じられるものや、感情が揺さぶられ記憶を思い出せるものたちを、きっと人は「そばに」置いておきたいものになるんだと思うんです。新村さんのそうした感受性や経験は、プロジェクトにも生きてくると思います。
何歳になっても「初めて」を始める人は、ウェルビーイングな人が多いんですよ。東京で新しい一歩を踏み出した新村さんは、まさにその体現者ですね。
山本さんは何をしている時にワクワクしますか?
山本:プライベートでは、車やバイク、スノーボードが趣味で、休日は外に出て体を動かしています。子どもの頃から体を動かすのが好きで、高校生まではサッカー少年でした。大学ではアルティメットの部活をやっていたのですが、今はとくにスノーボードにハマっています。
最近は、彼女の影響でSixTONESの音楽をよく聴くようになって、今度ライブにも行ってみたいなと思っているところです。
堂上:趣味を通じてコミュニティができると、より人生が豊かになりますね。新しい世界に好奇心を持って飛び込めるのも、ウェルビーイングを高める大事な要素です。ぜひその輪を広げていってください。
岩井さんはいかがでしょう? 以前Zoomでお話したとき、ご家族との時間をとても大切にされている印象を受けました。
岩井:普段は仕事に熱中するタイプなんですが、家族と一緒に過ごす時間は、やっぱり安らぎますね。家族との時間でリフレッシュして、良いプレッシャーを感じながらまた仕事に挑む。そんなリズムが、自分にとっての心地よい働き方かもしれません。

堂上:ある程度のプレッシャーがないと人は成長しないですから、良い環境で仕事をしてこられたのですね。岩井さんのように多くの人と出会い、移動距離が長い方は、ウェルビーイング度が高い傾向にあるとも言われています。特に海外での経験は、新しい視点や刺激も多いのではないでしょうか?
岩井:そうですね。出張先で、自分たちの商品が実際に使われているのを見ると、やっぱり嬉しいですね。僕らの仕事が形になって、誰かの生活の中に組み込まれている。その実感がある部署にいるので、社内の仲間にもその喜びをもっと伝えていけたらと思っています。
心が動くものを、いつも「そばに」。

堂上:最後に皆さんにお聞きしたいのは、「これからの未来、自分のそばにずっと置いておきたいもの」は何か、ということです。
新村:私は「常に挑戦できる環境」をそばに置いておきたいと思います。
それと、日本人は奥ゆかしくて控えめな人が多いからこそ、素晴らしい日本文化をなかなかアピールできていないと思うんです。展示会に行くといつも「こんなに素晴らしい技術があったんですね」と驚かれることが多くあります。奥ゆかしさはとても素敵なことだと思うので大切にしつつ、自分たちでは当たり前と感じていることでも、誇るべき技術や文化をきちんと発信していくことも、これからは意識していきたいですね。
堂上:相手を慮る精神性や、着物・陶磁器など日本各地に根付く文化には、継承すべき価値がありますよね。岩井さんはいかがですか?
岩井:私もやっぱり「思いやり」や「相手を慮る」気持ちを、これからもそばに置いておきたいですね。
堂上:お二人のお話から見えてくるのは、「そばに置いておきたいもの」がそのままウェルビーイングと結びついているということですね。分断や孤立が進む今だからこそ、多様な人たちとどう関わり合い、どう慮り合うかが問われています。
自分の幸せを軸にしつつ、誰かとの対話を重ねていく。そんな「人への愛」や「文化への敬意」が、まさに「Sobagni(ソバニ)」の核にあるのではないかと感じました。
素材と価値を、もっと遠くへ! 「Sobagni(ソバニ)」から広がる挑戦

堂上:みなさんは東京に来られて、新しい挑戦の真っただ中にいらっしゃるわけですが、この先、やってみたいことや挑戦してみたいことはありますか?
山本:自動車向けに開発している素材を、まったく異なる業界で活かしていきたいと考えています。例えば、土木や建設の分野でも、「Sobagni(ソバニ)」のような素材が使える可能性はあると思うので、領域をどんどん広げていきたいですね。
岩井:「Sobagni(ソバニ)」を多くの人に知ってもらうことで、自動車事業にも好循環が生まれるといいなと思っています。日本の技術力が詰まった自動車には、まさに「思いやり」「慮る」気持ちが随所にあると思うんです。たとえば、ちょうどいい位置に収納があったり、操作が自然だったり。そうした“思いやり”や“使う人のことを考えたものづくり”は、ブランドを超えてつながる価値だと思います。「Sobagni(ソバニ)」での新たな挑戦を通じて、既存事業でも新たな発展が生まれると嬉しいです。
堂上:挑戦によって新たな気づきや出会いが生まれますから、既存事業でも必ず良い影響を与えると思います。新村さんは今後やってみたいこと、ありますか?
新村:周りに30代の子育て世代の女性が多く、皆さん家族のために忙しくされていて、自分の時間を後回しにしている方も多いと感じます。そんな方たちが、自分のために少しでも「癒し」や「ときめき」を感じられるようなアイテムをつくっていけたらと思っています。
堂上:すごく共感します。子ども向けのアイテムでも、ただ消費されるのではなく、親子で愛着を持って長く使えるような“そばに置いておきたいもの”をつくっていけるといいですよね。ぜひこれからも一緒に、挑戦と対話を重ねながら、プロジェクトを育てていきましょう。
今日は本当に、素晴らしいお話をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました!

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】
「もったいない」から生まれた「Sobagni」のアップサイクル
「まだ使えるのに、捨てられてしまう素材」に新しい命を吹き込み、価値ある素材へと生まれ変わらせるSobagniのアップサイクル。それは単に「ごみを減らす」だけでなく、素材や道具に込められた命や想いを尊び、ものを大切にする気持ち、社会や地球に対して責任を果たすという想いを大切にしている。
その取り組みの1つが、アップサイクル素材「Wフェイス」。高級車のインテリアに使われる合成皮革は、裏側にほんの0.1㎜の汚れや傷があるだけで自動車用としては不良品になってしまう。そこで裏面が規格外になったものを、表側と同様に樹脂でコーティングし、リバーシブルで使えるように再加工。両面を樹脂でコーティングしたSobagniオリジナル素材に生まれ変わらせている。
1つの素材を活かすことから始まる小さな循環を、社会全体を支える大きな流れへと育てていくことで、Sobagniは「もったいないの心」を未来の世代へ受け渡している。





1999年、共和レザー株式会社に入社。モビリティ事業でアメリカ・中国・インドへの製品拡販を行いながら、「Sobagni」に参加する。
https://sobagni.jp/