
私たちの身体を形づくる、アミノ酸。このアミノ酸の可能性を追求し、社会課題の解決や人・社会・地球のウェルビーイングへの貢献を目指してきたのが、味の素株式会社だ。
同社のバイオ・ファイン研究所では、最先端のバイオ・ファイン技術を駆使して、新しい医薬品や素材の研究・開発に取り組み、社会に革新をもたらしている。
今回は味の素株式会社の執行役常務であり、バイオ・ファイン研究所所長を務める髙柳 大さんに、研究者としての原点と、イノベーションを生み出し続ける組織のあり方について、Wellulu編集長の堂上研が話を伺った。

髙柳 大さん
味の素株式会社 執行役常務/バイオ&ファインケミカル事業本部 副事業本部長/バイオ・ファイン研究所長/川崎事業所長

堂上 研
株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長
1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。
「見たことのないものを、この目で見てみたい」好奇心が導いた研究者への道

堂上:今日は髙柳さんの過去から現在まで、じっくりとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
髙柳:こちらこそ、よろしくお願いいたします。
堂上:早速ですが、髙柳さんはどのようなお子さんだったのですか?
髙柳:私は愛知県出身で、周りは田んぼばかりの田舎で育ちました。小学3~4年生の頃のことですが、よく自転車で冒険に出かけていました。「今日はあっちの方へ行こう!」と決めて、その方向へひたすら進むんです。
堂上:目的地は決めずに、とにかく進むんですね!
髙柳:はい。どこまで行っても、大体田んぼなんですけどね(笑)。それでも、初めて見る用水路を見つけたり、新しい発見があることもありました。進んでいくうちに、いつの間にか辺りが真っ暗になって、帰れなくなってしまうんです。すると、近所の交番からお巡りさんが探しに来てくれて、パトカーで家に送ってもらうことも。当然、親からはこっぴどく叱られました。
堂上:すごい原体験ですね(笑)。
髙柳:それでも懲りずに、次の日は別の方向を決めて冒険に出かけるんです。
堂上:その遊びを思いついたきっかけは、何かあったのですか?
髙柳:子どもの頃から「見たことのないものを見たい」という気持ちが強くありました。本を読んで知るよりも、実際に自分の目で見て、「ああ、こうなっていたのか」と納得したかったんです。
堂上:その好奇心が研究者の道へとつながっているわけですね。
髙柳:今振り返ると、まさにそうですね。学校の勉強では、高校生まで数学や物理が好きでした。やはり、物事の仕組みを理解して「腹落ちする」瞬間が面白さにつながっていたんです。

堂上:そこから化学分野の研究者になっていく経緯をお聞かせください。
髙柳:大学進学を考えていた頃は、天文学に興味がありました。「まだ解明されていない宇宙の謎を解きたい」という思いがあったんです。
堂上:いろいろな分野に興味が移っていったんですね。
髙柳:そうですね。昔から、ひとつのことに熱中してしまう性格なんです。その頃は、天文学を研究するために応用物理を学びたいと考え、大学に進学しました。
ところが、大学では部活に熱中してしまったんです。
堂上:今度は部活ですか!
髙柳:大学では弓道部に入部し、弓道に没頭していました。部室に寝泊まりし、弓を引く毎日でした。
入学時には学部しか決まらず、2年生に上がるときに学科が決まる仕組みだったのですが、成績が悪くて希望していた応用物理学科には入れず、化学科に進むことになったんです。
堂上:そこで天文学は断念せざるを得なかったんですね。
髙柳:その後、化学の道に進み有機合成化学に出会って、また熱中してしまうんです。
堂上:本当にひとつのことに熱中するタイプなんですね! 有機合成化学のどんなところに魅力を感じたのでしょうか?
髙柳:実験が本当に面白いんです。学生がやる実験なので、どうしても精度が低くて、予期せぬ変化が起こることがあります。薬品の量が少し多かったり、不純物が混ざったりすることで、化学反応の温度が予想よりも高くなってしまうことも。
原因はすぐにはわからないのですが、分析してデータを集めていくと、まるで推理小説のように少しずつ謎が解き明かされていきます。毎日考えて続けて、原因がわかって「ふっと腹落ちする瞬間」が訪れると、今まで感じたことのない感情が湧き上がるんです。
堂上:そこで、髙柳さんの研究者としての歩みがスタートしたんですね。
入社1年でアメリカ留学へ。“挑戦”と“考えること”が自身を成長させる

堂上:味の素に入社したのは、どのような経緯だったのですか?
髙柳:大学院に進学して、有機合成化学を6年間研究したのですが、その先を考えたとき、アカデミアに残るか、企業で研究するかとても迷いました。最終的に企業を選んだ理由は、有機化学を突き詰めて行くなかで、人の身体への作用に対する興味が湧いたことでした。
そこで、味の素株式会社と縁があり、面接を受けることになったんです。
堂上:どのような面接だったのですか?
髙柳:当時の医薬の研究所の所長と、化学プロセスの研究所の所長の2人と、ホワイトボードに構造式を書きながら1時間半ほど議論を繰り広げました。企業で働く研究者の方たちとの議論は、私にとって本当に楽しい時間でした。
そして、大学の研究室に「合格です」と連絡をいただいたんです。
堂上:それはうちの会社でもぜひ取り入れたい面接方式です!
髙柳:採用の場面では、正解がある問いに対して学生たちが正解を答えようとする面接が多いかもしれませんが、本当に大事なのは、「問いを立てて」それに対して「考える力」だと思います。
堂上:たしかに、今の時代は「問いの立て方」や「考える力」がますます求められていますよね。企業側が一方的に「正解」を与えるのではなく、一人ひとりの視点や気づきを尊重しながら、共に問い続けていく姿勢が重要だと思います。
味の素に入社して、思い描いていた通りの研究をすることができましたか?
髙柳:入社したばかりの頃は、私は自分の研究力に自信がみなぎっていて、ちょっと尖っていたところがあったんです。入社1年目のキャリア面談で上司に「すぐに留学させてください」と伝えました。
堂上:それはかなり尖っていますね!
髙柳:自信があったので、世界で自分の力を試したいと思ったんです。上司からは、「1年で特許を申請できたら、留学を許可する」と言われて、「やってやる」と医薬品の研究に没頭しました。実際に特許申請をして、アメリカへ2年間留学できることになったんです。
堂上:有言実行、素晴らしいですね。アメリカでの経験はいかがでしたか?
高柳:本当に化学のバケモノのようなすごい人たちばかりで、鼻をへし折られる毎日でした(笑)。でも、この世界レベルへの挑戦が非常にいい経験になりました。
堂上:どんどんとチャレンジできる環境があるというのは、まさに味の素という企業のカルチャーのひとつなんですね。
Welluluで取材した企業の方々からも、「挑戦することができるかどうか」は、働く人のウェルビーイングに深く関わっていると聞きます。失敗が許容され、好奇心を起点に動ける組織は、人も自然と生き生きとし、イノベーションも起きやすい。まさにウェルビーイングな働き方の土壌だと思います。

堂上:当時の社内の雰囲気はどんな感じでしたか? 研究者集団というと、それぞれが一人で研究に没頭しているようなイメージもありますが。
髙柳:みんな考えるのが好きな人たちなので、いろいろなことを相談できる雰囲気はありました。私も15年ほど考え続けていたことがあったんです。
それは「犬がなぜ転ばないのか」。犬を散歩に連れて行くと、体重60kg以上ある大人が15kgほどしかない犬に引っ張られて、バランスを崩してしまうなんてことがありますよね。しかし逆に犬は転ばない、「なぜだろう?」というのが、長年の疑問でした。
堂上:たしかに不思議ですね。僕のサッカーでの経験から想像すると、体幹や重心などが影響しているのでしょうか。
髙柳:その通りです! 犬は重心が人よりも低いので、自分よりも体重がある人を引っ張っても重心が動かず、バランスを崩さないんです。
こういった問いは、インターネットで調べればすぐに答えが出てくるかもしれません。しかし、自分で考えて導き出したいという思いで、長い間、頭の隅に置いていました。
でも、後輩に「犬が転ばない理由がやっとわかった!」と話したとき、彼はきょとんとしていましたけどね(笑)。
堂上:それでも、チームの方々は髙柳さんの探求心や好奇心を感じられて嬉しかったのではないでしょうか。上司や先輩が「共に問いを持ち、悩みながら考える人」であること。その人間味が、相談しやすい環境や「心理的安全性」を生むのだと思いました。
行動することで「助けてもらえる自分になること」の大切さ

堂上:研究者として「尖っていた」時代があったというのが、今の髙柳さんの姿からは想像できないのですが、何か変わるきっかけがあったのですか?
髙柳:じつは、15年前に妻を病気で亡くしているんです。まだ小さかった息子を一人で育てることになり、シングルファーザーとしての生活が始まりました。そのときに、仕事でもプライベートでも、誰かの助けなしでは自分一人では何もできないことを痛感しました。
当初は、「申し訳ないです」「ありがとうございます」と言い続ける日々だったのですが、次第に心境に変化が生まれてきました。「みんなに助けてもらえる自分にならなければならない」と、そう思ったのです。
堂上:そうだったのですか……。そこから、生き方が大きく変わったんですね。
髙柳:そうです。人に助けてもらえるということは、周囲の善意に甘えるということではなく、自分も周りの人に貢献しているということなのではないかと。そうならば、自分はどうすれば、人に貢献することができるだろうか、どうすれば価値を提供できるだろうかと考えることが大切だと感じるようになりました。それから、人への興味や関心が次第に強くなっていきました。
それまでは、研究者として自信を持って進んできましたが、妻を亡くして半年ほどが経ち、仕事と子育ての両立に四苦八苦していたころ、人事部への異動を告げられました。
堂上:研究者としては一段落してしまうような印象ですよね。
髙柳:そうですね。それも仕方ないかなと思いました。しかし、人事部の管理職に就くことになったときに、そこでまた意識を変える出来事がありました。
異動して間もない頃、人事のベテラン社員が、シュレッダーのゴミ袋を交換しようとしていたのを見て、「手伝おうか」と声をかけたんです。すると、「髙柳さんは管理職として、もっとやるべきことがあるはずです。それをやってください!」と言われ、ハッと気づきました。「自分がやるべきこととは何だろう」と。
堂上:そこで、自分に対する問いが生まれたわけですね。
髙柳:「私が人事部で、どんな価値を生み出せるのか」という課題に直面して、「考えるだけではなく、まずは試してみよう」と思考を切り替えることができました。味の素という会社が社会にイノベーションを起こすためには、どんな人や組織をつくるべきか。会社が成長していくシナリオを進めるために、マネジメントを実行するという方向に舵を切っていったんです。

髙柳:人事部で3年間経験を積んだ後、研究企画に異動しました。そこで初めて、研究とお金を儲けるということのつながりを理解することができました。そしてマネージャーとして、研究所に戻ってきたんです。
味の素には現在、食品全般を研究する「食品研究所」とそれ以外のすべてを研究する「バイオ・ファイン研究所」があり、ここバイオ・ファイン研究所では本当にさまざまなジャンルの研究が行なわれています。
堂上:髙柳さんは人事部と研究企画での経験を経て、バイオ・ファイン研究所にどのような組織をつくろうとしているのでしょうか?
髙柳:私がバイオ・ファイン研究所の所長に就任して、今進めているのは、この研究所という組織が一体どのようなDNAを持っているのか、解明するというプロジェクトなんです。
堂上:組織としてのDNAですか! 研究所自体をひとつの生命体と捉えて、研究しようとしているような感じですね。
髙柳:そうなんです。バイオ・ファイン研究所は、これまでにも数々のイノベーションを起こしてきています。人が入れ替わっていても、イノベーションを起こす何かを持っている組織。その「何か」を言語化して、次の世代へと引き継いでいきたいと考えているんです。
研究者たちのアンサンブル――コミュニティと共創がイノベーションを生む
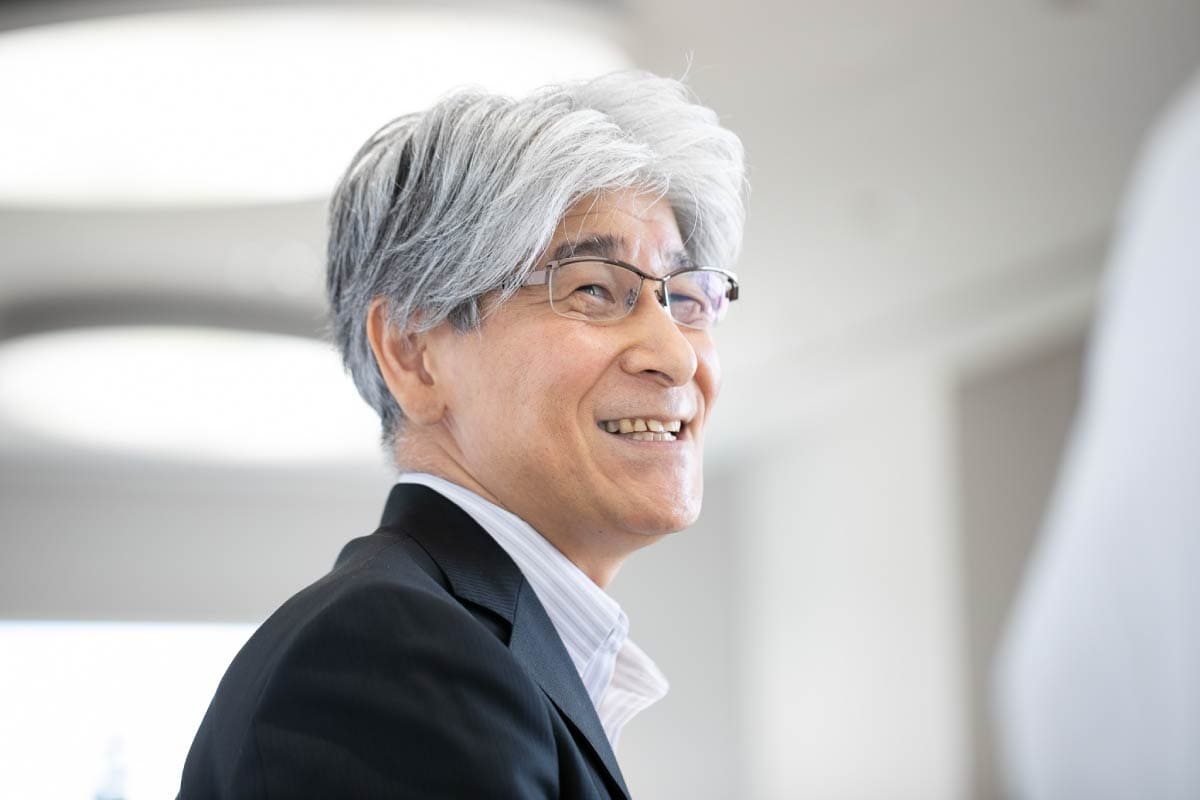
堂上:バイオ・ファイン研究所のDNAを解き明かすプロジェクト、じつに面白い発想ですね。今の段階で見えてきた部分というのはありますか?
髙柳:プロジェクトはまだ道半ばですが、見えてきた中で面白いと感じている点があります。バイオ・ファイン研究所には先ほども言ったように、さまざまな専門分野の研究者が集まっています。専門性の高い研究者たちは、基本的に排他的になりがちです。
堂上:自分の研究が一番だと思ってしまうということですね。
髙柳:ですが、この研究所の人たちは、自分の専門分野に高いプライドを持ちながら、他人の専門分野をリスペクトできるという特性があるんですね。
堂上:素晴らしいDNAですね! 相手へのリスペクトがあるというのは、ウェルビーイングな組織をつくる上でも大切だと思います。
髙柳:自身の研究分野に情熱を持ちながら、他の分野と一緒に新しいものを生んでいける素地がここにはあることが少しずつ見えてきました。
イメージとしては音楽の「アンサンブル(合奏)」です。指揮者が指揮をして音楽を作る「オーケストラ」ではなく、自由に演奏者たちが集まってきて、新しい音楽が紡がれていくような。
堂上:研究者たちが自由に集って、新しいものを生み出していくわけですね。
髙柳:専門分野を越えて、共創できる環境こそがバイオ・ファイン研究所のDNAだと思っています。
プロジェクトという点では、ほかにも横のつながりを作るための仕掛けも進めています。例えば、アジパンダ®トートバックというのも『BF-CONNECT』というプロジェクトから生まれた企画のひとつです。
堂上:髙柳さんも使われている、そのトートバックですか?
髙柳:そうです。もともとは、所内の安全衛生面を考慮して、「パソコンをトートバックに入れて持ち運びましょう」という話がスタートでした。

髙柳:でも、所長命令で「パソコンをトートバックに入れるように」と指示を出すのは、私の感覚とは違う気がして、若手のメンバーに「トートバックを持ちたくなるような仕掛けは何かないか?」と聞いたんです。
その結果、アジパンダがそれぞれの分野で研究しているイラストが入ったトートバックのアイデアが生まれました。
堂上:なるほど! 自分たちが普段行なっている研究の様子がアジパンダのイラストになっていたら、持ち運びたくなりますね。
髙柳:最終的に10種類のイラストがデザインされたアジパンダトートバックを作って、みんながパソコンを入れて持ち運んでくれるようになりました。
堂上:パソコンを安全に持ち運ぶための習慣化を、デザインの工夫によって進めるという、本当に素晴らしい企画ですね!
これまでもひとつのことにのめり込んできた髙柳さんが、いま一番熱中しているのはどんなことですか?
髙柳:研究所のみんなが発案してくれる研究は、どれもが面白くて、アミノ酸発酵製造、工業化、先端医療など、どれも注目しているのですが、さらに面白さを感じているのは、そのアイデアを生み出す人たちの「コミュニティ」なんです。
私の中で、組織とコミュニティという言葉は使い分けていて、組織は静的に固まっているもの。コミュニティとは、もっと動的で、塊としての境界線の曖昧なものだと考えています。
かつてバイオ・ファイン研究所に所属し、今は退職して他の企業で研究している人がいますが、私はその“卒業生”たちを応援しているんです。研究所という組織の一員ではなくなっても、コミュニティの一員として、つながっていければ嬉しいですね。
堂上:組織を越えたゆるやかなつながり、つまりコミュニティが世の中にイノベーションを起こしていくわけですね。
髙柳:その通りです。会社という枠を超えた大きなコミュニティがないと、現代の様々な社会課題を解決していくことはできないのではないでしょうか。
そのため、味の素を退職した卒業生を呼んで、若手社員に語ってもらうような企画も「所長公認」で開催しています。
堂上:髙柳さんが組織やコミュニティを大切にしながら、人と人が交流する機会を積極的に作られているというのが本当によくわかりました。
最後に、髙柳さんは2050年にどのような社会ができあがっていると思いますか? そのとき、ご自身はどんなことをやっていたいですか?
髙柳:具体的な未来像はまだ考えていませんが、人と人とがつながりあうコミュニティがもっと一般化されて、全体がゆるやかにつながっていくような社会が創られていくのではないでしょうか。
私個人としては、サイエンスが好きなので、引退後は子どもたちにサイエンスを教え、その面白さを伝えていければと思っています。それが長年の夢なんです。
堂上:素敵な夢だと思います! 味の素という企業の歴史やミッションを軸にしながらも、個人の好奇心や探求心を原動力に挑戦を続けてこられた髙柳さんのお話には、ウェルビーイングな働き方のヒントがたくさん詰まっていました。本日は素晴らしい話をありがとうございました。


1996年、東京工業大学(現東京科学大学)大学院を修了。味の素株式会社に入社し、新薬開発の最前線で研究に従事する。その後、人事部を経て、研究開発企画部、イノベーション研究所研究管理部長、バイオ・ファイン研究所評価・分析室長などを歴任。2024年より現職を務め、「社会にイノベーションを起こし続ける組織」の創生を推進している。
https://www.ajinomoto.co.jp/